monzansiの観てきた!クチコミ一覧

売春捜査官
劇団EOE
都内某所(東京都)
2014/02/17 (月) ~ 2014/02/17 (月)公演終了
この時代に求められる「1対1」の真剣勝負とは…
「ミスターXは誰なのか?」
『売春捜査官』(作・つかこうへい)は4名で構成する舞台ですが、2013年入団組の離脱により、『劇団EOE』役者陣は2名しかいませんでした。
そのため、史上初という劇団オーディションを開催し、客演に迎えたのが伊織さん です。
この陣容だと まだ 一人 足りないわけですが、「では、誰が出演するのだろう?」とファンの間は疑心暗鬼が拡がっていました。
『劇団EOE』主宰を務める真生氏が 万を辞して 御出演したファン感謝デーは、”養成所スタイル”を捨てる いわば「総力戦」です。
[本番前の宗教儀礼?]
「10分間、人が変わります」と観客へ説明した真生氏。
一体、何が行われる というのでしょうか。
会場中に流れる大音量のロック調BGM。
すると、出演者4名が「シュッシュッ…」と力強く、息を吐き出しました。
この動きは「モチベーション法」ですね。
『絶対エース』平澤氏は「意識を深める状態にします。決して、宗教団体では ありません!劇団です!」と語り、観客を笑わせました。
でも、「呼吸法で意識を深める方法」は、科学的に解説しますと血中酸素濃度を低くすることなのです。これを仏教用語で『瞑想状態』と呼びます。
私は、二人一組となって“大将”真生氏と向き合った際に18歳 佐々木氏 の顔から涙が零れ落ちる場面を見逃しませんでした。
『週刊EOE』(『劇団EOE』を追うメディアです)によると、この『売春捜査官』稽古中、佐々木氏は二度も“脱走”してしまったそうです。まるで『戸塚ヨットスクール』のような表現ですね(笑)
「お客様の前では辛い顔しちゃダメなんだよ」という鋼鉄の意見も あるでしょう。
「舞台至上主義」ですね。
その考えに対し、「いや、舞台裏を見せてもいいんだよ。製作する過程を お客様と共有したいんだよ」とする考え方が、『劇団EOE』=『週刊EOE』そのもの だといえます。
つまり、本番前の「モチベーション法」をファンに公開し、18歳少女(?)の美しい涙を 拝ませてくれること自体が「舞台裏を含めた、『演劇活動』」なのです。
現代に暮らす日本人であれば、体育会系ともいえる こうした「目と目を合わせる」ホットな関係に浸る機会がありません。なんだか羨ましい関係です。
[衣装、照明が 不足したから わかった!大物劇作家『つかこうへい』の構想力]
故・つかこうへい 氏。
彼は慶應学在学中に書いた『熱海殺人事件』でブレークします。
その当時、早稲田大学出身の劇作家・寺山修司氏が、今までの演劇文化を否定した『アングラ演劇』を立ち上げていました。
ところで、『ヘイトスピーチ』が2013年流行語トップ10に入ったことを ご存知でしょうか。
つかこうへい氏の『熱海殺人事件』は、土地の差別や、女性の苦悩を描くわけですが、「40年間経っても結局、変わらないんだな」という不都合な真実を気づかせてくれます。
今回のファン感謝デー公演、通常公演には ない特徴が…。
役者の衣装はおろか、照明も用意れていません。Tシャツにジャージ姿、劇場を照らすのは蛍光灯だけの空間は、文字通り『稽古場』に近い。
ここで、「照明って、劇場に備え付けられるんじゃないの?」という疑問がわきます。
たしかに、照明機材が完備されている劇場も ありますが、「レンタカー等で運び、設置(解体)作業をする」のが一般的な公演。
「1時間後に次の劇団が作業始めるから速やかな撤収を!」(真生氏」ー「ないない尽くし」でした。
しかし、演劇設備で逆風だったからこそ、「役者が放つ肉体エネルギー」「眼差し」「削ぎ落とされた役の本質性」を、観客側も体感できたのではないでしょうか。
「そこにいることが、『つか作品』を造った」のです。
[観客と歩む『劇団EOE』は変化の兆し]
開場中、キャストがふるまっていたのが“お鍋”“焼き鳥”でした。
極寒ですから温かい おもてなし料理は心に染みます。
佐々木氏から勧められたのにもかかわらず、前の方が「いいや」と断わった流れで「お腹いっぱいです」と社交辞令してしまったことを悔やんでます(笑)
『劇団EOE』ファン感謝デーに参加したのは“初”なので、この「振る舞い」が恒例か どうかは 知らない。
ただ、「ファンと歩んでいく」は随所に散りばめられている舞台でした。
そう感じたのが大山金太郎役・真生氏の 次の台詞です。
(伊織氏を)「客演に迎えるんじゃなかった!」
アドリブか台本か…。
今まですと「舞台に真剣に取り組む」姿が、試合中のスポーツ選手を思わせる特徴だったのですが、「舞台を おどける」、そうした柔軟性が発揮されたように感じます。
『劇団EOE』は「役者面会なし」を貫いています。(小劇場界の非常識ですね)
今回、兆しが見える“変化”とは、「舞台造りを通してファンと交流する」(『週刊EOE』も 役割)この劇団ならではの 触れ合い方です。
役者数わずか2名、主宰すら登場せざるをえなくなった『劇団EOE』。これから飛躍したい身としては現在、茨の道かもしれません。
ただ、客演・伊織氏の「内面から湧き上がった感情表現」は見事でしたね。「情熱社会派」としての未来を映し出しました。
今後も期待です。
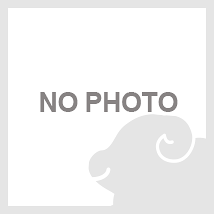
小松政夫×石倉三郎 『激突!人間劇場』~哀愁の人生図鑑~
日本喜劇人協会
三越劇場(東京都)
2014/02/17 (月) ~ 2014/02/17 (月)公演終了
『横浜トヨペット』販売記録を塗り替えた!「小松政夫」と“無責任時代”
日本喜劇人協会第10代会長に就任するコメディアン・小松政夫。
同協会に参与として迎えた石倉三郎と「新作コント」を三連発 披露した後、30分のトークショーを行う。
そこで大御所コメディアンが口滑った“秘話”の数々とは…。
元クレイジーキャッツ・故植木等の付き人兼運転手となる前、『横浜トヨペット』のバリバリ販売員だったことを明らかにした。
「『横浜トヨペット』ひと月の新車販売台数の新記録だったんだって?」(石倉)
「『10』売れれば大したところを、新車で『27』以上販売した。中古車を入れるともっとかな」(小松)
「完全な歩合制でしたよ。8台目までは一律1万円。で、9台目からは3万円になる」(同)
当時小松の月給は70万円近くだった計算だ。(1960年代前半)しかも、たかだか『横浜トヨペット』新入社員の身分である。
新卒社会人の初任給が1万6000円という時代。
20歳前半の新入社員・小松が得た月給は同年代と比較し『約40倍』に膨らむ!
「熱海旅行へ行くと、“大勢連れてきてやった”んだよな。宴会に、芸者遊びやらさ…」
小松がブレークしたキッカケが日本テレビ『シャボン玉ホリデー』。
谷啓『ガチョーン』と茶の間を沸かせた一発ギャグが『知らない、知らない』だった。
小松によれば、新入社員時代のある日、『横浜トヨペット』上司である課長が業績について しつこく文句を続けたらしい。
様子を聴いていた部長(事務機器会社から引き抜いた恩人)がその課長を批判したところ、課長が小松のところへ来て『もう、知らない、知らない』と怒ったそうな。
植木等へ この新入社員時代エピソードを話した小松。
「面白い。テレビでやってみろ」(植木)
『シャボン玉ホリデー』生放送である。
あのギャグは「実話が基」だった。
公演について_
「試みです。次回はちゃんとしたものを やりますので」(小松)
アドリブ劇に近い、方向性の定まらなかったコント。
二発目では「疲れた。疲れた。体力の限界…」と『年齢』を隠せない小松の姿が あった。
パンツ一丁になり、女性用ドレスを着用する。
(当初、石倉が脱ぎ始めると笑い声も起こった)
往年の喜劇人に限界はない。
“小松正夫節”炸裂である。

「r 」
日本演劇連盟
阿佐ヶ谷アートスペース・プロット(東京都)
2014/02/15 (土) ~ 2014/02/16 (日)公演終了
これが「屋上遊園で思索」の『リアル』だ!
劇団名が 堅物「日本演劇連盟」だから、「小劇場界のホープを集めた役者・製作陣」と身構えてしまう。
しかし、実体は、20代、30代の新進役者を中心とする「若手劇団」だ。
アンケート用紙に「劇場に足を運んだ理由は?」項目があったのも、この「日本演劇連盟」というネーミングに惹かれる客を見込んでの措置か。
思わぬ集客攻勢だった。
「作・演の木下伸哉さん(=理事)は 百貨店屋上遊園のベンチで思索する(笑)
三人連れがアトラクションの行列に待機。お祖父ちゃん、お婆ちゃん、両手に挟まれているのが5歳くらいの お坊ちゃん。
家族団欒の横で大人男性が“独り思索中”とはね…」(舞台通M氏)
『ひとりディズニー』なら ともかく、それが百貨店屋上遊園であれば、確かに“ヤバイ奴”だろう。
この現実は木下氏も自覚済み。
登場人物のキャラクターに反映させる。
常連美女ー上島・東ヶ崎 恵美(舞夢プロ)
毎日来園し、自ら『ロミオ』と名付けたパンダ・アトラクションにまたがる習性の持ち主だ。
「“闘牛並”の場面転換力でしたね。叙述的な台詞とオペラショーが観客を圧倒させた。
“乱れ髪”すら気にしないヒロイン精神です。
そうそう。彼女といえば、60秒間の休憩を宣言する役割も。
わずか90分の舞台で休憩時間があるのは珍しいですが、カウントダウンが開始すると同時に、観客は一斉に立ち上がりましたよ」
小劇場の座席は 『満員エレベーター』とも称されるから当然か。他劇団でも導入すれば この“立ち上がり現象”は風物詩となる。
「こんな百貨店社会は存在しない。登場人物は基本 ぶっ飛んでます。
でも、演劇ならではの『質素な夢の国』だと思えた時、木下さんの妄想世界と共鳴できたようで、すごく有意義でした」
百貨店屋上でビールを飲み干す時代は終わった。
爆笑の渦に包まれた90分…。

FLY ME TO THE DREAM 〜夢の欠片の向こう側〜
Succeed Project
六行会ホール(東京都)
2014/01/24 (金) ~ 2014/01/26 (日)公演終了
観客熱狂で呼び出される『マンマミーア!』の「リピート回数」
千秋楽の回、既にカーテンコールは4度目であった。
熱気に沸き立つ観客。
どこで入手したらやペンライトを握り、前方は総スタンディングオベーション。
「せ〜の……ありがとうございました!」と、頭を下げていたのが主演・渡辺 瞳だ。
舞台通M氏は苦言を呈す。
「前列に座るリピーター客が求めているのは一種のトーク。
ミュージカル養成所が母体だから、友人、保護者が大挙して集まったはず。笑顔をみせ、手を振って、幕が降りたら“はい、おしまい”だと、日頃から支えてる分、不満が残るでしょう」
老舗『ミュージカル座』が定期的に公演場所に選ぶ「六行会ホール」。
「Succeed Project」の本公演『FLY ME TO THE DREAM ~夢の欠片の向こう側~ 』 は、まるで同座を含む先達ミュージカル劇団へのリスペクトだった。
使用したミュージカル楽曲は『ミュージカル赤毛のアン』『レ・ミゼラブル』『マンマミーア!』などなど。
全寮制ミュージカル専門学校生徒に扮したキャスト陣が、忠実に唄って踊る。
「物語は ありきたり。男性インストラクターとの恋模様は、20代に向かって投げた球かな」
赤ふんどしを締めたイケメンの生尻を、渡辺 瞳がビシビシ叩く衝撃場面も。
「女子高校生は美術教師(役)の尻を叩かないでしょ。
笑い声が少なかったのが気になる。
女性客は引いちゃった」
「劇団スタッフにも疑問を持ってるんです。遅れた客へ『視界の妨げにならないよう頭を低くしてください』と要求するのはいい。ただし、なかには“四つん這い”で這っていく若い客も。
『そこまでしろ!』とは言ってないけど、真面目な人は結構いますからね」
挿入歌を聴けば、あの頃のミュージカル映画が思い浮かぶ。
カップルで鑑賞していた観客も、一人で録画再生した観客も。
むしろ、「偉大なミュージカル」を 紹介するダイジェスト版のようだが、残念ながらオリジナル・ミュージカルは記憶に残らなかった。

嗚呼素晴らしきサラリー人生
東京サムライガンズ
劇場MOMO(東京都)
2014/02/13 (木) ~ 2014/02/16 (日)公演終了
本番を一時中断させた180cm超「榊原仁」の「B級ミス」
―こんなこと、前代未聞―
遭遇した男性客(後方座席)は「これも演技なんじゃ…」と絶句。
そのミスは開演直前に起こった。
主演・船原孝路がかかるべき“ドッキリ”のトラップを、暗転中に共演・榊原仁が踏んでしまったのだ。
「初日だからね…もう一回やろう!もう一回」
作・演出を務めた主宰の加藤隼平は、何もなかったかのように始まった本番を中断せざるをえなかった。
舞台通M氏が語る。
「そのまま無視することもできたハプニング。本番を中断してまで“笑い”を取りにいく攻撃性ですよ」
失踪した広告代理店社長のバカ息子(アメリカ在住)が、ある日突然、社長に就任しなければならなくなった設定。
「前半は『社会人養成講座』だった。“通勤の方法”“名刺の渡し方”をバカ息子に解説する手法だが、観客も教えられているようで恥ずかしい」
加藤隼平にはサラリーマン経験がない。
通常、未経験の社会人はサラリーマンに対し漠然とした「コンプレックス」を抱えている。
前半の『社会人養成講座』も、加藤の“サラリーマン・コンプレックス”が響いた結果なのだろうか。
「後半になるにつれ、ボルテージは上がってきた。全体として話の筋もいい。映像・音楽の演出がエンタメ性を高めた」と、評価したいポイントも。
終演後「大変、申し訳ありませんでした」と謝った榊原仁。
これも『社会人養成講座』で習得した技らしい。

『白痴』 『コーカサスの白墨の輪』
TOKYO NOVYI・ART
シアターX(東京都)
2013/03/22 (金) ~ 2014/06/07 (土)公演終了
役者を涙させる菅沢 晃
『東京ノーヴイ・レパートリーシアター』は、ドストエフスキー、ブレヒトといった偉人作品を、翻訳劇に囚われず提供してくれる、稀有の劇団である。
その上演時間3時間30分は 削ぎ落とす無駄がない。
一般的な演劇だと、ゲネプロ(公開練習)から千秋楽へ向かって「進化していく」順路だろう。
帝国劇場ミュージカルは通常、本公演前に レビューを設ける。このチケット料金はS席につき約2000円安価である。
一方、ヨーロッパ・オペラ劇場に多い、日替わり上演を行うのが「レパートリーシアター」。
『レパートリーシアターKAZE』等の劇団は名が知られているが、日本においては圧倒的に導入された例のないシステムだ。
今回『白痴』を観劇し痛感したことは、「役者に新鮮さ」が与えられるプラスであった。
セリフを聞けば、『東京ノーヴイ・レパートリーシアター』の『白痴』『白墨の輪』シリーズは、メインキャスト以外 稽古量は十分ではない 可能性を伺わせる。
しかし、菅沢 が 魔術師である事実は変わりない。
ムイシュキンが スイス療養中に出逢った娘の回想をすれば、隣にいた役者は号泣してしまう。
照明は菅原ピン。
涙する場面ではない。
ところが、回想シーン後も、鼻水が止まらなかったのが麻田(アレクサンドラ)であった。
「冷たい女」の役柄を否定。
彼は人の心に礼儀正しく侵入し、それを癒すパワーを発揮した。もはや宗教だ。
舞台進行に支障が生じるギリギリの線である。
こうした事態は、「役者に新鮮さ」が与えられるレパートリーシアターでなければ 再現しえない。

Girls, be a mother【アンケート即日公開】
劇団バッコスの祭
シアターグリーン BOX in BOX THEATER(東京都)
2014/02/05 (水) ~ 2014/02/11 (火)公演終了
いつも隣に与謝野晶子
与謝野晶子は大阪府堺市出身だ。
歴史教科書に掲載される写真の女性が話し出すと、案外「大阪の おばちゃん」だったのかもしれない。
そう思わせる辻明佳の演技だった。
開演15分前に来場した客には「与謝野晶子クイズ」のシートを渡す。
出身地に関する項目があり、舞台の幕開けとともに「回答」してしまったのが本人・与謝野晶子(辻明佳)だった。ところが、2.3問の解は明らかにせず、「与謝野鉄幹と設立に関わった日本初の男女共立大学は何か」を考察していた観客も多い。もちろん、集中しなければ分からない。
『劇団バッコスの祭』が提案する、もう一つの「舞台の楽しみ方」であった。
NHK経営委員の長谷川三千子埼玉大学名誉教授が男女共同参画に反対する論説を産経新聞紙上で発表していた。
今、改めて「ウーマンリブ」に社会的関心が集まる状況だ。
政府が中心となり、「ライフ・ワークバランス」を推進する動きはあるが、若い世代の女性からすれば「女性が働きやすい環境をつくってほしい」「託児所を増やしてほしい」という要望も聞こえる。
一方、「専業主婦回帰派」の女性は見過ごされていた現実がある。
首都圏在住・20代の女性(大学生)は、「男の人って大変。それに比べれば女性は結婚して仕事を辞めることもできる」と話す。
世界をみると、主要国のトップを女性政治家が務めることは「普通」になった。
ドイツ・メルケル首相、韓国・朴大統領、タイ・インラック首相…。
日本に女性首相は育つのか。
ここで疑問が浮かぶのは、日本の国政選挙における投票者を分類すると、総投票者、総得票率ともに女性が男性を上回るデータである。
公益財団法人「明るい選挙推進協会」が2012年12月16日衆院総選挙から全国188選挙区を抽出し調べた統計資料。
全国30歳〜34歳の世代男女別投票率は、男性45.69%に対し、女性48.51%だった。(約3%の開き)
実に55歳〜59歳までの年代は、「女性優勢」である。
日本の衆院・女性議員比は7.9%だが、公職選挙法に男女差別はなく、女性有権者の方が より参政権を行使しているなかの“マイノリティ”を、私たちは どう考えればよいのだろうか。
※続く(次は舞台)

東京パフォーマンスドール PLAY × LIVE 『1 × 0』(ワンバイゼロ)アンコール公演エピソード1&2
キューブ
CBGKシブゲキ!!(東京都)
2014/01/31 (金) ~ 2014/02/11 (火)公演終了
ワールドクラスの文化交流、TPD
日本の心「祭り」を第二部「ダンスサミット」に取り入れた。
ディズニー映画『アラジン』。
宮廷内の踊り子も着用するだろう、煌びやかな衣装のTPDが そこにいた。
舞台ステージ上に散らばったボックスを叩く。そうすると、センサーが反応し、赤、青、緑などのカラーが点滅するのだ。
TPDメンバーは両手に「バチ」を抱え、全力で歌いながら、曲のリズムに合わせ連打しなければならない。
一度、他メンバーのリズムに遅れてしまえば、「ボックス・カラー」が何色かにより、そのミスが浮き彫りになる。出演者泣かせのパフォーマンスだ。
終演後、ダンスサミットを楽屋モニターで観ていたという板倉チヒロは、若干の涙を目に浮かべた。
「彼女達も公演中、悩んだり、泣いたり、といった姿がある。でも、ライブは それを覆す出来で、感動してしまった」
TPDは公演日程が進むにつれ、第一部「エピソード2」のアドリブにも幅を効かせ始めた。
2013年9月、アルゼンチンで開催されたIOC総会。フリーキャスターの滝川クリステルさんが演説した そのセリフに着目した。
※ネタバレ箇所
ステージから透ける彼女たちの試行錯誤だった。
再公演は第二部「ダンスサミット」を拡張。
1時間40分のうち、半分は いわばTPDワンマン・ステージである。
ペンライトが発光しない空間。
アンコール曲なのに、決して立ち上がろうとしない観客もいる。
しかし、この演技+映像+ダンスがもたらす「感動」の最終幕は、板倉のいうとおり、「本物」であった。

HOME SWEETS HOME 【ご来場ありがとうございました】
青春事情
ザ・ポケット(東京都)
2014/02/05 (水) ~ 2014/02/11 (火)公演終了
近くの友より遠くの親戚?
観劇後、街のケーキ屋さんに行く日が増えそうな舞台である。(女性なら特に)
なぜか、店のドアを開けた客に一般人がおらず、「関係図」が唐突に成り立ってゆく展開は違和感を抱かせるが、よく出来たハッピーヒューマンドラマだ。

東京パフォーマンスドール PLAY × LIVE 『1 × 0』(ワンバイゼロ)アンコール公演エピソード1&2
キューブ
CBGKシブゲキ!!(東京都)
2014/01/31 (金) ~ 2014/02/11 (火)公演終了
進化し続ける、TPD
「昨年の夏公演は、周りと衝突してしまう姿。でも、アンコール公演では“弱さ”を出せたらいいなと思って演技している」
平均年齢15歳の東京パフォーマンスドール(TPD)小林は終演後、次のような感想を語った。
最新映像技術を駆使した舞台×映像。
白を基調とする無機質な空間。
そこに、『シブゲキ!』前身の映画館時代、映写機も流していただろう映像を、“セットというスクリーン”へ映し出す。TPDが共演者だ。
TPDのパフォーマンスは、巷に形容される“アイドル像”を否定する洗練した動きが特徴であり、ユニット名にふさわしい都会的雰囲気。
「千秋楽まで成長できたらいいなと思ってる」
プロローグは毎回、同じ内容だ。
確かに、昨年の公演だと、「渋谷の地下に落ちた」その状況を、TPDメンバー自身も戸惑っているように思えた。観客はゲーム感覚で、バーチャルに、彼女たちの困り顔を観察していたのかもしれない。
だが、アンコール公演のTPDは、名作小説に触れてきた年季世代すら、メンバー同士の「試練」「友情」へ向き合わせ、新たな価値観を吸収させてあげることができる。そんな舞台だった。
客層は95%以上が大人の男性だ。もし、女性やシニア世代、子どもが その演技とパフォーマンスを目の当たりにすれば、スタイリッシュな世界に圧倒されるだろう。
『ダンスサミット』も、前半「バーチャル・ミステリー」と同じく、進化をし続ける。(一部と二部の落差は縮まった)
グレープフルーツはフレッシュだ。
そして、TPDは木の枝に ぶらさがった、生育中のグレープフルーツである。
モダン衣装、身体的なキレを重視した振付け、一点を見つめた笑顔が、劇場を明るく照らす。
※ネタバレ箇所
舞台×映像の融合は、観客にとっても、TPDに とっても、高速で進んでいた。

我らがジョーク
多摩美術大学 映像演劇学科 FT 3年生Aコース
多摩美術大学 上野毛キャンパス 演劇スタジオ(東京都)
2014/01/31 (金) ~ 2014/02/03 (月)公演終了
どこか傍観者を装う演技
まず、25分遅れて観劇したため、彼らの『我らがジョーク』の本質的完結に触れることができたかといえば、大いに疑問である。
この舞台は大学演劇学科の稽古場と、キャンパスからの脱獄を図る二部構成だ。多摩美大が2時間の長編作品を上演すること自体、珍しい機会であるが、今回はストリートプレイを やや試みたのだろう。
通常、年配男性に「理解できないな」とコメントされる彼らの作品は、幾何学的な台詞やダンスを多用する傾向がある。そうした過去公演と比べれば、『我らがジョーク』は演劇スタジオというリアリズムに則った空間設定、稽古中であるという話の筋はしっかりしているかもしれない。
ただし、私は彼らが「ストリートプレイ」を追求せず、「多摩美らしさ」を隠せなかったことに対し、安堵している。
25mほどの長い舞台空間に、数人の役者同士が「群」をなす。
それは、演技中だろうと、休憩中だろうと、関係ない。
“非常に自然な、現代の若者における内輪”のリアリズムを表現した「コミュニケーション」が、その片方の群れAで交わされる。当然ながら、もう一方の群Bでも交わされるわけだが、この「コミュニケーション」が互いに影響し合い、新たな展開を作り出すことはない。
つまり、演劇スタジオなる確固たる空間設定がなされておきながらも、右と左では“異なる舞台が同時並行に、全く同一の目的を持ち進む”構成である。

幸せを運ぶ男たち【たくさんのご来場ありがとうございました!】
アナログスイッチ
高田馬場ラビネスト(東京都)
2014/01/31 (金) ~ 2014/02/02 (日)公演終了
4時間だって耐久できるトーク
ボロボロ アパート一室の会話である。しかし、まるでトーク番組出演者のような一体感、笑いの方法だった。
単なる内輪の会話ではなく、5人それぞれに「役割」が用意されており、舞台の大部分を占めるだけの「面白さ」がある。
ここ最近、若い作家の書いた脚本は、若い世代しかない感性へ訴えかける傾向をもつ。それが、昔流の表現でいえば「ナウい」わけだ。中年世代からすると違和感かもしれない。
本作はシチュエーションコメディという枠組みながら、若い世代限定「ナウい」を連発した。そこに、一種のトーク番組が登場してしまうことは、決して無関係ではないはずだ。
上演中、主人公・唐沢(山下 征志)が、幾度となく液晶テレビを視聴する。その顔を座敷童たち が「幸せそうだ」といいながら、実は退屈な、非生産的に沈む表情を意図して浮き彫りにする。
彼は、観客と同じ立場だろう。
「観る」ことには変わりない。
ところが、その虚しい日常を、「見えない客観性」である座敷童たちに意見させたところが、メディアをえぐる演出効果を感じる。
劇場空間で「観る」「笑う」特権性を観客側へ問う、卓越した窓だろう。

REizeNT~霊前って...~
junkiesista×junkiebros.
シアターグリーン BIG TREE THEATER(東京都)
2014/01/29 (水) ~ 2014/02/02 (日)公演終了
この葬式ショーに参列していることが嬉しい
「お葬式をミュージカルにしちゃえ!」というコンセプトであれば、最近、近親者を亡くした観客は「不謹慎にも程があるぞ!」だろう。
だが、一人ひとりのキャラクター性が造られた新喜劇だったため、そうした苦情すら生じないはずである。
帝国劇場『レ・ミゼラブル』のような、目を閉じ、聴きいってしまう歌声ではない。まるで、映画『ロッキーホラーショー』のミュージカル挿入部のごとく、大した意味のないソングは、我々の眼前に「アップ」で迫ってくる。
「もしかしたら、そうなのではないか…」
葬式の真相を、私自身は早く把握しまった結果、ラストまで待つ間のコメディすら疎ましく感じた。
ただ、 この劇団の良い点をあげれば、バナナの叩き売り だ。
つまり、完全なる新喜劇ミステリーを追求せず、観客が考察中だろう「真相」を早出しする器量である。早い段階から知った観客も、この値切りスピードの早さ(コメディは中盤、炸裂が止まったか)なら参加できる。
少なくとも、コメディ・ファンであったり、ミュージカル映画を盛んに鑑賞する人間であれば、足を運び損することはなさそうだ。平日昼のシアターグリーンを満席にさせた事実、(ダンス学校関係者こそ多くみられたものの)それは極めてホットな現象である。

「Reverse Historica」 リバース・ヒストリカ
BIG MOUTH CHICKEN
サンモールスタジオ(東京都)
2014/01/30 (木) ~ 2014/02/04 (火)公演終了
「ゆとり世代」へ対する偏見とコンプレックス
こう記すと、誤解してしまう方もいるが、「演劇のパッケージ」を提供されたように感じた。
戦国時代の織田信長や明智光秀といった武将が憑依という形で現代にタイムスリップする話である。現代人の口からは、「浜田幸一」や「三宅久之」といった故人、果ては「田原総一郎」さえ出てくる。
この舞台は何度も上演され続けた脚本を元に造られているが、特に演出家の意図として、「現代の日本政治」への捨てきれない意欲が見え隠れし、観客も それを期待した。しかし、なぜか政治評論家や政治討論番組のワードが飛び交うだけであり、そこに意味が存在したのか疑問である。
戦国時代の争いから、現代政治の混迷を描くアプローチも有りだっ
たはずだが、それでも今回の まとまった演劇を観ると不必要だったかもしれない。殺陣シーンも、不安なく見届けることができた。
晴天の日の観覧車である。
那珂村たかこが「泣く子も黙る」織田信長を雄々しく演じた姿は本当の憑依だった。日本・インドネシア共同合作映画『キラーズ』(2014年)主演を務めた北村一輝氏は、「野村(主人公の元外資系ビジネスマン)になりきっていた」と述べたが、演じるとは何であるか 洞察させる威厳だった。
沖田桃果の萌え機関車、大門与作のお笑い休憩空間、今若孝浩の肉体スライムは 『リバース・ヒストリカ』の歴史を塗り替える。
私たちは、「昔の人」を特殊なレンズを通してしか観察していない。もし、「自分の祖先」を思い浮かべれば、その人物像も変化する。
横田庄一さんはブラウン管を観て名言を残しただろうか。「あれ、中に人がいるぞ!」と。
織田信長も、きっと、一日経過すればスマートフォンを使いこなし、減税の訴えをYouTubeに投稿。
そして二日後には、政治を諦め、名古屋市内のアイススケート場を滑っていることだろう。

母乳とブランデー
トローチ
赤坂RED/THEATER(東京都)
2014/01/26 (日) ~ 2014/02/02 (日)公演終了
辻親八に酔いしれた
『トローチ』は、一回一錠までと決まった用法のもと舐めなければならない。その名称を語るだけあり、何度もリピート観劇をし「増幅する味」ではなく、一度目の「感動」を噛み締めたい趣向であった。
アメリカ・ハワイ州は、ワイキキの白浜ビーチと青空が数多くの写真にフォーカスされてきた世界屈指のリゾート地である。他のマーシャル諸島と同様、日系移民が暮らす太平洋の島だ。「フラダンス」「アロハ・シャツ」「ロコモコ」「ブルーハワイ」等を日本に広め、文化的な繋がりも深い。
ハワイという海外を舞台としたのにもかかわらず、現地人を「日系」としたため、圧倒するリアリティを確保している。このことは、今まで脚本家、演出家が見落とす対象であった「日系社会」を改めて浮き彫りにし、私たちのアイデンティティを再考させるコンセプトだろう。
文句を告げる観客すらいないのだと思われるが、藤尾一郎役・辻親八氏がトノサマガエルのごとく豪快な演技で存在感を示していた。他の「日系人」がアメリカ・ドラマに出演する俳優のような口調をすれば当然、劇場は笑いに包まれることだろう。翻訳劇だと、吹き替え声優を担当することはあるが、この『母乳とブランデー』は、むしろ英語も交え、70年代ホーム・コメディの当事者であった。
ところが、辻親八氏は ひとりの日本人として、こうした演技に並ぶ。
脚本・太田善也氏は、カナダ映画『人生ブラボー!』を鑑賞され、構想を得た可能性がある。
第一回公演ということは、すなわち旗揚げ公演だ。この冠すら不必要なほど、コメディの見せ方は洗練されており、私は一定数の評価を獲得したと思う。
ソチ五輪を欧州各国がボイコットするかもしれないテーマを、(観客は笑ったが)真剣に扱ったことは、特筆に値する。

四時の籾(しじのしいな)
劇団HumanDustUnion
d-倉庫(東京都)
2014/01/23 (木) ~ 2014/01/26 (日)公演終了
「聖人」吉田松陰が慕われる理由とは
吉田松陰の出身地・山口県旧松本村を訪れると、絶対に発してはならない呼び方が あるという。
もし、部外者が「吉田松陰」と呼び捨てにすれば、地元民は「松陰先生と言いなさい!」と顔を赤面させ、その後の人間関係にさえ支障が生じるらしい。
そんな吉田松陰“先生”を舞台化するのだから、著書や歴史書を読み解き、旧松本村の方々にとっても無礼ではない人物像だったと思う。逆にいえば、「聖人」を描くばかり、亡くなった時は29歳であった、その「若さ」を感じることが できなかったのである。ペリー提督の黒船に潜み、アメリカ行きを試みた冒険心を映すべきだった。
「明治維新」「尊王攘夷」を打ち立てた独立思想の持ち主なのだから当然、「朝鮮征伐」もセットだった。舞台では、「万民一君」の理念が塾生の間を巡るが、身分の違いを乗り越えた思想を説く「聖人」の面しか表さない。
「富国強兵」の善し悪しは議論されるべきだろう。しかし、山県有朋等の国権主義者を輩出した松下村塾の、その攻撃性は描けておらず、やはり「新政府軍」「薩長同盟」側からみた吉田松陰なのである。
私は今、短い文章のなか、七つも四文字熟語を提示した。国政選挙のフレーズを思い出せば、私たちが熱狂した文字数は四文字ないし、五文字の熟語が圧倒的だった。
「政治とは言葉である」という例えもあるが、時代が動き出す際、「キッチリした造語が溢れる」のは世の常である。
日本には人種問題が存在しない。だが、21世紀の今日ですら、山口県人と会津若松市民が腹を割って語り合う状況ではないことを考えると、「戊辰戦争」の遺した影は人種問題に匹敵する。1964年〜1973年のベトナム戦争時、韓国・朴正煕大統領はアメリカの要請に応じ、同盟国最大規模の計32万人を 派兵した。
この部隊は「猛虎」という名を広め、戦闘中を問わない残虐行為ぶりから韓国に対する同国民の感情は極めて複雑である。
NHK大河ドラマ『龍馬伝』にみられるように、「明治維新」という権力闘争を、志の持った脱藩武士達のドラマへ置き換えがちだが、その一方、『八重の桜』の物語も忘れてはならない。
無形文化遺産『隠岐相撲』は、第一戦を闘い、どちらかが白星を取れば、第二戦では白星力士が負けなければならない掟が存在する。これが、離島を生きた島民による「敗者を労る精神」だ。
少なくとも、旧幕府側の武士、民間人を犠牲にさせた思想のバックボーンなのだから、吉田松陰が完全なる「聖人」は あり得ないだろう。そこは、その人物の持つ「人間らしさ」を掴みたかった印象である。
ただ、舞台は、吉田松陰役・大和鳴海の静かな語り調が安らぎを与えていた。他の血気盛んな若者がコメディ要素を出すごとに、その「聖人」が浮き彫りになる構図だろう。
身体観に重厚さが欠けていたのは残念であったが、「幕末の恋愛」には女性客も泣いた。

異邦人
東京演劇集団風
レパートリーシアターKAZE(東京都)
2014/01/20 (月) ~ 2014/01/27 (月)公演終了
青年ムルソーがもつ「知性」と太陽の灼熱
レパートリーシアターKAZE『異邦人』は、青年ムルソーに燈る「知性」を、陪審院という言論空間を通し、大衆社会へ溶け込めえない異質なものとして扱っていた点が印象的であった。元のテーマ性通りである。
第二幕ライトの点滅が、光と影のクロス・パズルを 床空間に現す。それは、2秒間ほどで入れ替わるが、工場の歯車が半回転するように、役者も変わるのだ。

『白痴』 『コーカサスの白墨の輪』
TOKYO NOVYI・ART
シアターX(東京都)
2013/03/22 (金) ~ 2014/06/07 (土)公演終了
スタニスラフスキーで東西融合
ロシアの演出家•レオニード•アニシモフ氏を迎えてのドストエフスキー代表作『コーカサスの白墨の輪』。
スタニスラフスキーシステムは、自然の法則に基づいた演劇理論として、世界中最も権威がある。
彼の出身地・ロシア共和国連邦といえば、東はヨーロッパ大陸に通じ、西はアジアへ通じる地球儀半周分の長さ だ。北米大陸アラスカはアメリカ合衆国の州であるが、帝政ロシアが財政難のため自国領土を売却したことに起因する。
『コーカサスの白墨の輪』を観劇し気づいたことは、三味線を弾き、音響・語り手を担当する講談師。そして、グルジア語の代わりに東北弁の「うん、だべ」で 話すグルジア人であった。しかも、コーカサスの山脈だと、関西弁の「そや、せやろ」も登場する。
『ト音』という日本劇作家協会新人戯曲賞候補作が、標準語と津軽弁を入れ替えた工夫により革新的モチーフとして迎えられた経緯からすれば、改めてスタニスラフスキーシステム、すなわち この理論を応用した演出・アニシモフ氏の先見性を思う。
グルジア共和国は現在、「西側ヨーロッパ社会」の一員を目指す。最終目標はEU加盟であり、NATO参加である。ただ、この国の背にそびえたつコーカサス山脈は、アジア系民族が定着する土地でもある。中央アジアのウズベキスタン・カザフスタン等の国々に地政学的にも近く、トルメクスタン人などの東洋、グルジア人などの西洋が混在する民族空間でもあった。そういえば、『コーカサスの白墨の輪』は、西に位置したオスマン帝国との争いを書く。この国も「東西の架け橋」だった。現在のトルコの首都イスタンブールは、シルクロードで賑わった巨大商業都市である。
せっかくロシアから著名な方が来日し、ヨーロッパ式レパートリー・システムを導入するのだから、講談師や東北弁や関西弁は聴きなくなった観客もいたはずである。その抱く脳裏には、
「コーカサスの文化を緻密に観せてほしい。これこそスタニスラフスキーシステムだろう」
という、反発が渦巻く。
しかし、中盤まで観劇したところで、私も抱いていた この懸念は払拭された。
つまり、金髪カツラを被らず、黒いマジックで顔を修正することは、東洋人=民族混在空間を現す。
あえて東北弁や関西弁などの方言を使うのは、山脈で言語性が変化する、そのニュアンスを伝えたかったからだろう。
結果、文化的本質が 体現されているならば、これを、自然法則に基づいたスタニスラフスキーシステムと呼ぶ。
方言の応用を誰かがアニシモフ氏へ助言したはずだが、標準語を使う兵士に「均一性」「国家」等の概念を与える演出意図があったと感じるのは私だけか。

櫻ふぶき日本の心中
椿組
ザ・スズナリ(東京都)
2014/01/15 (水) ~ 2014/01/19 (日)公演終了
日本の心を巧みに挑発する快作だ
『座頭市』は、世界的映画監督・黒澤明の代表作として多くの人が知っている。昨年10月、シネーマート六本木にて『座頭市血笑旅』を鑑賞したが、時代劇という映画作品ながら、コマ割の削れるところを削っていく大衆性を感じざるをえなかった。
この東京国際映画祭2013関連企画上映会『時代劇へようこそ~先ず、粋にいきましょう』は、国立近代フィルムセンター等が中心となり現在進められている「フィルムプリント復元事業」の成果を社会一般へアピールする企画として、文化庁が昨年から主催するイベントだ。
『椿組』は、国際社会のバッシングの対象となっている「ハラキリ文化」「恋色沙汰心中」「輪廻転生」(インド・バラモン教へ通じ、カースト制を生む原因)の三点を、驚くべき編成、人物描写により劇場空間を席巻してしまった。
四方のステージ。通路を老人が歩き出し、「盲で ございまーす。盲でございまーす」(差別語であることは承知しておりますが、江戸時代を描く史実関係も大切だと思い、台詞をそのまま掲載させて頂いています)を お知らせする。
黒澤明も撮影した その『座頭市』を現在進行形の形に添えた上、終戦後50年代〜60年代の「色沙汰心中」で交差させる、スリリングな構成であった。
開場中、ずっと音響スピーカが流していたBGMこそ「50年代ニュース映画」である。1951年4月16日7時25分マッカーサーの離日実況中継は、当時の「民主化の父」へ対する崇拝の世論を映し出すようで興味深い。
戦後復興期を迎え、「金」が絶対権利を持つ資本主義社会と、個人の悲壮感「挑み、そして散る者」に哲学価値を定義する舞台は多い。漫画家・手塚治虫も1980年代以降、こうしたテーマを強く意識した作品制作を行っている。
だが、『椿組』が全く異なったアプローチであるのは、「色沙汰心中」を、かなり思い切って肯定してみせたことだろう。
「都会にはレモンがいる」等の台詞が、シェイクスピア調の格式高い香り。あまりの難解なセリフは笑いすら起こった。

うん
泥棒対策ライト
サラヴァ東京(東京都)
2014/01/09 (木) ~ 2014/01/10 (金)公演終了
レタスは楽器かもしれない
パフォーミング公演は、「○」か「×」か判断し易いタイプだろう。
『泥棒対策ライト』は所見だったが、おそらく実力でいえば、「○」の部類に属する。しなやかな身体と、モダニズムに裏付けされた世界観は、渋谷の地下空間を酔わせたラム酒であった。もし、こうしたパフォーミング路線を貫いていれば、観客も酔った可能性がある。
