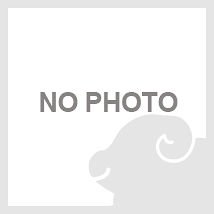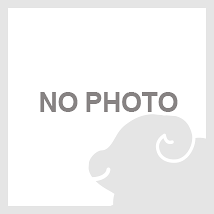満足度★★★
個人的体験としては、、、
全体としてはよくわからなかった。
ただ、部分的、個人的にはとても面白い部分があった。
ネタバレBOX
シェークスピアの『オイディプス王』を基に、現代社会の問題と重ねて書かれた作品。(ハイナー・ミュラーの影響も大きいのだろう。)
すべてが言葉に充たされている舞台だと思った。
役者の発する言葉は勿論、身体表現に関しても言葉に変換されることを望んでいるように感じた。まさに記号として。
だが、作品の中で、「意味や記号に回収されないものこそ、個の身体の中にある」というようなことが語られていたので、作者の意図は不明だ。
少なくとも観客の私には、すべてが記号に見えた。
作者はそれに抗う演出を試みたつもりが私にそう見えなかっただけなのか、それともあらゆる言葉や行為は記号に回収されるということを自己批評(自己相対化)も含めて描いた作品なのだろうか。
言葉も、難しい言葉が飛び交っている割に、その内容は一義的に感じた。
現代社会への批判的な言辞。言葉にならない言葉を言語化しようとしているという意味では、社会に押しつぶされる者の叫びという複雑さは孕んでいるものの、その言葉の向かう先は一方向的。メッセージと言っていい内容。全てが一色だと感じた。
それでも、前半部分では、その一方向性に中断が加えられていると感じ、そこまで悪い印象ではなかった。台詞を複数の役者が一緒に語るなど、言葉が聞き取りずらいものだった。それによって、意味内容をそのまま伝達されない演出になっていた。それが「人は他者の声に容易には接続することができない」というディスコミュニケーションのことを問題にしているようにも受け取れたのだ。
だが、後半では役者の台詞(テキスト)は舞台後ろのスクリーンに文字として投影された。そこには、言葉を「意味」そのものとして、それもできる限り内容がズレない形で観客に伝達しようという意志が見えた。
もしかしたら、言葉と身体(目の前で演じられるもの)とのズレを示したかったのかもしれないが、私には、言葉と演技は相互補完しているようにしか見えなかった。つまり、ズレては見えなかった。
それでは、どこに向かって作品が作られているのか、何を批評しているのか、何を問いかけたいのかが全くわからない。
わかるとすれば、それは最も安易なメッセージとしてでしかない。
難しいことを色々書いたが、以上のことはすべて頭で考えたことで、
舞台そのものから感覚が強烈に刺激されることはなかった。
ただし、ここからは個人的な体験に絡む話なので、客観的批評にはなりえないのだが、
劇の中盤に観客参加のような部分があり、観客の何人かが舞台上に引き込まれた。その何人かに私が入ったのだ。
やり尽された手法とはいえ、実際に参加する側の興奮は、ただ劇を傍観している感覚とは違う。
それでも、それだけなら、殊更ここで書く必要はない。
問題は、そこから。
舞台に上げられ、椅子に座らせられ、さらにその私の膝の上に、女優さんが座ったのだ。
そこで女優さんの足と私の足が触れる接点の感触の妙な生生しさが、作品の示す観念的なものと引き裂かれているということを身体を通して感じることとなった。私が男性であり、相手が綺麗な女優さんだということも、その感覚を増幅さた要因にあると思う。
そして、その女優さんの足の感覚は、その後の舞台を観る中でも残りつづけ、その身体の感覚と舞台上の観念的世界とのズレを考えながら舞台を観続けた。
すると、この作品が問いかけているテーマと、この問題は重なっているように思えた。
上滑りする言葉・情報の氾濫の中で、個の身体性の回復とは何か、など。
ただし、これは私の極めて個人的な劇体験からくるものであり、おそらく観客参加者に選ばれていなかったら、こんな分裂は覚えなかったと思う。
「観念だけの作品を観たな」という印象で終わっていたように思う。
観客参加がなかったらおそらく【満足度】は「評価しない」を付けていたと思う。
だが、すべての劇体験は個人的なものでしかないとも言えるので、そういう意味では★4。
ここでは、間をとって★3にした。
満足度★★★★
嘘と生活者へのアンビヴァレンス(追記あり)
東憲司氏の作品には、時代状況への問いかけが常にあるため、
そのような部分で期待が裏切られることはない。
必ず何かしら受け取ることができる。
だが、今作は芝居自体としては惹き込まれなかった。
ネタバレBOX
心の底では薄々気づきながらも、
嘘を信じ続けるしかない銃後の女たち。
その女に嘘を語り続けるしかない老人(彼は満州の馬賊だったと言い張るが、これも、実は嘘で、小日向白朗の話を自分のこととして語っていたようだ。)
お互いのために嘘が必要であった。
そして、その両者で自警団を組織していた。
そこにその集団を相対化する外部からの視点、2人の兵士が現れる。
二人はこの集団に巻き込まれながらも、
一人は引いた眼線でその集団を見つづけ、
もう一人はその集団に取り込まれていく。(後者は、体が弱く何度も兵役免除になっていて、そのことを自分で悔しい・申し訳ないと思っていた劣等兵であるというのも面白い)
そして、8月15日(敗戦)を迎える。
それでも、集団は敗戦を信じない。
戦時中の特殊な(架空の)物語だが、
これが戦争の本質そのものだとも感じた。
そして、これはかつての戦争時以上に現在の社会そのものを表象しているのではないか。
原発神話などは明るみに出た顕著な例だが、皆が薄々オカシイと感じながらも、それを信じることでしか成り立たない嘘。そんな嘘で社会が均衡を保っているという、、、、。
戦争に敗れたと言われても、それでもその事実を受け入れることができず、敗れたことを認めない人と、敗れたことを受け入れた人とで対立するというのは。ブラジルの日本人移民の間で起きた「勝ち組」「負け組」抗争を思い出す。まさにこの物語のようなことはブラジルで起きていたのだ。この物語のように日本の農村でもそんなことがあったのかは知らないが。(おそらくなかったであろう。)
また、老人が五族協和を謳った満州の嘘を背負っているということも、構造的に面白い。
そんな史実を踏まえて書かれたものかはわからないが、架空の物語でありながら、妙なリアリティがある。
しかも、そこで戦う武器は、木をそれに見たてただけの偽鉄砲、木と紙でできた偽戦車。さらに、案山子を人間に見たてた偽軍隊。
嘘で集団の結束を固めている集団は、武力に関しても徹底して嘘に基づいている。
これは、当時の日本軍の虚妄・バカバカしさを揶揄しているようにも見える反面、何か単純な風刺とも言えない感覚も喚起させられる。
それは「魂を込めれば、それは本物の武器となり、鉄砲も戦車の大砲も火を噴くことができる。案山子は本物の軍隊になる。」という描き方が、
演劇表現そのものの可能性を語っているようにも思えるからだ。
嘘は現実を見えなくするものであるとともに、
本物をも上回るものに変える力とも見ている。
嘘に対しての批評と、共感。
ここに、東氏のアンビバレンスが表れているように感じた。
同時に、ここには一般的な生活者というものに対する東氏の分裂する想いも感じられる。お上の言うことを盲信してしまう者への批評と、そうすることでしか生きていくことができない者への共感。
どちらかと言えば、後者の方が強いのではないか。
これまでの東作品(『鬼灯町鬼灯通り三丁目』など)でも、戦場ではなく銃後に向ける視線の中に、戦争に振り回されながらも強かに生きていく生活者へ共感が強くあったように感じる。
この生活者に対する引き裂かれた視点こそが、東憲司氏の根底にあるような気がする。
<追記>
説教節の本(『中世の貧民 説教師と廻国芸人』塩見鮮一郎)を読んでいたら、もともと案山子とは人であったと書いてあった。
目の見えぬ者、足の悪い者が、他の仕事ができないため、差別され、鳥追いとして働かされていたということらしい。
東憲司氏がその歴史を背負った上で、案山子の物語を書いているのかどうかは、作品からだけでは判断できないが、いずれにせよ、かつて人であった案山子が、人形になり、更にその人形を再度人として蘇生させる物語だとう読みもできてしまう。大げさに言えば、差別された者の復権の物語とも。それが過剰な我田引水の解釈だったとしても、そのような読みさえもできてしまうこの作品の奥深さを、観劇後何日も経ってから感じた。
満足度★★★
正攻法
正攻法の芝居だと思った。
ネタバレBOX
脚本は、永山則夫の人生をうまくひとつのフィクションにまとめていて、技巧的にはうまいと思った。
アパートの一室にいる永山のもとに、「今日ここで(左翼的な)会合がある」という手紙をもらったという男が4人次々と現れる。
また、アパートには、母や姉も登場する。
若い永山少年も登場する。
そこで、永山の人生を振り返りつつ、対話がなされていく。
「永山の最後は刑務所じゃないのか?」と不思議に思いながら見進めるが、
最後に、これは刑務所の一室での彼の幻想なのだと気づく。
何度となく刑務所の中で振り返り、考え、想いを巡らせた様々なできごと、
その最後の幻覚。
4人の男とは、永山が殺した男だったのだ。
「この4人以外に誰が私を殺せる(裁ける)のか」と永山は言い、
死刑を待つ。
現実に起こった事件と永山の人生を、一夜のドラマに構成する手腕はとてもうまいと思うが、その作品の問いかける意味は、永山則夫について言われてきた言説の最も一般的なことを形にしたに過ぎない。
貧乏で、不遇で、親の愛情にも恵まれず、差別され、、、その不遇が、一人の純朴な少年を殺人鬼に変えてしまった、と。
それ以上の複雑は何もない。
そのため、観ていて、驚きも発見もなく芝居が終わった。
今日の社会で永山則夫のことを考える場合、
アキハバラ事件や先日起こったアクリフーズ群馬工場の農薬混入事件など、、、が頭をよぎるはずなのだが、
芝居を観ながらも、ここで起こっていることが、今日の格差や貧困とそこから生まれてしまう犯罪と、少しも重なっては見えなかった。
おそらく、複雑さを孕まない単純化された物語のため、そう思ってしまったように感じる。
(いくら不遇でも犯罪を犯さない人だっているという程度の分裂さえも、この作品には書き込まれていない。)
演出や演技に関しても、極めて正攻法。
特異な演出ならば完成度などは少しも気にならない私も、
正攻法の作品の場合、どうしてもその精度(完成度)を求めてしまう。
充分熱量のある芝居ではあったが、それ以上のものとは思わなかった。
この作品の真面目な姿勢と比べたら、
いい加減な姿勢の作品にも✩4や✩5などを私は付けていることもあるので、✩3というのは厳しいと自分でも思う。
ただ、正攻法のものは、観る側のハードルもどうしても上がってしまう。悪しからず。
文字通り、「評価」ではなく「満足度」だとお考えください。
満足度★★★★
秀逸な物語構成
チャンバラ・アクションにはそれほど興味がなかったが、
鐘下辰男作品を一度観てみたいと思い観劇した。
チャンバラ自体は興味の薄い人間をも虜にするということはなかった。
芝居の脚本構成がとても秀逸だと思った。
なんでも解り易くすることが是とされる風潮の中で、
一見物語がすんなり掴めないが、劇の進行とともに徐々にその全体像が見えてくるという作りには驚かされた。その具合が絶妙だった。
内容も、元は同じ集団だった者たちが二つの陣営に別れていがみ合うというテーマが、今日の政治状況、社会状況へのメタファーのようにも受け取れ、とても刺激的だった。
満足度★★★★
『新釈・瞼の母』観劇
スズキメソッドを身につけた役者の身体は強靭だった。
長谷川伸の『瞼の母』にある情緒的なものを、異化(相対化)している部分なども面白かった。
ただ、芝居としてはそれほど惹き込まれなかった。
それでも、上演後に行われた観客と鈴木忠志氏のQ&Aも含めて、
「演劇とは何か?」ということを深く考えさせられた。
それは、一方で敬意を持ちつつ、もう一方で批判的な思いもありつつ、
すべて含めて、多くの問題提起を上演全体から受け取った。
ネタバレBOX
まず、作品から感じたこと。
鈴木忠志氏の方法論、スズキメソッドを体得した役者の身体は極めて強靭だ。
役者の演技だけではなく、演出も含めた舞台全体が、鈴木忠志の世界として完璧に構築されている。
それはスズキメソッドに限らず、古典芸能からスタニスラフスキーシステムに至るまで、あらゆる「型」を持つ表現の強度である。
ただ、その一方で、世界がすべて鈴木忠志、あるいは「型」に支配されているという窮屈さも感じた。役者は自由な人間ではなく、常に拘束を受けている。
演出家に世界が支配されている。権力的だとも思った。
そういう拘束を受けながら生きるのが人間の生ということなのだろうか?
私はこの点がどうも受け入れ難かったが、
それこそが役者に命がけの演技をさせ、芝居にとてつもない緊張感を与えているのは確かだった。
(それは、マイルス・デイビスの楽団のようだとも感じた。マイルスが吹いていない部分でも、帝王マイルスの気配が楽団全体を支配し、音楽全体を支配する。その恐ろしい緊張感。)
観客と鈴木忠志とのQ&Aで感じたこと。
「なぜ『瞼の母』なのか?」という質問に、鈴木忠志は、
「日本語には言葉の中に旋律がある。その音程の変化によって、言葉の意味が変化する。
例えば、「どこへ行くんだ」という言葉は、音程を変化させて発語することによって、場所を尋ねる意味にもなれば、「どこにも行くな」という意味にもなる。
このような日本語特有の発語をきちんとやって演出をするためには、きちんとした日本語によって書かれた戯曲を使わないといけない。それは三島由紀夫でも谷崎潤一郎でもいいのだけれど、今回は長谷川伸の『瞼の母』にした。
この芝居で、古い流行歌を音楽に使っているが、昔の日本の流行歌では、そのような意味で、日本語がきちんと発音されていた。だから、そういう歌を使った」と答えていた。
とても説得力のある、本質的な答えだ。
また、この作品では、長谷川伸の言葉だけではなく、
ベケットの言葉や寺山修司と石子順造が対談で「瞼の母」について話している言葉も入れ込んで作品化しているという。
それら他者の言葉や鈴木自身が書き込んだだろう言葉が、長谷川伸の人情話を異化(相対化)していた。
母や家族への愛着は権力構造に根ざしているというような視点は、寺山のモチーフだろう。
また、「今の若い人の演劇についてどう思うか?」というような質問に対しては、「利賀にいることが多く、観る機会が少ないから明言はできないが、今の若い世代は、演劇人が演劇のことしか知らない。文学や映画など、様々な分野のことを知らないと演出なんてできない。また、演劇というジャンルの中でさえ、知り合いの劇団や自分の好きなものしか観ない。昔の演劇人は他の劇団の公演も観て、賛否あれど、参考にした。自分の嫌いだろうものでも、とりあえず観るということをした。ただし、それは、若い人が悪いというだけではなく、特に演劇の場合は、入場料が高いので、安易に芝居を観に行けないという構造のせいもある。いずれにせよ、それが、若い作家の世界を狭めているのではないか」と語っていた。
的確な指摘だと思う。
また、「同時上演した『リア王』は、なぜ日中韓の役者でやっているのか?」という問いに、「スズキメソッドを体得した役者が世界にいて、特にアジアにも素晴らしい能力を持っている役者がいるということを提示するためというのもある。それに、日中韓の政治的な関係がギクシャクしている時だからこそ、その三国の役者でやりたかった。」と言っていた。
特に後者の視点は素晴らしいと思う。
(『リア王』のゴネリル(三姉妹の長女)役:ビョン・ユージュンさんは、SCOTで6年くらい訓練を受けている役者らしい。本当に凄い演技だと思っていたが、鈴木忠志氏も、やはり長く訓練を受けているだけあってスズキメソッドをかなり体得していると言っていた。)
また、寺山修司や唐十郎、安部公房などの話が出た際、
「自分が書いたものしか演出していない人は演出家とは言えない。一人の劇作家の戯曲しかやらない演出家もそうだ。指揮者で、自分が書いた曲しか指揮しない指揮者なんかいない。他人の書いたものを読み解き、そこに普遍的なものを見出して形象化するのが演出家の仕事だ」というような趣旨のことを言っていたのも印象的だった。
総じて、演劇とは何かということを深く考えさせられた。
満足度★★★★★
現代の時代状況への強烈な問いかけ!多くの人に観て欲しい作品。
現在の社会状況に、この作品の問いかける意味は大きい。
現首相は「美しい国」「日本を取り戻す」と声高に叫んでいるが、
そこでイメージされているのは、「強い日本」のイメージ。
まさに戦前「明治の日本」であり、「昭和の日本」の姿だ。
その間に挟まれた大正時代。
それは、大正デモクラシーや大正ロマンに代表されるように、
ほんの一時自由が花咲きかけた時代だった。
その時代の天皇の話。
作品から、大正天皇が、大正時代が、歴史から消され、忘れられた理由が見えてくる。
「取り戻す」べきは、明治や昭和の「強い日本」ではなく、弱くても自由な大正の気風なのではないか。
作品のラストでは、目の前の芝居が、今現在の社会状況とぴたりと重なって見えた。
私は作り事の芝居を観ているのではなかった。社会の中で自分が置かれている状況そのものを自覚させられていたのだ。こんな感覚を覚えた舞台は初めてだ。
ブレヒトのような演出(異化効果など)がなされていた訳ではないが、ブレヒトが叙事的演劇として観客に感じさせたかったものは、私がこの作品のラストで感じたものなのだろう。
理屈では分かっていたが、初めてそれを体感した。
*箇条書きのように書きなぐっているので、後日整える予定。
ネタバレBOX
私は大正天皇についての知識がないので、
大正天皇がこの物語のような人物だったのかどうかは検証できない。
ただ、観客の姿勢としては、大正天皇が本当に善人だったのか、大正という時代が本当に自由なだけだったのかなど、この作品で描かれているものを史実としては信じ込まないという留意は必要だろう。
視点を変えて歴史を見れば、明治から昭和へと続く発展過程の一段階として大正を捉えることも当然できるのだから。
それでも、そもそもこれは創作物語でり、事実がどうであったかよりも、
この作品で劇団チョコレートケーキが問いかけようとしている内容にこそ意味がある。
これは、過去を扱いつつも、現在を問うている作品なのだ。
この物語の中で、天皇は、体が弱いが、自由を愛し、権威を振りかざすことのない、心優しい人物として描かれる。
それは、強さと威厳を誇る父:明治天皇や、父と同じ資質を持つ息子:昭和天皇とは全く異なる資質のものだった。物語の中では、その天皇の資質が、施政にも影響し、大正時代の自由な気風を作り出したとなっている。
だが、それは天皇の威厳を損なうものにもなりかねない。天皇は臣民には手の届かない神であり、人間であってはいけないのだ。
それでも、原敬などは、その大正天皇の人間性に大いに敬意を持つ。
牧野伸顕も初めはその人間性に惹かれたものの、第一次大戦で多くの国が欧米列強に力で征服させられていった様を見て、日本も強くならねばならない。「自由より力を」という気持ちになっていく。ちょうどその時期に、大正天皇に脳の病気が発症する。そして症状はどんどん悪化し、もはや天皇の威厳は保たれないと牧野は判断し、皇太子裕仁を摂政(実質上の統治者)にしようと考える。だが、大正天皇は承知しない。牧野は皇太子と組んで、大正天皇の脳の病気のことを新聞に発表する。それも、幼少期より脳の病気を患っていたということにし、歴史までおも書き替えてしまう。それは国民の記憶を書き替えることでもある。最終的には、皇太子が「父である大正天皇は摂政になるということを許可した」と言い張り、母皇后から「本当にそれでいいのですね」と釘をさされるも、「それでいいもなにも、陛下が許可したことだ」と言い、摂政に就任する(1921年11月25日)。
その数年後(1926年12月25日)、大正天皇が崩御する。崩御から半年も経たない内に、本来ならば喪に服しているべきなのにも拘わらず、明治60年祭(←正式名称不明)を行う。意図的に大正天皇、大正時代の記憶を消し、明治の「強さ」を昭和で復活させようとしている。(顕著な例は、1927年11月3日に、明治天皇誕生日が明治節として祭日に復帰。その一方で、大正天皇誕生日は平日に。)明治60年祭の直前、昭和天皇裕仁の前に現れた母(元皇后)は「大正天皇を二度殺すことになるのですよ」というようなことを言う。それは、一度生命が死した者を歴史からも抹消するという意味なのか、嘘を付いて摂政になったことを一度目の殺しとし、歴史から葬ることを二度目の殺しと考えているのか、、、いずれにせよ、「歴史からも父を葬り、父や母とは全く違う道を歩むので良いのですね?」という問いかけである。
これは、物語内で昭和天皇が問われていることであるとともに、現代日本社会が(つまり、観客が)、「優しさや自由を捨てて、強い国を本当に目指すのですね」と問われているようにも感じられる。
ラストシーンは、昭和天皇が、大正時代を葬り、昭和時代を踏み出すシーンで終わる。
このシーンが、私には今現在の社会と重なって見えた。単に重なったというだけではない。
舞台を観ながら、昭和天皇の姿を観ながら、自分の置かれている社会状況について考えていた。
「本当に、自由を捨てて、強い国になろうとするのか、この国は?」と。
その入口に、もう私は、私たちは立たされてしまっているのだと。
戦慄を覚えた。
舞台作品を観て、こんな感覚に襲われたのは初めてだ。素晴らしかった。
この時代にこそ必要な表現だ。
他にも印象的だったシーンを書く。
劇中、大隈重信は大正天皇との会話で、「なぜ明治維新が天皇を担ぎ出したかと言えば、欧米から日本を守るため、幕府に代わって日本を統率するには、臣民の誰もが崇める神棚が必要だったからだ。その手段として天皇を利用した。だが、時代が経て天皇を崇めるのが当然という世代の政治家が現れると、天皇を崇めることが目的となり、手段と目的が反転してしまう。つまり、国を統治するために、神棚としての天皇が必要だったのに、天皇制を崇め守ることが目的となり、そのために国民が犠牲になる。」という趣旨のことを言う。まさしくそのように歴史は進んだ。
役者さんたちも本当に素晴らしかった。全員素晴らしいのだが、
特に松本紀保さん(貞明皇后節子役)は、淡々とした演技で、最初はそれほど印象的ではなかったのだが、芝居の最後には、その存在感に圧倒されていた。彼女の静かな振る舞いと、穏やかでありながら、強い信念を持った問いかけが、芝居全体を支配していた。大正天皇を支えた妻であると同時に、芝居を底辺で支えていた演技であり、彼女の言葉こそが、最終的には観客への問いかけにもなっていた。驚くべきことだ。
また、いつも思うが、チョコレートケーキの劇団員、西尾友樹さん、浅井伸治さん、岡本篤さんは特に良い。
西尾さんはヒトラーを演じた時も思ったが、繊細な人物を演じる時の揺らぎのようなものが絶妙だ。
基本的には絶賛なのだが、一つだけもったいないと思ったのは、皇后節子と昭和天皇が話をする時の二人が、親子に見えなかったということ。<『治天ノ君』関連年表>には「節子、昭和天皇裕仁を出産」とあるので、実の親子のようだ。だが、そう見えなかった。史実としても、二人には確執があったようだが、いくらいがみ合っていても、母と子の関係は、愛情であれ、憎悪であれ、もう少し情が見え隠れするような気がする。それが感じられなかったのはもったいなかった。
そうは言っても、作品全体としては、本当に素晴らしかったです。
ありがとうございました。
満足度★★★
化けるかも
THE SHOWの前公演『贋作☆スイミー』のセンスのよさに驚いたので、
その作・演出だった栗☆兎氏の作品を観にいった。
私が観に行った日の公演は、
作・演出:松坂貴大『過失』
作・演出:栗☆兎『川越駅西口物語』
『過失』は割とスタンダードな作品。
『川越駅西口物語』は、前作同様、とても興味深く拝見した。
演出のセンスが抜群に良い。
詳細は「ネタバレBOX」に書くが、
栗☆兎氏には、今後化けるのではないかと思わせる何かがある。
ネタバレBOX
川越駅西口を舞台に、そこを過ぎていく日常の描写から物語は始まる。
西口は、華やかな東口と違って少し陰がある。
この公演が行われている尚美学園は、その西口からバスに乗って10分位の処にある。
西口を利用する人の多くは会社員か学生であり、
両者共に、そこは常に通過するだけの場所だそうだ。
(観客である私も、バスで尚美学園に行ったので、この作品で語られていることの幾ばくかは、来る途中に感じとることができた。)
その普段は通過するだけの場所を巡って物語は展開していく。
まず、その描写力が素晴らしい。日常のほんとうに些細なことを描くことで、その物語にリアリティを持たせている。それを支えているのが、ドキュメンタリー的と言ってもいいような、演出。そして、それを演じる役者のラフな演技。ラフでありながら、面白く観られるのは、役者たちの個性に依るところも大きい。とても個性的で魅力的な役者たちである。
その日常の細部と対比するように、巨視的な見方が示される。
西口は改築工事をしていて、数年後には近代的なロータリーができるのだという。
ここで、都市というものを見る鳥瞰的な視点と、未来というものを見る歴史的視点の二つの巨視が示される。そこに、かつてここには川越少年刑務所があったという過去の視点か加わり、通時的視点は補填される。
更に、そこに西口にたくさんいる鳩やムクドリ(?)の話が重なる。それによって、人間中心の世界観に対して、動物や自然からの視点が示される。
また、川越駅西口から程ない処に雀ノ森氷川神社というものがあり、鳥の問題は過去の歴史にも接続させられている。
このように様々な視点が示されることで、普段はただ通り過ぎるだけで、何も見ていなかった川越駅西口が、全く別の彩りをもった景色として見えてくる。
ここで示された様々な題目は、それぞれに繋がっているのか、いないのか。重なっているものは、偶然か必然か。これらは観客が考えることとして投げ出されている。
この点を開かれた作品と考えるか、テーマが絞り切れていない作品と考えるかは様々な見解があるだろう。
私は後者だと思った。充分に面白い問題提起がなされているにも拘わらず、散漫な印象で、心に残るものが少ない。
日常的な細部への対比として様々な視点が示されるけれど、
それらはあくまで添え物という感じで、その両者が絡み合いうねりを生むことはない。
様々な視点が現在を生きる私(作者であり、演者であり、観客)の日常に対して、どう関係を持つのかが、より有機的な繋がりをもって示すことができていたら(あるいは、そんな繋がりなど今日は全くもって断絶してしまっているということを示すのでもよい)、より深い印象の作品になったのではないか。
また、これは前作でも指摘したことだが、最近流行の現代演劇(「マームとジプシー」などかな?、、、)によくある文体と発語の型のようなものを使っているので、モノマネっぱさがどうしても耳についてしまう。これは決定的にもったいないと思う。オリジナルの実力があるのだから、亜流だと思われたら損だ。
正直に言えば、現状では、学生劇団の中では桁違いに面白いと思うけれど、一般の表現者の地平で評したら、賛辞を贈るほどではない。
だが、この栗☆兎氏には、ひょっとしたら大化けするんじゃないかと思わせる要素が多分にある。
役者さんたちもとても個性的で魅力的だった。
今後の活動にも期待しています!
満足度★★★★
問いかけのある
男・女の役割を入れ替えるという話をめぐって、
社会にある制度や構造のことを考えさせられた。
正直に言えば、作品としてはそれほど惹き込まれなかったが、
やはり、問いかけのある作品(作風)は素晴らしいと思う。
ネタバレBOX
男・女を取り替えるという『とりかへばや物語』を、
それを語る噺家の物語へと書き換えている。
更にこの『新説』では、
古くは噺家は女性だけの世界だったという仮説をつくることで、
現在にも続いている男性中心の噺家の世界と、その構造を「とりかへ」て物語を展開させている。
(ある意味では『家畜人ヤプー』のような反転)
そこから見えてくるのは、男・女という性によって別けられている制度のことなど。社会全体の構造についても考えさせられた。
ただ、物語としてはそれほど惹き込まれなかった。
それでも、このような問いかけを持った作品は素晴らしいと思う。
私がカムヰヤッセンの作品を観るのは3作目。
3作とも、観客に対して(時代に対して)の問いかけのある作品で、とても素晴らしいと思っている。
この作品の中でも、
噺家が「語るべき物語とは何か」「意味のある物語とは何か」というようなテーマが何度か出てきていたが、それに対して私は、観客に対して、時代に対して、「問いかけのあるもの」こそが、優れた作品の条件だと思っている。
(「メッセージ」ではなく、「問いかけ」。)
それがある作家の作品を観たいと思っているので、カムヰヤッセンの活動に注目している。
満足度★★★★
『リア王』観劇
役者の身体と演技がとにかく強靭だった。
特に、ゴネリル役:ビョン・ユージュンさんの鬼気迫る演技が凄かった。
完成された世界観で、さすが鈴木忠志という感じでははあったが、
強烈に心が揺さぶられることはなかった。
・・・
アヴァンギャルドという名の古典芸能。
エロ・グロ・シロヌリ、折り込み済みの破綻。
すべてが予定調和だった。
満足度★★★★★
素晴らしい演出と演技(追記あり)
さりげなく、ポップな作風なれど、その奥に強い現代への問いかけがある脚本。
緩急の絶妙な演出。
共に、素晴らしかった。
個性的で、力のある役者たちも、とても魅力的だった。
冒頭から中盤までは文句なく素晴らしかった。
後半<あと一歩、、、>と思う部分があったが、それは、プレヴュー公演だからだと思いたい。
※ネタバレの最後に、生活保護を受給して生活している田所優美の描き方についての違和感、その違和感から生じた作品全体についての印象の変化を追記しました。(12/18)
ネタバレBOX
冒頭から中盤までは、文句なく素晴らしかった。
何と言っても、演出の緩急が絶妙だった。
動的演技と静的な演技の切り替えの妙。
谷賢一氏は、音楽的な感性のある演出家なのだと思う。
ここで、警察を演じた大原研二さんと一色洋平さんのエネルギー溢れる動の演技も素晴らしかった。
その一方で、シェアハウスの人たちの淡々とした静の演技も素晴らしかった。
両者のバランスが絶妙だった。
内容面でも、現代の若者を巡る問いかけが良かった。
警察がある事件の捜査のために、クリスマスパーティをやっているシェアハウスに乗り込む。
正義を振りかざす警察を、熱烈な演技をさせることで、極めてコミカルに描いているが、その裏には痛烈な批評性が隠されている。
ひとつは、権力への批評性。警察の横暴な振る舞いを痛烈に批評している。痛烈と言っても、笑いの中に毒を含ませているので、堅苦しくなくとても痛快。
奇しくも私が観た12月6日は、「特定秘密保護法」が成立した日。
このような社会情勢の中にある空気感を、この作品はうまく捉えている。
もうひとつは、年配の世代が押し付ける価値観への批評性。
「最近の若者は、根性が足りない」「熱さが足りない」に代表される年配の言うガンバリズムへの批評性も見事に描かれている。
ここで面白いのは、この批評性は両義的で、観ている間も、観終わった後も、この年配刑事の上から目線が嫌な反面、どこかで彼の言うことも一理あるんじゃないかと思えてしまうことだ。これは、さまに、物語内の話だけでは済まされず、今の社会が抱えている問題を的確に捉えているからこそ生じたものだろう。
勿論、ブラック企業なども多く存在し、雇用・労働環境の変化によって、「若者の根性が足りない」という意見はナンセンスだという場合も多々ある。
だが、本当に「根性がないだけ」という場合も存在する。おそらく、どちらか一方が問題なのではなく、その両者が問題なのだろう。
この作品でも、その両者の間を揺れながら、物語が進んでいく。
ただ、後半は少し乗り切れなかった部分もあった。
それは、警察に「シャアハウスの住人の中に、先日起きた猟奇殺人の犯人がいるかもしれない」と言われ、シェアハウスの面々は動揺し、しんや(渡邊亮)が「出頭します」と言い始める部分から。しんやは事件を起こした訳ではないのだが、「今のままの生活をしていると、そのうち殺人をしてしまうかもしれない」という想いから、事前に出頭したいと言い出す。
そこで神戸連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇事件)や秋葉原事件のことが語られる。両事件とも、犯人は1982年生まれ。しんやを含め、このシェアハウスに住む6人中4人が1982年生まれの31歳。理由なき犯罪などとも言われる事件を起こしてしまうこの世代の闇が、しんやの述懐を中心に語られる。それに呼応する形で、てつ(東谷英人)、ゆう(堀奈津美)の想いも加わる。(同じ年なのに、ゆかり(中林舞)はその感覚が理解できないというのも良い。)更に、少年A:酒鬼薔薇聖人(清水那保)も登場し、彼の犯行時の言葉も語られる。
だが、私はここで、しん、てつ、ゆうの言っていることが、理屈上では「その感覚わかる、、、」と思う部分もあったが、それ以上には身につまされることはなかった。
ここが、いまいち入り込めなかったので、ラストにかけての展開が物足りなく感じてしまった。
また、ラストに、「アクアリウム」の生態系の話が、人間社会(シェアハウス)の人間関係の話と重ねて語られるのも、よくできていると思う反面、ちょっとキレイに終わりすぎかなという気がしないでもなかった。
と不満も書いてしまったが、全般的に素晴らしかった。
わに(中村梨那)やとり(若林えり)など、動物を擬人的に役として登場させると陳腐になる場合も多いが、この作品では、ファンタジーではないのに、うまくその世界が成り立っていた。
私は、台詞をしゃべっていない時の役者の演技(聞き役など)を観るのが好きなのだが、そういう観点から見ても、役者さんたちはとても魅力的な演技だった。
【追記】(12/18)
観劇後、どうしても引っかかっていたことが、とても重要なことのように思えたので、追記する。
生活保護を受けて生活している田所優美という人の描き方について、違和感を覚えた。
確かに、生活保護を受けて楽をして生活している人も中にはいる。人気お笑い芸人の親が、生活に困っている訳ではないのに受給していた例も確かにある。
だが、それは一部であり、多くの人は本当に苦しくて生活保護を受けている。それどころか、本当に生活が苦しいにもかかわらず、生活保護を受け付けてもらえない例もたくさんある。
更に、私がこの芝居を見た12月6日に、改正生活保護法も成立し、改正の名の元に更に受給者の首を絞める施策が行われる。
そのような社会情勢の中で、少ない登場人物の一人として、生活保護を受けてぬくぬく生活しているという人を描くというのは、とても危うい描き方だと思った。勿論、フィクションであるから、解釈は観客に委ねるということで構わない。
実際、観劇直後は、私もこの点に引っかかってはいたものの、敢えて批判的なことは書かなかった。そうやってぬくぬく生活している人も確かにいるのだろうし、フィクションというのはそういう部分があっても仕方がないと思っていたからだ。だが、よく考えると、フィクションだからこそ、このような問題を扱う時は慎重になるべきだし、片方の見方に寄らない描き方はできたはずだと思い直した。
そう考えると、この作品全体が、単に根性がない若者を上から批判的に観ているだけの作品のようにも見えだしてしまうのだ。
雇用環境やブラック企業などによる過剰労働などの問題が背景にあって、若者が簡単に会社を辞めてしまう。それは根性の有る無しと関係ない部分も大きい。勿論、単に根性がないだけという場合もある。この点は、キワキワで両論が描かれていると観ている最中は好意的に観ていたが(わざわざ批判的に見ようと思って芝居を観ることはないので)、よくよく考えると、どちらかと言えば「根性がない」という方にウェイトが置かれていたのではないだろうか。
いずれにせよ、現代の過酷な労働環境に関する言及はほんの少ししかなされていない。
厳しく見ると、全体的に上から目線で描かれている作品のようにも見えてしまったのだ。
ただ、これは批判的に見ようとした場合なので、その判断はきわどい。
また、観劇時に好意的に見ていた時は、そのキワキワさこそが面白いと思っていたので、私が重箱の隅を楊枝でほじくっているだけなのかもしれない。
好意的に見れば、作者も若い作・演出家なので、自己批評を含めて同世代を描いたというのなら、批判すべきもないとは思う。
それに、上記のことを批判的に見たとしても、演出や演技の妙に関しては、その素晴らしさを損ねるものではないとういのは強調したい。
満足度★★★
完成された世界観
完成された世界観だった。
興味深く拝見したが、私はそれほど面白いと感じなかった。
ただ、好きな人には強烈に響くものなのかもしれない。
ネタバレBOX
なにげない会話や人間関係の中にあるズレのようなものを意識した脚本・演出。
それらの断片が積み重なって物語が展開する。
大きい枠での物語はあるが、明確に意味付けされたものはない。
細部のズレは物語からはみ出し、そのはみ出したものを、
観客は想像力の中で繋ぎ合わせることで、観客一人一人の物語が起ちあがる。
私は、生者と死者の境界のことを、私自身が生きている生活の中での問題と重ねながら見た。
ただ、そのズラし方や切断の仕方が、あざといような気がしないでもなかった。演出にしても、脚本にしても。
演出では、有機的な会話にならないように、
敢えて関係性を切断しているような演出がなされていた。
勿論、普通の会話を異化するために行われているのだし、実際、その異様な感じが興味深くはあったが、それ以上の意義を感じることはできなかった。
私は松本雄吉氏の演出を観るのは初めてなので、この作品での演出の仕方やその位置づけなどはよくわからない。
脚本でも、わざと線をぼやかすことで、観客にゆだね、さまざまな解釈ができるようにしているというのが、戦略的な振る舞いに見えてしまった。
(作品内でも、映画監督:御厨が須藤の妻に、「きちんと色を塗らないで、作品をぼやかして、誰にも通じないような作品を作っていないで、誰にでもわかるような作品を作ったらどうなの」というような罵倒をされるシーンがある。作品内でこれを語らせるというのは、作者の自嘲なのか、それとも自分は矜持を持ってやっているということの表れなのか、、、わからない。)
松田正隆氏の作品を観るのは3作目。
松田氏が脚本を書き、平田オリザ氏が演出した、『月の岬』は本当に素晴らしい作品だと思った。
だが、去年のF/Tの演目だった『アンティゴネーへの旅の記録とその上演』は、今まで私が観たあらゆる演劇と名の付く表現の中で、もっとも酷い作品だと思った。
私の中で、松田氏への認識はそのように引き裂かれている。
この作品を観て、さらにわからなくなった。
本質的に表現を探求している人なのか、それとも、奇を衒っているだけの人なのか。
批判的に書いてしまったが、興味深く観ることはできた。
ただ、それを支えていたのは、脚本や演出というより、
役者さんたちの強さだったように思う。
満足度★★★★
「ショッキングなほど煮えたぎれ美しく」を観劇
役者さんが良かった。
成清正紀さんが特に良かった。
竜史さん、桑原裕子さん、異儀田夏葉さんもよかった。
正直、物語には不満が残ったが、演出は面白い部分が多々あった。
ロックバンド「フリサト」とのコラボは、想像以上の化学反応は起きていなかったが、期待を裏切ってもいない。
やはりロックバンドの生演奏には力があった。
ネタバレBOX
正直に言えば、この舞台から、この点がとびぬけて凄いというものは感じなかった。
ただ、随所に面白い部分はあった。
一番印象的だったのは、ラストシーンの手前、
飛山甚平(成清正紀)と飛山平(竜史)が向き合うシーン。
竜史さんも良かったが、それ以上に成清正紀さんの演技が素晴らしかった。
甥(もしかしたら息子かもしれない)飛山平(竜史)に色々責められ、それを黙って受け止めている飛山甚平(成清正紀)の姿。その姿だけですべてを語っていたと思う。
このシーンが素晴らしかっただけに、その後の物語展開がとても不満に思えてしまった。せっかく2人が向き合いはじめたのに、その後、単にお互いが鬱屈したエネルギーを爆発させて、物語は終わってしまう。
それも、タイトルとパンフに書かれた「ごあいさつ」を読めば(それにロックバンドとのコラボということを考えれば)、だいたい予想がつく終わり方。
煙に巻かれたような気分だった。それも、予定調和によって。
どうせ予定調和なら、もっともっとぶっ壊してほしかった。
また、そのラストも、ヘッドフォンの差し込みを外して、ラジカセ本体から音が出るまさにその瞬間にロックバンドが生演奏で爆音を出すというのが、お約束だろうという場面で、その瞬間に生演奏が入らず、ラジカセの音が出てから、段階を踏んで生演奏が重なっていった。
展開は予定調和なのに、なぜここではお約束をやらなかったのか、、、期待していたのに!敢えてズラすことによる効果は感じなかった。単に、合わせるのが難しいから、安全パイをとっただけなのだろうか?
このお約束が決まっていれば、作品の印象はだいぶ違ったものになっいたと思う。3コードでも感動してしまうパンクロックがあるのと同様に、展開が予想できても、「やっぱロックってこういうもんだよな」「この爆発力と疾走感だよな」と納得できたような気もする。作品のテーマもそこなのだし。
ロックバンド「フリサト」とのコラボに関しても、想像していた以上でも以下でもなかった。ロックバンドと演劇がコラボしたら、こういう感じだろうなという予想通り。それでも、歌詞がもっと聞き取れれば、コラボしている必然性がより感じられたのだろうが、初日だからか、舞台の音響さんはロックバンドの音圧に不慣れなのか、バンド側の音作りの問題か、理由はわからないが、(静かな曲は別として)歌詞がほとんど聞き取れなかった。(最初、音が割れたりもしていた。)とてももったいないと感じた。
そうは言っても、生ロックバンドの臨場感は充分にあったし、よく融合していたとは思う。
姫路勝子役:桑原裕子さんの演技はとても面白かった。絶妙だった。
富永美幸役:異儀田夏葉さんもよかった。
批判的なことばかり書いてしまったけれど、ラストの前の2人のシーンが本当に素晴らしかったからこそ、もったいないと思い、厳しく書いてしまいました。悪しからず。
満足度★★★
カーテンコールの奇跡
褒めているのかどうかわからない言い方で申し訳ないが(詳細はネタバレBOXにて)、舞台後のカーテンコールが素晴らしかった。
ネタバレBOX
そもそも、この作品で描かれているエリック・サティ像は、私が想い描いていたサティ像とは違うものであった。私はサティをより反骨的な人物だと思っている。「家具の音楽」にしても、「私の音楽を聴くな」というのは「BGMとして聞いてください」というようなものではなく、当時のロマン主義全盛の音楽界にケンカを売っている、更には「芸術とは何か」を根底から問い直す批評的・反骨的な行為だったと認識している。ダダイスムに関わっていたことはその証左だと思う。ただ、私はサティについて詳しくないので、私の認識の誤りかもしれない。また、そもそも事実は確かめようもなく、それに作中でも「これは私が想像したエリック・サティの話」と断っているのだし、ミヤタユーヤ氏独自の大胆なフィクションとして仕上げているので、その点はどちらでもいい。
ただ、事実がどうかはどちらでもいいのだが、ミヤタユーヤ氏がサティ像を自分に引き寄せ過ぎているように感じたのは気になった。「美しい音楽を奏でる際は、美しい動きになる。だから、その動きをすることから始めていった。」というような部分は、ダンサーでもあるミヤタ氏自身の考えを重ねて書かれているものだろう。作品に、サティの顔でも、サティから距離をとった脚本家の顔でもなく、ミヤタ氏自身の顔が透けて見えてしまうのは、少し興ざめだった。(勿論、その点が良いという人もいるかもしれないが。)「美しいものは正しい」というのも、サティの言葉ではなく、ミヤタ氏の信念のように聞こえた。
そのような部分から、ミヤタ氏が自分にサティを重ねて描いた物語なのだろうと思って観ていたので、「天才」「天才」と連呼される部分に、最初はとても違和感があった。そもそも私は、特殊な表現者を「天才」などと神聖化するのが大嫌いだからだ。そう思っていたら、物語の後半でひっくり返されて、サティの天才像は、盟友のクリス(虚構の人物?)と共に創り出されたものだとわかる。
そのクリスも、「自分は天才と豪語していたが、実は、ただの凡才だったのだ」と告白して、死んでいく。その死んだクリス(Kris?)の想いを背負い、Eric Satieと Krisとの共同作品として、Erik Satieが生まれたという話。(ただ、イニシャルからkをとったなどとは語られないので、クリスは一般的なCris という表記で、単に本名と芸名の差異というだけの意味なのかもしれない。)
いずれにせよ、この大胆な創作物語は面白かった。天才がいる訳ではなく、様々な出逢いや影響の中で天才と呼ばれる人物が作り出されていくということだろう。
終焉後のカーテンコールで、ミヤタ氏は、「この作品は、自分が書いた言葉だけではなく、様々な友人の言葉を脚本に使わせてもらっている」と述べ、「自分一人でできた舞台ではない」ということを強く語った。そして、照明・音響・製作などのスタッフにも感謝の念を述べた。それが、まさにこのサティの物語で語られている内容と重なっていた。「エリック・サティは一人の力で生まれたのではない、この舞台も私一人の力で創りあげたのではない」とでもいうように。
その際、想いが溢れたのだろう、ミヤタユーヤ氏は、時に言いよどみ、言葉を詰まらせながら、ゆっくりと言葉を発していた。その姿、呼吸、空間のすべてが、今まで演じられてきた舞台そのものよりも、凄い作品となっていると感じた。これが本当の芝居であり、踊りだとさえ思えた。
(この点まで踏まえれば、満足度は★4だが、あくまでこれは作品外と判断し★3)
満足度★★★
別物として
良くも悪くも、寺山修司の世界とは別物になっていた。
寺山のモノマネのようなものは観たくなかったので、そういう意味では良かったが、ならばなぜ寺山の『無頼漢』を元にしたのかはわからなかった。
反権力がテーマなら、中津留章仁氏自身のオリジナル脚本の方がよっぽど説得力がある。(流山児氏の作品は、寺山脚本のものしか私は観たことがないので、他の作品のことはわからない。)
そこに寺山でなければならない抜き差しならないものは感じなかった。
どんちゃん騒ぎをしていたという印象しかない。
助成金をとるためや、客を呼ぶために、寺山をダシに使った企画なのだろうか、、、
外波山文明氏はさすがの存在感だった。
声優として有名な三ツ矢雄二氏も、存在感があった(と言っても、演技というより、やはりその声の存在感の部分が大きいが)。
満足度★★★
キャストBを観劇
意識が高く、川村毅氏の演出に喰らいついていった大学生たちの姿(役者もスタッフも)が素晴らしかった。
ただ、そのプロ志向の感じが、良くも悪くも、、、。
ネタバレBOX
学生が演じているということを考えると、極めて高い水準の芝居だったと思う。
ただ、作・演出がプロの基準で作られていたので、
観客としてもその基準で観てしまった。
そう観ると、正直、演技が弱いなと感じてしまう部分が多々あった。
学生を育てる公演としては、素晴らしいものだと心から思う。
最近は、高い意識を持って作品制作に臨む若い世代が減り、
手近なテーマとやりやすい演技を基に作品創りをする人が多い。
そんな中で、やはりプロの基準はここなのだということを、今後の演劇界を背負っていく学生に示すことは、極めて有益なものだと思う。
学生にとって、こんな幸運なことはない。
ただ、いち公演としては、やはりプロ予備軍の芝居という印象。
純粋な観客としては、逆に、
プロにはできない、学生にしかできない強度を持った芝居が観たかった。
内容としては、劇中劇的構造の芝居。それも、ギリシャ悲劇を基にしつつ、それが変異した物語が展開され、とても複雑な構造になっている。更に、そこに今の(または初演時の)日本が抱えている問題と、家族というものが持つ普遍的な問題も重ねられていることで、その意味はさらに多様化している。
構造的にも、意味内容としても、何重にも層が重なって世界が構築されているという印象。
エレクトラ役:鶴田理沙さんの存在感と
ヘクトル役:渡部太一さんの演技が印象に残っている。
渡部さんの演技を見るのは今作で3度目。どんどん力を付けていると感じる。
インテリの観念遊び
100人の素人を舞台に乗せ、統計学をしただけ。
ちょっとした社会意識をまぶせるのが、最近の流行か。
一見実験的に見えるが、演劇の概念は何も壊れていないし、拡張されてもいない。
豪華なミュージシャンの生演奏が付いているが、その意味も全くない。
*リミニ・プロトコルの活動には以前から注目していて、『ムネモパーク』(2008)、<『カール・マルクス:資本論、第一巻』(2009春)はテレビで)>、『Cargo Tokyo-Yokohama』(2009秋)と観てきたが、いずれも面白いとは思えなかった。それでも、その姿勢は他に類を見ないものなので、3度目の正直とばかりに今作を観た。だがやはり、今作も私には興味の持てない作品であった。もう観ることはないだろう。
満足度★★★★
場所の活かし方が秀逸
舞台装置を使わず、場所を活かした演出が、3作とも素晴らしかった(一作品、照明は使っていたが)。
作品内容も学習院女子大学という場を活かしたもの。
個々の感想はネタバレにて。
ネタバレBOX
『こうしてワタシは完全になる ~1969年 ある女子大生が書いた日記より~』(作・演出:小池竹見) ★4
高野悦子の『二十歳の原点』を元ネタにして作られた脚本を、2人の役者と共に、観客が台詞を読むことで舞台が成り立つ。
観客は男1・女1・女2と割り振られ、脚本を渡され、その役の台詞を読むことになる。
まず、どういう場面設定で、観客が芝居に参加することになっているのか、よくわからなかった。そのため、芝居に参加しているというより、イベントごとに参加ているような印象になった。
また、その脚本を観客に読ませることで、何を意図しているのかも、よくわからなかった。観客にその言葉を発語することで内面化して欲しいのか。それとも、単に観客参加の興奮を味わわせたいだけか。
ただ、実験のズルいところで、意図はわからなくとも、面白い部分は発見できてしまう。
私は、台詞を読むことよりも、それを読んでいる観客の姿を観るのが面白った。指示されたことを遂行すべく一生懸命に台詞を言っている人もいれば、ぼそぼそ言っている人もいる。バカバカしいと思ってか、単に恥ずかしいのか、台詞を言っていない人もいる(ごく少数だが)。
また、ほとんどの人は、なぜか脚本を追うことに必死で、うつむいてばかりいた。そういう観客は、劇に没入していたということか?
いずれにせよ、観客とは何かということを深く考えさせられた。
私は、観客参加でありながら、演出家の言いなりになるのでは、結局受動的観劇態度でしかないじゃないかと、この演出に乗っかるのは少し嫌だったが、やらずに批判するのも違うかなと思い、小さな声で台詞を言いながら、周りの観客を見続けた。
結果としては面白く観劇したが、私が面白いと思った点は作品テーマとは何ら関係していないので、結局なぜこんな演出をしたのかは全くわからなかった。
『放課後 女子学生 1920』(作:古川健/演出:倉迫康史)★4
そもそも、この公演に足を運んだ理由は、劇団チョコレートケーキの古川健氏が描く、戦前の女学生の日常が観たかったからだ。正直に言えば、期待外れだった。よくできた作品ではあったが、今までに何作か観た古川作品にある細部の描写力の凄味は感じなかった。ただ、ラストの問いの残し方は秀逸だった。私たちが生きている日常の時間、それが大きな歴史の流れの一部であるということを深く感じさせてもらった。
ここで、問いかけられたことが、3作品全体の臍(核)になっている。大きな時代の流れの中で歴史を認識することは難しいが、その細部には、人が笑い、そして泣く日常の日々がある。
奇しくも、特定秘密保護法案が衆院可決された日の上演であった。
『40歳の女子大生 -女子学生2020‐』(作・演出:横田修)★4
広い空間(学生が食事や休憩をするスペースだろうか)を活かした演出が素晴らしかった。空間の側面はガラスになっていて外が見える。そこにはドアも付いている。それを活かし、役者はそのドアを出たり入たりする。反対側は吹き抜けになっているので、役者はその奥に消えていったり、戻ってきたり。壮観だった。ラストも外に消えて行って幕。まるで、唐組の芝居のラストシーンのようだった。
作品内部の演出も素晴らしく、役者の演技がとてもよかった。特に、青い女の子(お母さんが亡くなったという子)と市橋朝子さんがよかった。
脚本の内容もよかったのだが、社会的な問題を描きこんだところが、妙にとってつけたような感じになっていたのがもったいなかった。
勿論、そういう社会的な大きな流れとそこにある日常との問題がテーマなので、ある部分仕方がないのかもしれないが、もうちょっとさりげなくその問題が描きこまれていたら、もっと素晴らしかったのにと思う。
これまでの2作のことをこの作品で取り込んでいるのもよかった。
歴史を考える際に、まずは手触りのある日常から世界を捉まえようという姿勢が素晴らしかった。
満足度★★★
変わった演出
変わった演出なれど、それがどこに向けて作られた作品かわからなかった。
ただ、商店街にある理髪店の2Fスペースでの公演というのは、興味深かった。
隣の飲み屋の客のおじさんが、公演前に並んでいる観客に声をかけていたり(演出ではない)、公演が始まってからも、そのおじさんが飲み屋でしゃべっている声が聞こえてきたり、劇場ではない空間、その場にしかない生々しさがあった。
立会川という場所自体、さまざまな歴史的背景を持っている地のようで、パンフレットに「坂本龍馬が青年時代を過ごしたことでも有名」とある。隣にある公園にも坂本龍馬像が立っていた。また、「一説には、昔、近くにある鈴ヶ森形場へ送られる罪人が、家族たちと最後に別れを惜しむために立ち会う場所ということから「立会川」と呼ばれるようになった」ともある。この歴史を背負った場所を、「ヴォイツェク」に重ねて上演されているようだ。だが、そもそもヨーロッパの話であり、上演とこの場との連なりを感じることはできなかった。
ネタバレBOX
場所と芝居との関係も、芝居内部の演出自体も、有機的な必然性に貫かれたものを感じなかった。
その逆に、有機性をあえて断ち切っているという前衛性(異化)も感じなかった。
そのため、変わった演出がどこに向かっているのか、わからなかった。
もったいないと思った。
ただ、マリー3:白井愛咲さんが足で医者を演じたのは面白かった。
アイデアが面白いというだけではなく、足できちんと医者を演じられていたと思う。
音楽の付け方も興味深かった。
即興的なノイズギター、ラジオノイズ、蓄音機風のレコードプレーヤーでのスクラッチノイズなど、音楽自体としてはそれほど新奇なものではないが、舞台に合わせてその場でノイズを付けるという作品は、ありそうで観たことがなかったので、臨場感があってよかった。