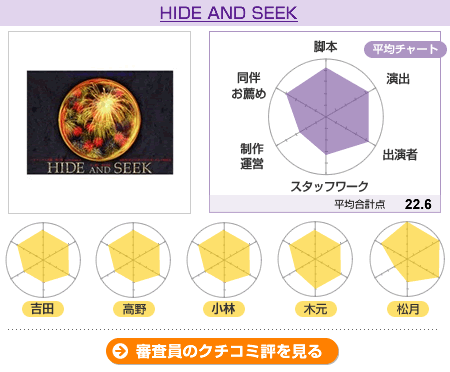各団体の採点
江戸川乱歩と横溝正史と夢野久作が同じ部屋でともに語るというだけで、相当に面白いです。しかも彼らの代表作の登場人物(明智小五郎、金田一耕助、呉一郎)まで同じ次元に出て来るのですから、愉しみはさらに増します。
ザムザ阿佐ヶ谷の和風空間で大きな赤いカーテンを使って、探偵推理小説、幻想怪奇小説のムードを上手に作っていました。※私は最前列で堪能しましたが、後方の席からだと高さがあるので見え方が違ったかもしれません。
これまでの公演との違いで顕著なのは、まず笑いが多いこと。役者さんは緊張が途切れない丁々発止のやりとりだけでなく、どたばたパロディにもチャレンジしています。感情を内に込めることで密度を上げる演技を、貪欲に外へと開放する方向にも広げたのは、大いに歓迎したい変化でした。また、「前回あの役をやってた役者さんが今回はこんな役!?」という驚きも良いスパイスになりました。
パラドックス定数というとワン・シチュエーションの会話劇という印象でしたので、今回のように次々と場所が変わるのは新鮮。脚本・演出を手がける野木萌葱さんの力量を再確認できました。集団としての厚みも増してきていると思います。
色んなタイプの男の魅力を様々な角度から見せてくれます。キャストに絶世の美男子が揃っているわけではないけれど、今流行りの“イケメン芝居”に似たところがある気がしました(笑)。私は敢えて気取る姿勢が面白いと思いますが、それが鼻につくお客様もいらっしゃるかもしれないな~とも思いました。
約2時間の上演時間は、会場の環境から考えても少々長すぎた気がします。
「虚構と現実の境界」--その曖昧さを、物語としても目に見えるものとしても描き出した力作。舞台という表現の可能性を真摯に追求して、視聴覚ともに同じ方向性の刺激を生み出すことのできた稀な例ではないかと思います。中央の背景に三角巾のように赤い布の後方に垂らして、その裏から出入りさせたり、さらに床に広がる赤い布の下からうごめくように這い上がらせたりを可能したあの美術は、シンプルながら秀逸でした。
江戸川乱歩と横溝正史と夢野久作という作家たちに交流があったってことも知らなかったし、子供のころに探偵小説に明け暮れたなんて本好きでもなかった自分ですが、それでもきちんと3者の関係が理解できたということは、作者の取材力とそれをせりふを通して伝えられる咀嚼力が優れているんでしょう。しかも、史実をモチーフにしたフィクションというだけにとどまらず、きちんとがその物語を通して、「小説の登場人物は作家のものなのか?」という劇作家の方ならではの視点がはっきり描かれていることで、「評伝劇」風作品からまったくのオリジナル作品へ昇華できたと思います。作家が死んでもなおテレビや映画で生き続ける金田一耕介。今や「現実」の作者よりも大きな力を持つかもしれない「虚構」の存在は、コンテンツの時代と呼ばれる今、ますます怪物じみてくるかもしれないなと思った次第。
出発点は『プライベート・ジョーク』と似ていますが、登場人物たちへの思い入れが滲み出ている分、遊びに見える瞬間があったり。そこを遊びで終わらせないよう捩じ伏せる力はさすがですが、観たことのないそのサービス精神には若干の戸惑いを感じるほど。こういうことができるようになったのも、きっとカンパニー化したからこそだとは思います。 新たな試みや企みにしっかりと答えている俳優陣。いつもの緊張感溢れるやり取りが観てみたかったりもしますが、前に出てくる彼らも魅力的でした。
私自身あまり小説を読まないので、ストーリーを理解するのに大変でしたが 小説の中の登場人物の表現方法や読者の存在方法など、大変を刺激を受け、どんどん引き込まれていく要素があったと思います。明らかにお笑い用の場面ではちゃんと大爆笑させてもらったり、とても面白い作品でした。