麻美 雪の観てきた!クチコミ一覧

愛情の内乱
ティーファクトリー
吉祥寺シアター(東京都)
2016/05/12 (木) ~ 2016/05/25 (水)公演終了
満足度★★★★★
TFactory:「愛情の内乱」
夏のような陽射しの照る土曜日の昼下がり、吉祥寺シアターで末原拓馬さんが出演されているTFactoryの舞台、「愛情の内乱」を観て参りました。
今回の舞台は、私にとっても、色々と感慨深く特別な舞台でした。
なぜかと言えば、生前母が好きだった白石加代子さんがこの舞台に出演されていたからで、母の影響で、私も白石加代子さんが好きになり、1度白石さんの舞台を観たいと10代の頃から思っていたのが今日、末原拓馬さんと共演のこの舞台で拝見出来たからだ。
若かりし頃の母の写真をバックに忍ばせて、母と一緒に観ている気分になる。生きているうちに母にも観せてあげたかった。
舞台に置かれたちゃぶ台と襖、舞台に有るのはそれだけ。ちゃぶ台は家族の象徴。
そこで繰り広げられるのは、母と3人の息子の「愛情の内乱」。
遠い未来の近い過去。とある地方の大きな家。立ち退きを迫られているその家に暮らすのは、母と次男と謎の家政婦。
家族を絶対的な力で支配しているのは、母。その母から逃れる為に志願して戦場に行った長男と母を愛していながら恐れ、長い間家を出ていた三男。
退去勧告を受けても尚、家に居座り続ける一家に興味を持つ男が、TVのドキュメンタリーを撮りたいとやって来たのと時を同じくして、戦争で英雄になった長男アニと長い間家を出たままだった三男のジンが帰って来て、家族の歯車は思いもかけぬ方向に回って行く。
顕になってゆく家族の問題と過去の記憶。最後に待ち受けている結末とは....。
あらすじを言うとこういう物語なのだが、これはきっと、誰もが思い当たる親と子の物語であり、私の、そしてあなたの物語でもある。
良くも悪くも母は子供が老人になったとしても母なんだと思う。私の母は子供の顔を見ただけで子供の心や状況を理解して、見守ってくれる母だったが、白石加代子さんの母は、どちらかと言えば、私の父に近い。
そんな父から逃げたくて、逃れたくて、煩悶し葛藤し、時に憎みもし、父と離れたいと思い続けた母が亡くなった15歳の時から、父が兄の家の近くの施設に入って離れるまでの34年間を、この舞台の白石加代子さんの母を観て思い起こした。
高圧的で支配的、息子たちにとっては、ある種恐怖でもあり、疎ましくもあり、心の奥底では愛している白石加代子さんの母を見ているうちに、ふと思う。疎ましく重く思っていた父の高圧的な態度は、私への父なりの愛情を間違った発露の示し方だったのだと。
母を愛し過ぎていた故に、容貌は年々母に似て来ながらも、母のようにはなれない娘の私への苛立ちと失望と、そのことで、私にあたってしまう自分への苛立ちと多少なりとも持ち合わせていた私への愛情を上手く表現できず、誤った表現と発露で埋め戻す事の出来ない溝を作ってしまった父の心に思い至る。
白石加代子さんの演じる母がそうだったように。
認知症が進み、苛立ちを暴力で表し始めて兄の近くの施設に入り離れた父は、もう、私のことも忘れ始め、私を私と認識することさえ覚束無くなりつつある。「愛情の内乱」を観て、 ふと、その事に気づいて少しだけ父を赦し、少しだけ理解できた気がして最後に泣いた。
大場 泰正さんの長男アニは、もしかしたら、私の兄と重なるのかも知れない。両親に反抗したこともなく、親思い、友達ともめることもなく、良く出来た兄と言われ、其れに比べてお前はと比べられて育った私。
大場泰正さんのアニも正に、良く出来た兄と言われて育った長男。しかし、そう言われ続ける長男のプレッシャーと、「良く出来た兄なのに、反抗ばっかりして、お兄ちゃんを見習いなさい。」と言われ続けていた私は、兄にとっては、家では言いたいことを言える、気楽で我が儘勝手で反面、羨ましいとも見えていたかも知れない。
誰よりも私の味方で、私を判ってくれた母だったけれど、唯一今でも、それは言わずにいて欲しかったのは、「お兄ちゃんに比べて」「お兄ちゃんを見習いなさい」という言葉と、死のひと月ほど前に言われた、「あなたは、打たれ強いから心配ないけど、お兄ちゃんは打たれ弱いから心配。私に何かあったら、お兄ちゃんを頼むわね。」という言葉であり、その言葉に長らく呪縛され、苦しんだ事を兄は知らないだろう。
二人兄妹の末っ子でありながら、長女でもある私は、どちらの面も持ち合わせ、どちらの立場も何となく解る。
そういう意味において、一番感情移入をして観られたのは、兼崎健太郎さんの次男ドスと末原拓馬さんの三男ジン。
兼崎健太郎さんのドスは、心の奥底では母に愛して欲しかった寂しさと愛情を持っていながら、絶対的な力で支配する母を疎ましく思い逃れたい、家を出たいと思いつつ、残された母と母への思いが踏みとどまらせ、逃れたいと思いながら息子としての葬り去ることの出来ない、家族の愛情というに引き裂かれそうになりながら、自らをこの家と母に縛りつけているという事にさえ気づいていながら、行くも戻るも出来ない自分への苛立ちと諦め、其れに抗う気持ちを持て余し、葛藤しているように思った。
それは、嘗ての私の姿と重なり、胸が軋んだ。
末原拓馬さんのジンは、母を好きで愛しているが、その反面、母の絶対的な支配力に、自分が搦め捕られていつか、自分が自分として生きることが出来ないのではないかという不安と、これ以上この家にいて、母の影響下に居続けることへの恐怖から、家に居られないと家を出ることを選んだ。
その、ジンの葛藤と不安もまた、私が父に対して長年感じ続け、呪縛されていたものでもあった。
ここまで読むと、重くシリアスな母と子の愛憎の話のようだが、コミカルでユーモラスな笑いも随所に散りばめらていて、鬱々とした感じは一切ない。
随所に笑いを散りばめながらも、しっかりとそれぞれの抱える痛みと葛藤、母と子、家族の愛情という、厄介で、でも、どうしようもなく愛しい家族の姿がある。
最後の最後に、母の自分達への愛を知った息子たちは、その先に新しい家族の愛情の形があるのではないかと思わせる。
その意味で、これはある種のハッピー・エンドの物語なのではないかと思う。
心に様々な思いが兆した舞台だった。
文:麻美 雪

イエドロの落語其の参 再演!!
イエロー・ドロップス
新井薬師 SPECIAL COLORS(東京都)
2015/12/18 (金) ~ 2015/12/20 (日)公演終了
満足度★★★★★
イエロー・ドロップス:「イエ・ドロの落語 其の参 再演」
先週の土曜日、西武新宿線新井薬師前から歩いて5分程の所にある、Art Live Space 「Special Colors」にイエロー・ドロップスの「イエ・ドロの落語 其の参 再演」を観に行って来ました。
前回の「イエ・ドロの落語其の参」に新たに2つの落語を加えて、再演というより、これはもう、新作と言ってもいいような、パワーアップして、面白さも、ホロッとした切なさも増量していて、私の中では、「イエ・ドロの落語 参.五」と言った感じ。
前回と同じ、八幡山の秘密の見世物小屋でやるはずだったこの芝居を新井薬師前のArt Live Space 「Special Colors」に移しての上演したその意味が、始まった途端にすぐにわかった。これだけのパワーと熱量、秘密の見世物小屋では、収まりきらなかったと思う。
より、近くにおぼんろのわかばやし めぐみさんとさひがし ジュンペイさんの息遣い、間合い、表情のひとつひとつが感じ、観られる。
物語コーディネイターの末原拓馬さんの紡ぐイエ・ドロの落語の世界は、更に滑らかに、濃く、深く、ホロリと切なくて、とてつもなく可笑しくて、笑って泣いて、ラストに向かうにつれて、さひがしさんの金蔵が前回以上にしみじみといいお男(ひと)になっていて、めぐみさんのお染は、情のあるいい女になっていて、胸にきゅんときて、ほろりっと涙が頬を伝ったりなんぞして、この芝居が観られたことを幸せに思った。
今回新たに加わった、追い剥ぎならぬ「追い剥がれ」、さひがしさんのセクシー・シーンに一瞬、目のやり場に戸惑いながらも、追い剥がれて行く時のめぐみさんとのやり取りの間合いが可笑しくて、可笑しくて好きな箇所。
イエ・ドロの落語を観ると、「やっぱり、落語っていいよね~」と思う。
今回、物語コーディネイターの末原拓馬さんも、短編作品だぼだぼラボラトリー の「ズタボロが捧げる聖夜の祈り」で出演。
前回の「イエ・ドロの落語 其の参」、「ゴベリンドン」にしても、「イエ・ドロの落語」、「だぼだぼラボラトリー」にしても、末原拓馬さんの紡ぐ物語の世界が私は大好きなんです。
紡がれる世界はもちろん、紡がれ、声となって空間に放たれるその言葉のひとつひとつが、五感をフル稼働させ、感情がうねり、水が静かに染み込むように心を浸す。
放たれた言葉が、シンと冷えたクリスマスの夜空に昇って、きらきらと星の雫になって落ちて来る、キュンと痛かったり、切なかったり、寂しかったりするのだけれど、掌に落ちて溶けた雪が暖かいように、いつもどこかに仄かな温かさとやさしさがある。
クリスマスの夜空、頬を掠める冬の夜の風、温かな部屋の空気、ひとひら、ふたひら、心の中に、言葉の雪の華が舞い落ちて、何かをぽつりぽつりと残して行く「ズタボロが捧げる聖夜祈り」。
クリスマス近い、師走のとある土曜日の宵、笑って泣いて、いろんな想いと感情を胸に抱いて、外に出れば冬の夜の冷たい風とキンと清んだ美しい夜空。
心はぽかぽか、たくさんの幸せな気持ちとわくわく、楽しい心を胸の中に両手いっぱいに抱えて帰路に着いた「イエ・ドロの落語 其の参 再演」だった。
文:麻美 雪

フランス革命三部作
芸術集団れんこんきすた
シアターノルン(東京都)
2016/07/20 (水) ~ 2016/07/29 (金)公演終了
満足度★★★★★
『フランス三部作 Bleu~青嵐の憧憬~』
舞台にあるのは、Rougeの時にあった両端トリコロールカラーの幕だけで、舞台の上には小道具ひとつない舞台の上で、4人の人物たちによる物語が描かれて行く。
貴族令嬢マリー・アニュースと彼女に仕える執事家の青年セルヴィニアン、従僕の青年アルノー、革命家のロべスピエール。
4人が、革命の渦に呑まれながらも愛と友情と誇りに必死に生きた若者たちの青春を描いた物語。
4人だけで「革命」を描く。
Rougeは、女性革命家の視点、Bleuは貴族令嬢から図らずも革命に身を置くことに
なった一人の女性の視点からみた革命が描かれる。
最近、自由と愛するものを守るために、武器を取り、戦うことの矛盾とジレンマについて、考え向き合う舞台を観ることが続いていたのだが、この作品でもその事を改めて考えさせられた。
自由と平等と平和を得る為に武器を取り戦い、血を流すことの矛盾とジレンマと、いつしか暴走して行く恐怖と、そこから生まれる新たな差別と憎しみとやる瀬なさをこのBleuを観て改めて感じた。
差別のない自由で平等で平和な世界を創る為の革命であり戦争が、いつしか暴走し、嘗て自分が味わった苦しみと悲しみを新たに生み出し、自分がされたことを自分が人にしていることに気づかない怖さとジレンマ。
力や暴力、思想弾圧による革命や戦いでは何も変わらないことを、何故これほど歴史で繰り返しても気づけないのか。
そんな中で、小松崎めぐみさんのマリー・アニューズの掛け値なしの透明で真っ直ぐな明るさと純真さ、純粋さに触れた時、涙が溢れるほど心に染み入る。
人の心を開くことで、平和で平等で自由な世界を創ることが出来る事に気づきかけ、それでも一途に革命こそが全てを変えると頑なに思い込み行動し、やがて当初の思いとは裏腹に、独裁者へと変わっていってしまった、早川佳祐さんのロベスピエールに、平和で平等で自由な世界を守り、得る為に戦うことの矛盾とジレンマを感じ、胸に深く痛くもどかしく、ロベスピエールの悲しみを思った。
中川朝子さんのセルヴィニアンもまた、大切なマリーを守る為に、戦いに身を投じざるを得なかった姿と一途さが切なくも、最後まで守り切ろうとするその姿が、とても潔くかっこいい。
そんな中、いつもマリーをそっと見守り続け、最後まで傍にいて、マリーの心を守り続け、唯一武器を取らず、戦うことに身を投じなかった平田宗亮さんのアルノーは、ほっとする存在だった。
やはり、変えられるのは、綺麗事かも知れないけれど、心であり、愛であり言葉だと思えてならない。
「物語には、言葉には、力がある。だから、物語で、言葉の力で世界を変えたい。」私の好きな劇団の主宰であり、俳優である末原拓馬さんの言葉だが、私も同じ思いで作家になろうと思った。その言葉の持つ意味がこのBleuの舞台を観て重なった。
めぐみさんのマリー・アニュースの透明で真っ直ぐな、優しく強い純粋さと純真さが胸に染みて包み込み、様々な心と感情を抱き、駆け巡り涙が溢れた。
めぐみさんから、『ぜひ、観て頂きたい』とご案内を頂いたのが解る、心に焼き付いたとても素晴らしい舞台だった。
文:麻美 雪

黒き憑人
GAIA art entertainment
シアターグリーン BOX in BOX THEATER(東京都)
2015/04/23 (木) ~ 2015/04/26 (日)公演終了
満足度★★★★★
「黒き憑人」
「あなたの人生はあと4日で終わります。」そう、言われたらあなたは一体どうしますか?
「あと4日、やり残したこと、思い残しがないように、あなたをお手伝いするのが私の使命。何かやり残したこと、思い残すことはありませんか?」と憑人(死神)に問われたら、あなたは、そして私はどうするだろう。
この舞台を観ている間中、ずっとこの2つの事を考えていた。
足立優樹さんは、「あと4日」と命の期限を切られた、喧嘩っ早く、我儘で、すぐに物事を投げ出し、自分の事しか考えなかったが、死神の伊座波や暴漢に襲われた乃璃子を助け関わって行くことで、本来のお人好しで優しさと、人の為に動く自分を取り戻し、気持ちが行き違ったままだった父やバンドのメンバー、関わった周りの人々を思いやれるように変わって行く、人気バンドのヴォーカル倉菱礼を丁寧に、繊細にして激しく演じていた。
実は、「あと4日」の命の期限を切られたのは礼の父であり、礼と気持ちが行き違ったままであることを悔やみ続けていた父の心残りが礼との和解であったことを知った礼が、最後のシーンで父にかけ続けた言葉と姿に、涙が込み上げて、溢れないようにずっと上を向いていた。
船戸慎士さんの死神は、今までの死神のおどろおどろしいステレオタイプの死神像を軽やかに打ち破り、お茶目ながら、肝心な所では、きっちり強くかっこよく、礼を一番よく理解し、要所要所で、名言をさらっと言いながら、結果的に礼を導いて行く死神伊座波を飄々と演じていた。
小祝麻里亜さんの乃璃子は父との心の距離に葛藤しながらも、純粋で爽やかな乃璃子だった。
佐藤和久さんの乃璃子の父、龍之介は、政務と娘への愛情の狭間で悩み、乃璃子への愛情の示し方が解らない、不器用な父の姿を見事に現していた。
鶴巻美加さんは、三役されたのですが、とても若いのに礼の母の心情が伝わって来て、しみじみした。
今駒ちひろさんも、三役を演じられたのだが、三役を違う顔で演じられていた。
最期に、保志乃弓季さんの龍之介の秘書原田は、秘書として、一人の女性としても密やかな想いを抱きつつ、龍之介をサポートして来たのに、龍之介が信頼しているからこそ、良かれと思って秘書ではなく乃璃子のサポート役にしようとしたのを、その意味を取り違えて、乃璃子を誘拐させるという過ちを犯してしまう、切なく強く胸がキュンと痛む一人の女性として描き出していた。
重い内容になる話を、軽妙に面白く、それでいて「あと4日の人生」と言われた時、自分は何をやり残し、何を思い残したと思うのだろうかと考え、これからどう生きるか、親を始め自分の周りの人、自分と関わった人の事を改めて考えさせられた素晴らしい舞台だった。
文:麻美 雪

フランス革命三部作
芸術集団れんこんきすた
シアターノルン(東京都)
2016/07/20 (水) ~ 2016/07/29 (金)公演終了
満足度★★★★★
『フランス三部作 Rouge~花炎の残像~』
劇場内に一歩踏み込むと其処には、両端をトリコロールカラーに染められた幕がかかり、その前に1脚の椅子と花の生けていない花瓶のようなものが乗ったテーブルが1つ置かれた舞台があるだけ。
舞台の幕が上がり、白い布の塊が蠢き、這い出すように現れたのは、女性革命家テロアーニュ。
ベルギーに生まれ、イギリス、イタリアと流転の人生を送り、流れ着いたフランスで民衆による革命に出会い、アンヌから「フランスの自由の恋人」と称される女性革命家テロアーニュ・ド・メリクールとなった実在の女性革命家の生涯を、中川朝子さんが激しく、艶やかに鮮やかに、切なくも毅然としたひとりの女性として描き駆け抜ける一人芝居、『フランス三部作 Rouge~花炎の残像~』の物語の扉が開いた。
優しくはあるが、継母の暴力から守ってくれなかった父に絶望して、家を飛び出してから信じては裏切られを繰り返し、イギリス、イタリアとその都度自分の居場所を探して流転の生活を送っていたアンヌが、最後に行き着いたのは、「自由と平等の国を創る」という思想を旗印にして革命を起こしていたフランス。
革命に出会ったことで、アンヌの中の何かが弾け、革命へのめり込んでいった彼女の前に大きな壁として立ちはだかるのは、またしても男たちであり、女という自分の性。
女であるテロアーニュが注目され、認められることで、敵視され、陥れようとする男たちの狭量さ、テロアーニュを翻弄してきた男たちの視線と目線、女であるということ。
革命家を標榜する彼らでさえ、男としての本質は変わらないことに憤り、絶望したであろうテロアーニュ。
命尽きるまで、テロアーニュの身を焼き尽くした、赤い革命への熱の滾りは、その最後に緋へと昇華してのではなかったか。
彼女の目指した革命は、性別や貧富の差、宗教や思想、地位の差で差別されない平等で自由な世界にすることであり、決して血で血を洗い、誰かを陥れたり排除するものではなかったはずだ。
テロアーニュの『革命は、心を変えること。心を変えなければ革命は起こせない。』の一言が胸を抉る。
心に差別や区別を持っているうちは、その考え方を変えなければ、自由と平等を手にいれる革命は起こせない。
最近のテロの報道を見る度に感じることも正にこのことである。
時に可憐に、時に艶やかに、毅然と激しく、鮮やかに切なく、命を緋(あか)く燃やし尽くしたテロアーニュ・ド・メリクールそのものの中川朝子さんが其処にいた。
一人の女性の身の内側を染め尽くした革命という名の熱の赤、その赤が身の内全てを焼き尽くし緋(あか)に変わる迄を一人で描き切った、中川朝子さんの熱の紅が私の心に移り、感じるものがあった素晴らしい舞台でした。
文:麻美 雪

at Home Coming
Team ドラフト4位
ART THEATER 上野小劇場(東京都)
2016/07/20 (水) ~ 2016/07/24 (日)公演終了
満足度★★★★★
Team ドラフト4位 第2回公演『at Home Coming』
居酒屋の横の急な階段を降り切って、右を見ると、すぐそこに舞台と客席が現れる上野小劇場は、場所自体もアットホームで、この舞台にぴったり。
今回は、奈穂さんの初脚本、兵藤さんの脚色。
奈穂さんから、「初めて脚本を書いた舞台を観に来て頂けたら」とご連絡を頂き、これは何を措いても駆けつけなければと観に行って参りました。
「夢を持って」「思い続け、言い続ければ夢は叶う」というと、恐らくは、「そんなの嘘だよ」「叶わない夢だってある」、「叶わないから夢なんだよ」「そんなのきれい事」という言葉が返って来ることがほとんどだと思う。
夢見荘に来た当初の松下芳和さんのノブもそんなタイプの青年。
それが、其々に夢と傷を抱え、それでも尚、それだからこそ尚更、夢を叶えるために、上手く行かなくて折れそうになっても、挫けそうになって傷付いたとしても、夢を見ることを止めず、叶えようとする姿に触れ、夢を見ることを、夢を持つことへの一歩踏み出そうとするノブは、きっと多くの人たちの姿でもあるのではないだろうか。
だから、観ているうちに、ノブの心中が自分の事のように思えてくるのだと思う
橘奈穂さんのサクも、過去に抱えた傷がストッパーになって、次に踏み出せないでいたのが、ノブと関わって行くうちに自分の傷を正面から見つめ、次へと踏み出す勇気を持つ姿に肩入れして観てしまった。
横山展晴さんのダクトの夢を持つきっかけが、私が作家になると決めたきっかけと重なる部分があり、思わず涙が溢れて、一番感情移入して観ていた。
去年、思いがけず子供の頃からの夢を叶え、文章を書く仕事のきっかけを得て、一歩踏み出した私は思う。
「夢は信じ続け、追い続け、言い続ければ叶う」と。
しかし、それはただ漠然と思い、追い、言い続けれるのではなく、何があっても続け、行動しなければ叶うものではない。
10歳の時に、傷ついた自分が物語や作家の綴った言葉で、励まされ、慰められ、力づけられたように、悲しい思いや苦しく辛い思いをしている人にそっと寄り添い、包めるような物語や言葉を紡ぐ作家になりたいと夢を持ち、40年書き続ける事だけは止めずにいて、去年初めて対価を貰って書く仕事をして、夢を叶える一甫を踏み出したからこそ、「夢は叶う」と言える。
観ながらそんなことや色々な思いや感情が目まぐるしく交錯する、温かくて、傷ついた心と背中をそっと包んで押してくれるような笑いとしみじみと染み入り、他人同士が各々の夢を持ち寄って、夢見荘に集まった住人たちは、誰よりもあったかい家族だと感じる。
ノブを始め、さまざまな傷と思いを抱えて、夢を追う夢見荘の住人たちを、時に核心をつき、時に抱きしめ、温かい目で見守り包み込む、ノブを始め、さまざまな傷と思いを抱えて、夢を追う夢見荘の住人たちを、時に核心をつき、時に抱きしめ、温かく包み込む、須佐光昭さんのマーコさんみたいな大家さんの家に住みたくなった舞台だった。
. 文:麻美 雪

フランス革命三部作
芸術集団れんこんきすた
シアターノルン(東京都)
2016/07/20 (水) ~ 2016/07/29 (金)公演終了
満足度★★★★★
『フランス三部作 Blanc~空白の抱擁~』
両端をトリコロールに染められた幕を背中に、舞台を跨ぐように据えられたギロチン台。
「最も人道的な処刑装置」として開発され、革命末期に多くの奪ったギロチンによる死刑執行。
マリー・アントワネットも露と消え、革命後期の恐怖政治と化した頃には、政治にも革命にも何の関係もない市民や子供までが、凡そ罪とも言えないような些細な罪で、死刑になりギロチンの露と消えた。
あのギロチンと代々処刑人の職を受け継いできた家に生まれ、革命期にはギロチンの全てを任せられた、死刑執行人「ムッシュー・ド・パリ」と呼ばれた男、サンソン。その命を奪ったギロチン台。
罪人の首を落とし続けたギロチン台と、死刑人サンソンの視点から見た革命と、死刑執行人の苦悩と真実を描いた舞台、『フランス三部作 Blanc~空白の抱擁~』。
『フランス三部作』は、女性革命家の視点から描かれるRouge、貴族令嬢から図らずも身を措くことになった令嬢の視点から描かれる Bleu、そして死刑執行人の視点から描かれるBlancの3つの視点で描かれる舞台。
死刑執行人とギロチンの視点からフランス革命を描いた舞台は、私の観て来た舞台で、私は初めて観た。
ギロチン台は、ギロチンの精と擬人化され、中川朝子さんのギロチン・マダム、濱野和貴さんのギロチン・シトワイヤン、調布大さんのギロチ・ンキュロットのギロチン一家として、観客の前に現れ、当時の情勢や革命の歴史やサンソンの事について、神出鬼没に現れては語る狂言回しの役回り。
ギロチンというと、おぞましく怖いイメージがあるが、このギロチン一家は、シニカルであると同時に何故だかじわじわとした可笑しみがある。
中川朝子さんは、Rouge、Bleu、Blancと3作品通しで全てに出演。Blancに至っては、ChariteチームとこのGenerouxチームの両方にシングル・キャストで出演されている。性別もキャラクターも全く違う役を、1日通して連続で演じるのは相当の体力と精神力が必要な筈だが、ギロチン・マダムを軽やかにコケットにひとつまみの毒と可笑しみを加えたマダムとしてBlancの中で生きていた。
濱野和貴さんのシトワイヤンは、去年此処で観た『リチャードⅢ世』とは、がらりと違い、たっぷりの皮肉と毒に、可笑しさとひとつまみの狂気を感じるシトワイヤン。
調布大さんのキュロットは、冷静にサンソンと革命を観つつも、何処かほのぼのとして、Twitter等でもかわいいという声が上がっていたが、何だかかわいさがあるキュロット。
武田航さんのデムーランは、人々から厭わしく忌まわしい仕事と、謗られ蔑まされ苦悩するサンソンの唯一の理解者で友人であり、革命によって、差別のない平等で自由な国を創ろうと革命に参加し、ロベスピエールと同じように次第に、独裁的になって行き、その事に気づいた時には引き返せない所まで来てしまった者の苦悩と痛みを感じた。
デムーランの妻小松崎めぐみさんのリュシルは、ただ一途に夫を愛し支える純真な姿が可憐で素敵だった。
死刑執行人の家に生まれ、兄と同じ苦しみを抱えて生きてきた加賀喜信さんのマルタンの家業を厭い家を出て、外の世界に行っても、結局は死刑執行人の家に生まれたことがついて回り、普通に暮らすことさえ儘ならない事に憤りと悲しみ、絶望を感じた姿が胸を刺した。
革命の理念に共感し、次々とロベスピエールたちの命により、痛みも疑問も持たずに死刑執行をサンソンに指示し、酷薄に見えた加藤大騎さんのダンヴィルが、自らもギロチンにかかる時に、サムソンに「お前が心配だ」と一瞬見せた人間らしさに、彼もまた、ただ、自由と平等と平和を願った革命に翻弄された一人の悲しい末路を感じた。
石上卓也さんのサンソンは、サンソンの佇まいが痛ましくも美しく、それだけに、厭わしく忌まわしい仕事と、謗られ蔑まされても、その家に生まれれば否応なしに継がなければならない者の悲しみと苦しみと葛藤とジレンマが犇々と伝わり、胸が締め付けられた。
人の手で、人の命を奪うことの葛藤、苦しみと痛み。それを一番感じ、心を苛まれていたのは死刑執行人のサンソンでなはかったのか。
木村美佐さんのサンソンの妻、マリー・
アンヌは、傷つき、悲しみと苦しみに苛まれ、葛藤とジレンマに懊悩するサンソンを静かで深く純粋な愛で包み、そっと見守り、毅然として支える姿に胸が震えて涙が溢れた。
一日通して観た3作品は、何れも素晴らしく、考えさせられることも、感じることも多かった。
『革命』とは、力や武力、弾圧で捩じ伏せるものではなく、今も蔓延る差別や区別を心から無くすこと。心をより愛あるものに変えること。心を変える事なのではないだろうか。
『フランス三部作』は、全て観ることによって、よりその事が強く伝わってくる素晴らしい舞台であり、3作品を通して観られたことを心から良かったと思う。
この舞台を観たことは、私の誇りであり宝物であると言える舞台だった。
文:麻美 雪
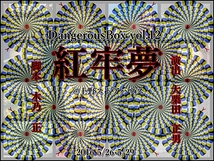
紅牢夢
Dangerous Box
上野ストアハウス(東京都)
2016/05/26 (木) ~ 2016/05/29 (日)公演終了
満足度★★★★★
書けない作家の頭の中と業
事前に解っていたのは、「謝罪ファンタジー」であるということと、冨永さんたちから、役者さんたちが死にそうに心身ともに大変だということだけ。
謝罪ファンタジー?死にそうに大変、一体どんな舞台なのか、頭に幾つもの疑問符だけが渦巻く状態で、舞台が幕を開けた瞬間、意味が解った。
オープニングから、激しい動きのダンス、軸になる役者はほぼ出ずっぱり、次々と被さるように重ねられて行く台膨大な台詞、叫ぶように、相手にぶつけるように発せられる言葉、劇中に何度も差し挟まれる激しいダンス、自身を抉るような台詞、肉体的にも精神的にも消耗するだろうと思った。
「謝罪ファンタジー」の意味は、内容が書けない時の脚本家、作家の頭の中の話だからだと解る。
この舞台を観ると書けない時の脚本家、作家の頭のがよく解る。交錯し飛び交う言葉と、右往左往する脚本家の頭の中の言葉と思考。それは、産みの苦しみだなんて月並みな一言では言い表せないものがある。
私自身の事を話せば、作家になると決心した12歳の春、決めたことがひとつある。作家になるなら、自分の痛みと傷にも目を背けずに、自分の中に存在する負も闇も情けなさ、不甲斐なさも見つめること。
そして、腑分けして、敢えて痛みや傷を抉る覚悟もした。逆に言えば、その覚悟をし、そうして来たから悲しみも痛みも越えられたとも言える。
脚本家にしろ作家にしろアーティストにしろ、物を創り出したり、言葉を紡ぎ書くということは、そういうことに目を背けないことであり、時にそれは自分の触れたくない部分を抉る作業でもある。
書けない、創り出せない状態というのは、そこから目を背けたい、逃れたいという、ものを創ること、ものを書くことを生業とした者が陥る苦しみであり、業なのだと思う。
それでも、創り出し、書いてしまう、創らずには、書かずにはいられない、創り、書くという行為から逃れられないのもまた、アーティストやものを書くことを生業にした者の業である。
それは、ただ創ること書くことが好きというだけでなく、創りたいもの、書きたいこと、創り、書かなければいけないことがあるから創るのであり書くのであり、創り、書くことを止めた時、自分の中の何かが死ぬような気がするのだと思う。
そんな事をつらつら考えながら観た舞台だが、そのややもすると重苦しくなりがちな内容を、笑いを散りばめエンターテイメント溢れる舞台にしたDangerous Boxの「紅牢夢」は、濃厚な時間を過ごした舞台だった。
文:麻美 雪

華蝶WHO月
朱猫
テアトルBONBON(東京都)
2016/04/13 (水) ~ 2016/04/17 (日)公演終了
満足度★★★★★
朱猫:「華蝶WHO月」
舞台は時代の流れと共に、苦しい経営状態のキャバレー。そんなお店を立て直すべく、一人の女性が立ち上がり、店の従業員たちと共にアイデアを出し合い、店を盛り上げようとするのだが・・・という粗筋の舞台。
粗筋だけ見ると、涙と笑の奮闘記のような舞台かと想像するが、そんなありきたりの想像を軽々と超える、「トムとジェリー」「バックス・バニー」「トゥイーティ」「バッドマン」「ポパイ」「チキチキマシーン猛レース」などのアニメーションで知られる、カートゥーンネットワークの・スタジオアニメのような動きのオープニング。
幕が開いて数分、音楽に合わせてそれぞれの登場人物の性格や話の粗筋が仄かにわかるような動きが賑やかに繰り広げられる。
その動きが、「トムとジェリー」を思わせ、子供の頃にリアルタイムで見ていた、カートゥーンネットワーク・スタジオのアニメーションを感じさせる動きが懐かしくも、楽しく、その動きは、舞台の中に随所に散りばめられている。
全編小粋で、ハチャメチャに馬鹿馬鹿しく、華やかで、艶やかで、ラスト近くにはしみじみした所もありつつも、くるくると回るミラーボールのようなきらめきを放つ、軽やかなコメディ。
條原志奈さんのかえでが、子供の頃に好きで何度も見た、カートゥーンネットワーク・スタジオの「ドラドラ子猫とチャカチャカ娘」「ドボチョン一家」に出て来る、女性キャラクターの色っぽい動きを彷彿とさせる。志奈さんは、うごきや表情が艶やかで、動きに色気があって美しい。
かつては指名No.1、今は自分に反発してくる若いホステスまいと丁々発止とやりあいながらも、店や若いホステスの面倒を見る、艶やかな色気が一本芯の通った、凛として潔い姉御肌のカッコイイ女。
志奈さんの座っている時の脚の置き所の綺麗さとカウンターに背中を見せて座っている時の後ろ姿が色艶気(いろけ)があって、かえでそのものでとても素敵だった。
江島 雄基さんのバーテン、タスクはおちゃらけて賑やかに見えて、まいを一途に思っている誠実さもあり、堀広道さんの服部と掛け合い漫才のような言葉のやり取りが絶妙なテンポで面白い。
堀 広道さんの服部が、縦横無尽に馬鹿馬鹿しくも可笑しくて、ちゃらんぽらんに見えて、随所で、店とかえでたちの事を思っている深い表情が印象に残った。
舞台中に、会場の観客も参加する所があり、役者さんと観客が一体になり、会場が
文字通り一体になって楽しかった。
洒落て小粋で、可笑しくて、楽しく艶やかで、キラキラしたエンターティメントなコメディの素敵な舞台だった。
文:麻美 雪

【公演終了】箱の中身2016【感想まとめました】
映像・舞台企画集団ハルベリー
テアトルBONBON(東京都)
2016/04/06 (水) ~ 2016/04/10 (日)公演終了
満足度★★★★★
箱の中に最後に残ったものは
昨日、初夏のような陽気の昼下り、中野のシアターBONBONで、劇団おぼんろのわかばやし めぐみさん演出、ハルベリーオフィス特別公演:「箱の中身2016」を観て来ました。
人は、心の中に開けてはいけない「パンドラの匣」と、開けられたくない「記憶の匣」を頭の中に持っている。
その匣が開けられた時、噛み合ってはならない歯車が噛み合い、回らずとも良かった歯車が動き出す。
舞台の幕が開くと目の前に広がるのは、歯車と振り子のある柱時計の中。
それは、この物語の開けられたくない「記憶の匣」を開けられようとしている、夥しい血痕を残したまま姿を消してしまった妻の行方に大きく関与しているのではと疑われ、精神鑑定を受けている、無口だけれど、悲しいほどに善良で、切ないほどに妻を愛している時計屋の主人の頭の中であり、記憶の箱である。
佐藤正宏さんの時計屋の主人佐藤の妻えみ子に手痛いほどに裏切られても、赦し続け愛し続ける姿が、最初から最後まで、哀しいほどに切なく、その切なさは、物語が進行するほどにしんしんと心に降り積もって来る切なさだ。
さかいかなさんの妻えみ子は、離婚歴があり、子供を産めない自分と結婚してくれた夫に、最初は引け目を感じながらも夫の誠実な温かさに、夫を好きになろうと謙虚であったのに、ある日を境に夫のお金や財物を売ったお金を愛人に貢ぎ、夫を見下し、やりたい放題をする女へと変わって行く、ここだけを切り取ると、「なぜ?」という憤懣やる方ない思いを抱く妻になっている。
が、この後に続くもうひとつの物語を見ると、そこには別れた夫への一途な想いとその夫が、偶然店番をしていた夫の店に訪れ、再開した瞬間に開けてはならない「パンドラの匣」が開いてしまったが故に、夫の財産を別れた夫へ貢ぎ、大量の血痕を残して姿を消す事へと繋がって行く、哀しい一途さが、夫佐藤への仕打ちになって行くことを知ると、妻えみ子の哀しい切なさもまた、胸に痛い。
そして、もう一つ。かつては喝采を浴び今は落ちぶれたボクサーの物語へと流れて行く。
その流れた先は、えみ子の別れた夫であり、愛人であり、今は収監されている大和さんのボクサーの「記憶の匣」とえみ子に再開したことで開けられてしまった「パンドラの匣」をたどって行く物語へと続く。
そのボクサーと同じ房に入って来た、かつてのライバルであり、引退を余儀なくされた最後の対戦相手のさひがしジュンペイさんのボクサー。
落ちぶれたボクサーの中に見える、身を持ち崩していない人の一抹の清潔さと生きる力が時々一粒の砂金のように光っていたさひがしジュンペイさんのボクサーが色っぽく見えた。
終演後、演出のわかばやし めぐみさんとお話しした時、この舞台の作りはやはり、時計屋の主人の頭の中をイメージしたものなのだと感じた。
それはまた、開けてはならない「パンドラの匣」であり、開けられたくない「記憶の匣」でもある。
匣とは、ぴったりと蓋を閉じる箱の意味であり、箱はだけで編んだ隙間のあるもの、蓋のないもの。
開けてはならない「パンドラの匣」が開き、噛み合ってはならない歯車が動き出し、開けられたくない「記憶の匣」に出来た隙間から零れ出てしまった記憶の行き着く果てのどうしようもない切なさと哀しさを描いたのがこの舞台である。
「パンドラの匣」に最後に残ったのが希望ならば、この「箱の中身2016」に最後に残ったのは、哀しみ、怒り、絶望、苦しみ、憎しみ、痛さ、辛さだったのか、それらを纏った一抹の希望だったのだろうか?
願わくは、一抹の希望であって欲しいと思って止まない。心にしみじみと降り積もる哀しい切なさに、涙が零れ落ちた心揺さぶる舞台だった。
文:麻美 雪

泡の恋
Xカンパニー
アサヒ・アートスクエア(東京都)
2015/12/21 (月) ~ 2015/12/27 (日)公演終了
満足度★★★★★
Xカンパニー旗揚げ公演:「泡の恋」
内容は、
近未来の浅草。
日本という国は今は無く、新しい合併国へと変わり、元日本の、現外国の領土となってしまった東京の街ASAKUSA。
そこは3つのグループが街を納める縄張り争いをする、昭和と未来が混在するカオス街になっていた浅草は、人が集まり、懐かしくも新しい街を作るための想いが交錯していた。
日本だった頃から浅草で育った美咲は、賑わう浅草を微笑ましく見つめながらも、変わっていく景色をどこか物憂げに眺めていた、そんな最中、時代は残酷にも人々を翻弄し、想いをねじ伏せて行き、わずかしか残されていない時間を前に、アサヒグループの朝日昌三は、街のため、美咲のため、対立する3つのグループを統合して1つの巨大な祭を打ち上げる決意をするのだが...。
日本人だった人々の、泡のような恋物語というもの。
こう書くと、シリアスな舞台に思えますが、ところがどっこい、大人の玩具箱をひっくり返したような、9割お腹から笑って、1割のしみじみがとっても素敵なバランスで散りばめられた1年を締め括るのに最高の楽しい舞台。
今までに観たことのないような舞台。舞台なのだが、単なる舞台ではない。舞台をポンと飛び越えたような、自由奔放、縦横無尽、てんやわんやで時間も時空も自在に行き来して、芝居、舞台というものの平衡感覚が一瞬失われて、今、自分は何処に居て、何を観ているのか、現実なのかファンタジーなのか、その境界があいまいであやふやになる不思議な感覚へと陥る。
だが、それ故に、気づくと違和感無くすっとファンタジーの中へと入り込み、物影から、覗いているような臨場感がある。
いつもなら、印象に強く残っている役者さんお一人お一人について、書かせていただくのですが、出演されている全ての方が、印象強くて、書ききれないので、舞台を観ての感想のみを綴らせて頂きます。
目まぐるしく駆け巡る舞台、3つのグループが、それぞれ存在感のあるキャラクターと強烈な印象を残しながら、時間と時空を行きつ戻りつ、縦横無尽に、自由奔放に交錯し、繋がり、滑らかに、物凄い熱量とスピードで展開して行くのに、せわしなさは感じず、どこかゆっくりと時が流れ、時が止まり、また動き出す。
笑いながら観て行く内に、「恋の泡」ではなく、「泡の恋」である意味が解って来る。
恋が儚く泡のように消えるのではなく、儚く消えて行く泡のような恋。
それは、昌三と薄野のマドンナ、美咲の病によって失われて行く記憶と命であり、美咲との時間であり、泡のように儚く消え想いであっても、誰かが誰かに恋をしたその時間。
その切なさといとおしさ、仄かに感じる温かさが、胸に沁々と染み透って行く。
「泡の恋」。
それは、淡く儚い初恋のようで、ほろ苦いビールの泡のような恋なのかも知れない。
パチンと弾けて消えてしまう恋。
それは、美咲だけに向けられたものではなく、美咲と昌三が愛した浅草という街への、今ここで生きているということへの恋なのかも知れない。
そのひとつまみの切ないしみじみさが、スパイスとなって、舞台を包む9割お腹から笑える忘年会のような自由奔放な舞台を、泡のように弾けさせつつも、胸にじんわりと沁みて面白い舞台にしていた。
年の瀬にぴったりの笑って、ほろっとして、思いっきり楽しめた、1年を締め括るのに最高に面白い舞台でした。
文:麻美 雪

カナリヤ【追加公演決定!3日19時】
日本のラジオ
新宿眼科画廊(東京都)
2015/05/29 (金) ~ 2015/06/03 (水)公演終了
満足度★★★★★
日本のラジオ:「カナリヤ」
内容は、「このへやで、ずっと好きなことをすればいい。
ぼくと神さまが、きみを一生まもるから」
母の食事に毒を盛り、観察し続けていた少女、医療少年院を出た彼女を迎えたのは
宗教団体「ひかりのて」の幹部となっていた兄、毒と家族と信仰と、地下室の短いお話。」
観始めてすぐ、これは世間を今も騒がせ続けている、松本某のカルト教団を下敷きにして織り上げられた芝居だと気づく。
信仰も宗教も、それぞれ独立していると、最初の成り立った時の思想や信心は、カルトでも危険でも歪んでもいなかったであろうに、信仰と宗教が連み信仰宗教となり、組織が大きく膨れ上がると共に得てして暴走し、危険を孕み、歪み、カルトになって行く傾向にある。
それはいつか、誤った宗教感に陥っていることに気づかずに、自分と相容れないものを排除し、人の命さえ奪うことを躊躇しなくなる怖さをも孕んで行く。
この舞台を観ると、人は如何にしてカルト宗教に嵌まり、呑み込まれて行くのかが、ゾクゾクと膚に這い上る様に解る。
上演時間の前から、舞台の隅で折り紙を折り続ける、田中渚さんの林の妹アンは、心の底に病みを抱えていることを暗示し、芝居が進むに従い、情緒不安定で何も解っていないように見えて、実は一番冷静で的確に、本能でこの「ひかりのて」という信仰宗教団体の危険さ、狂気を解っているのではないかと思った。
奥村拓さんのアンの兄、リュウタは、穏やかな顔の下に、どんな病みを宿していたのだろう。なぜ、あのようなものを製造したのだろう。なぜ、何のために 。その問が今も頭の中をぐるぐる回る。
八木麻衣子さんの広瀬は、同級生であり、教団を共に立ち上げた教祖早川が、当初の思いからかけ離れ、暴走して行くことに愕然とし、やはり同級生であったリュウタも早川の指示で、自分の知らないところで暴走と狂気に巻き込まれて行く姿を見て、自分が信じてきた物に疑問と怖さを孕んだ不安を感じた広瀬として、目の前に佇んでいた。
蓮根わたるさんの井上ヒソカは、じわじわと、心に浸食してくる怖さと不気味さ、それでいながら、妻と共に出て行った娘の事を話す時とアンに対する時だけは、ふと柔らかで温かな笑みを見せる。
教団も教義も井上は、信心しているのではなく、林リュウタその人だけに対する何か、それは恩義なのか、リュウタ自身への言葉にするには難しいある種の心酔、否それとも違う、でも、確かにある思いから人の命を奪うと解ってる素材を調達する。
自分では抱えきれない、傷、トラウマ、痛み、何かを抱え込んでしまった時、そこにカルト宗教団体があり、一見穏やかな仮面をかぶり近づいて来た時、人はあっけなく、狂気だと気づかずに狂気の中へ取り込まれ、呑み込まれて行くのだろうか。あの、ヒットラーのナチスのように......。
全ての役者が役者ではなく、登場人物その人として、目の前に佇み、観ている側は、その場面と場景に迷い込み、佇み、その人の体の中に入り、内側から観ているような気持ちになった。
家族、血の繋がり、生きる、命、清濁、表と裏、何が正しくて、何が間違いなのか、いろんなもの、いろんな感情が、いろんな思いや思考や言葉が、観てからずっと、頭と体を駆け巡っている。
シリアスなアングラではあるけれど、ただ重いだけではなく、随所に笑いも散りばめながら、見終わった後に、ずしんと何かが体の中に響いて来る、短い舞台でありながら、見応えがある素晴らしい舞台でした。
文:麻美 雪

トウキョウの家族
Theatre劇団子
駅前劇場(東京都)
2015/05/20 (水) ~ 2015/05/24 (日)公演終了
満足度★★★★★
「トウキョウの家族」
認知症の母を抱えて、伊豆大島で民宿を営む長女浜子、結婚して大阪に住む三女星子、父が亡くなる原因を作り、長女と感情を掛け違い反目し合い、家を出て音信不通の次女月子。
母がオレオレ詐欺にあったことから、大阪からは、三女星子夫婦が駆けつけ、長らく音信不通だった次女の月子が婚約者らしき男をつれて、ふらりと戻って来たことから、伊豆大島を舞台に繰り広げられる家族の物語。
三姉妹の姿の要素は、それぞれ自分の中にあり、自分と重なり、笑いながらも何度も涙が溢れた素晴らしい舞台。
杏泉しのぶさんの長女浜子の姿は、認知症で日に日に壊れて行く父を抱えて、一番辛かったちょうど一年前の自分の姿そのままで、身につまされ、浜子の叫びは当時私が胸の中で叫び続けた言葉そのもので、浜子の気持ちが手に取るように、皮膚感覚として解り、一番感情移入して観ていた。
兄がいても、常に父の事を頼むと言われるのも、しっかりしてるの、落ち着いているの、強いのと言われ、親戚や友達、先生に言われ続け、常にそう居ることを強いられて来て、「なぜ兄には言わずに、私ばかりに言うの。解放して。」そう思いつづけたのと同じ思いを浜子が吐露し叫ぶのを見た時、「これは私の姿だ、私の物語だ」と堪えきれずに、涙が後から後から頬を伝った。
浜子と同じ位の15歳の時に、心の支えの母が亡くなり、家事をしながら学校に行き、辛くても弱音も吐けず、自分の悲しみの中に閉じ籠り、自分の悲しみしか見えていない父や兄に甘えも頼る事も出来ず、私がしっかりしなければ、この家は暗くなると泣きたくて、叫びたい時も笑って、馬鹿を言っていた姿は、佐佐木萌英さんの長女と次女の軋轢の間で、常に無理しても笑っていようとし続けていた星子と重なった。
何も気づかない振りをして、反目し合う姉たちの間で母を気遣い、せめて自分が笑っていなければ、この家の空気が重くなってしまう、みんなが幸せになる為にと笑いながらも、疲れ逃げ出したい気持ちと闘っていた星子の姿は、15歳からずっと続いていた私の姿でもあった。
大島翠さんは、姉にも家族にも素直に、優しくなりたいのに出来ない、婚約者と偽って連れて来た入れげたホストにDVを受けているのを隠して強がって、助けてと言えない家族に対して不器用月子を描き出す。
その姿は、母が亡くなる一年ほど前から感情を掛け違い、言葉と態度によって傷つけられ続けて拗れた父との確執を如何ともし難く、認知症になって、気に入らないとぶったりけったりするようになった父に、優しく出来なかった、一年前の自分の姿と重なった。
誰の中にも三姉妹の姿と重なる部分があるのではないだろうか。それを目の当たりにして、観ることによって、いろんな感情が蠢き、泣き、そして何かが放たれたように、すっきりしていた。
大高雄一郎さんの月子にDVを働く葛山は、観ていて怖くなるほど、完全に葛山としてそこにいて、迫力があった。
斉藤範子さんの母絹恵は、どんなに呆けても、母としての思いや母性、子供への愛情がふっと戻る瞬間があることを見せてくれる。
それは、きっと男親と違い、臍の緒で杜月十日子供と繋がっているというその絆の強さをも感じさせる。
三姉妹の姿に自分の姿を重ね、三姉妹の姿を通して、「家族とは何か」を、笑って泣いて、深く胸に問われた最高の家族の物語でした。
文:麻美 雪

スパイ大迷惑
ホチキス
劇場MOMO(東京都)
2016/03/17 (木) ~ 2016/03/21 (月)公演終了
満足度★★★★★
ハチャメチャで粋な笑いの詰まったエンターテインメント
このタイトルを見て、懐かしいあの海外テレビドラマのパロディだとわかる方は、5、60代以上の方だろう。
「スパイ大作戦」、1996~1973年にアメリカで放送された人気テレビドラマで、日本でも1967年に放送され人気を博したドラマのタイトルのパロディ。
さすがに、2歳の私にこのドラマを見た記憶はないが、両親は見ていたようで、両親から話を聞いたことがあるのと、この「スパイ大作戦」のテーマソングは今でも、いろいろな番組で使われているので、聞けばこの曲かとわかる方も多いと思う。
さて、舞台の粗筋を説明しようと思っても、これが説明出来ない。
なぜかと言えば、いくつものストーリーが同時に絡み合って、最後の盛り上がりまで一気に怒濤の勢いで、笑いとハチャメチャな展開とテンションとエネルギーで駆け抜け、駆け上がって行くからであり。
そのストーリーがまた、ストーリーがあるようでないようで、説明するのが難しいと言うか、敢えて説明する必要があるのかとも思い、そもそも、説明など必要ないというか、しちゃいけないんじゃないかとさえ思うのだ。
ひたすらに、馬鹿馬鹿しいことを真面目にやっている。その真面目に馬鹿馬鹿しいことをしているのが、最高に面白い。
もう、ひたすらにハチャメチャで、細かく散りばめられた笑いが、老若男女問わず、昭和生まれも、平成生まれも世代や年代、性別も越えて、観に来た全ての人たちが共有出来る笑いに身を委ねられるエンターテインメントに溢れた舞台。
出演された役者さんの全てが、強く印象に残る。
「天満月のネコ」「君の瞳には悠限のファクティス」に出演されていた織田 俊輝さんや「メイツ」に出演されていた立道 梨緒奈さんが出られていて、その時の舞台とはまた、全然印象の違っていて素敵でした。
立道 梨緒奈さんの二階堂 誉が見せる「コマネチ」が、キレがあって、何だかカッコイイ。こんなに男前でカッコイイ「コマネチ」を見たことはなく、それは、変に恥ずかしがらずに、吹っ切って思いっきりやっていたからなのだと思う。
男より男前でありながら、細やかな繊細さと温かさを持って、さらりとした色気もある二階堂 誉は好きなキャラクターだった。
一番驚き、印象に残っているのは、主人公の諜報部員余怒峰 怒(よどみね いかり=松田 将希さん)をサポートする科学者アルフッド九の石倉 来輝さん。
小玉久仁子さんがゲストで出演されたこの日のアフタートークで、米山 和仁さんから石倉さんがまだ18歳と言った途端に、会場から「え~っ!」と驚きの声が上がり、私も同じように驚いた。
それほどに、アルフッド九の石倉 来輝さんは、落ち着いていて大人っぽかったのだ。観ていて、ご本人には申し訳ないのだけれど、30歳前後の方かと思って観ていた。アルフッド九もハチャメチャであるのだが、表情や立ち居振舞いがとても大人っぽく色気があって、とても印象に残った。
全編、エンターテインメントに徹した、ハチャメチャで、粋な笑いがぎゅっと詰まった最高に面白い舞台だった。
文:麻美 雪

世界が止まる時の音
劇団偽物科学
池袋GEKIBA(東京都)
2015/08/08 (土) ~ 2015/08/09 (日)公演終了
満足度★★★★★
「世界が止まる時の音」
昨日、池袋GEKIBAで、松本稽古さんが出演される偽物科学の旗揚げ公演、「世界が止まる時の音」を観て参りました。
「それね、時間停止装置。」そう言って依頼人が残していったのは、1つの部品と見知らぬ言語で書かれた研究ノートと時計の形をした時間停止装置、謎が詰め込まれたアタッシュケース。
その装置を完成させるべく、集められ依頼人添木の邸に残されたのは、プログラマーと天才ハッカー、数学者と翻訳家、料理人と添木の命を受け、彼らの面倒と護衛を受け持つ達人と呼ばれる若い女性。
其々の分野の才能を発揮して1週間で完成した装置は、世界を滅ぼしてしまうほどにとんでもないものだった。
淡々と笑いを含みつつ進んで行く物語は、時間停止装置の完成であっけなく終わって行くように見えたけれど、そこからが、実はこの舞台の見せ場。
静かにゆっくりと人間ドラマが紡がれて行く。
よく、楽しい時間を過ごすした時、とても幸せな時、「このまま時が止まってしまえばいい」と私たちは言うけれど、もしも、本当に時が止まってしまったらどうなのだろう。
果たして、そのままの状態で、時が止まり、全ての物の動きが止まったまま、年も取らず、今から1mmも一歩たりとも動けないまま、生きる時間も人生も止まってしまったら本当に幸せなんだろうか?
時間も命も人生も有限だからこそ、美しくて、いとおしくて、輝いてみえるのではないだろうか。
ましてや、停止させた時間の長い順番から物が消え、地球もこの世界も消えてしまうとしたら。それでも、無限の時を望むのか?時が止まってほしいと思うのか?
自分達が作り上げた装置の重大な欠陥に気づいた時、装置を使って時間を止めなかったプログラマー(進藤恵太さん)と時間を止めてしまったハッカー(橋本沙保里さん)、翻訳家(小川真紀さん)、料理人(松本稽古さん)、 数学者(寺床圭介さん)。
時間を止めてしまった彼らは、地球が消えると同じに、この世界から消え、時間を止めなかった彼は、消えることなく生き残れる可能性がある。
自分達の持てる力を結集し、地球が消えない方法を見つけ、プログラマーに託した彼らは、どうなるのだろうか。
残す者と残される者の想い、そこに描かれる人間ドラマは、美しくて悲しい。
有限の時間、生きること、愛することすこと。それは、限りがあるからこそ美しく、貴重で尊く、いとおしくも悲しく、そして愛すべきものなのだと思う。そんな想いが胸に沸々と沸き上がってきた瞬間に、涙がぽろぽろと溢れて止める術がなくなった。
出演されていた、全ての役者さんが、その人としてすぐ目の前に息づき、存在していた素晴らしさ。
中でも、「美味しいお料理で、癒します。」ふんわりと明るく可愛い、松本稽古さんの初春智子は、この舞台を柔らかく温かく包み込み、出てくる度にほっとする存在でした。
昨日、初日を迎えた舞台、本日の17時の回が千穐楽です。短くも濃い時間の流れる素敵な舞台です。
文:麻美 雪

四月の魚
劇団水中ランナー
ワーサルシアター(東京都)
2016/03/17 (木) ~ 2016/03/21 (月)公演終了
満足度★★★★★
儚くて、優しくて温かい嘘
エイプリルフールは、フランスが発祥の地であり、フランスでエイプリルフールのことを「Poisson d'avril [ポワッソンダヴリル」=「4月の魚 (Poisson d'avril)」と言う。
なぜ「四月の魚」というのか。それは、昔、4月から魚が産卵期に入るため、4月初旬から禁漁になる、漁獲期最終日である4月1日に、魚を釣れずに戻ってきた漁師をからかい、ニシンを川に投げ込み釣らせてあげたのがジョークの始まりだと伝えられている。
その言い伝えが基になり、フランスではエイプリルフールの4月1日に、同僚や友達同士で嘘をつきあったり、いたずらをしあって「Poisson d'avril(四月の魚)」と叫ぶのだという。
この舞台「四月の魚」は、嘘の世界を創り出す作家と嘘の話し。
書けなくなった作家に、有名な作家のゴーストライターの依頼が舞い込み、作家を見守る女性ともう一度作家に書かせようとする編集者に押しきられる形で作家が書き始めた物語は、余命幾ばくもない恋人に見せるため、エイプリルフールに百連発の花火を仲間と共に上げようとする物語。
物語と現実の思い出が交錯しながら進む物語は、やがて、何度も立ち止まろうとする作家の背中を、自らの意思を持ったように動き始めた物語の中の人物たちが押して書き上がる。その書き上がった小説の行き着いた結末は希望か哀しみか...。
私も、物を書く仕事の末席にいるものとして、思うことがある。
それは、物語とは1つの本当を99の嘘で包んで紡ぐ。それが、物語を書くということ。
童話作家になるために、学んだ専門学校の講師も、「100%の嘘で書いたものは物語ではなく、人の心に響かない、1つの本当があれば99の嘘が本当になり、ファンタジーになる」と言い、子供の頃、母が私に言ったのも、「嘘も100回言ったら本当になる。だから、今はそうでなくても、こうなりたいと思う姿、こうしたいと思うことを100回言い続ければ、本当になる。嘘をつくなら人を欺く嘘ではなく、自分も人も幸せになる嘘を吐きなさい。」と言うことだった。
「嘘」というと、負のイメージがある。けれど、時に人を励まし、救い、幸せにする嘘、やさしい嘘もある。それは、ただ、甘いことを言う優しさではなく、嘘を言う側の心が本当に強くないと言えない嘘だからこそ、やさしく温かな嘘になる。
舞台「四月の魚」は、余命幾ばくもない女性とその彼女に、彼女の命を少しでも長く止め、励まそうとするために花火を見せようと奔走する恋人と二人の友人たち、女性の弟と女性と一緒に入院していたことがあるその恋人たちの儚くて、切ないまでに優しくて温かい祈りにも似た嘘の物語。
それぞれに、事情や痛みや苦しさを抱えているのに、一人の人のために、それぞれが一生懸命、嘘を本当にしようと奔走し、必死に優しくて切ない嘘を吐き続け、嘘を本当にしようとする姿が、胸にひしひしと伝わり、深深と胸に沁みて、涙がぼろぼろと頬を伝い、喉を流れ落ち、胸を濡らした。
出演された役者さん、誰一人が欠けても、きっとこの物語は紡げなかったと思う。役としてではなく、その人としてそこに生き、存在していたからこそ、時間も劇場であることも忘れて、その物語の中に身も心も委ね、入り込み、皮膚感覚として感じ体感して、涙が溢れた。
薄青い4月の空に滲む淡い春の陽の光のように、仄かな希望が感じらる素敵な舞台だった。
文:麻美 雪

フランス革命三部作
芸術集団れんこんきすた
シアターノルン(東京都)
2016/07/20 (水) ~ 2016/07/29 (金)公演終了
満足度★★★★★
『フランス三部作 Blanc~空白の抱擁~』
両端をトリコロールに染められた幕を背中に、舞台を跨ぐように据えられたギロチン台。
「最も人道的な処刑装置」として開発され、革命末期に多くの奪ったギロチンによる死刑執行。
マリー・アントワネットも露と消え、革命後期の恐怖政治と化した頃には、政治にも革命にも何の関係もない市民や子供までが、凡そ罪とも言えないような些細な罪で、死刑になりギロチンの露と消えた。
あのギロチンと代々処刑人の職を受け継いできた家に生まれ、革命期にはギロチンの全てを任せられた、死刑執行人「ムッシュー・ド・パリ」と呼ばれた男、サンソン。その命を奪ったギロチン台。
罪人の首を落とし続けたギロチン台と、死刑人サンソンの視点から見た革命と、死刑執行人の苦悩と真実を描いた舞台、『フランス三部作 Blanc~空白の抱擁~』。
『フランス三部作』は、女性革命家の視点から描かれるRouge、貴族令嬢から図らずも身を措くことになった令嬢の視点から描かれる Bleu、そして死刑執行人の視点から描かれるBlancの3つの視点で描かれる舞台。
死刑執行人とギロチンの視点からフランス革命を描いた舞台は、私の観て来た舞台で、私は初めて観た。
ギロチン台は、ギロチンの精と擬人化され、中川朝子さんのギロチン・マダム、濱野和貴さんのギロチン・シトワイヤン、調布大さんのギロチ・ンキュロットのギロチン一家として、観客の前に現れ、当時の情勢や革命の歴史やサンソンの事について、神出鬼没に現れては語る狂言回しの役回り。
ギロチンというと、おぞましく怖いイメージがあるが、このギロチン一家は、シニカルであると同時に何故だかじわじわとした可笑しみがある。
中川朝子さんは、Rouge、Bleu、Blancと3作品通しで全てに出演。Blancに至っては、ChariteチームとこのGenerouxチームの両方にシングル・キャストで出演されている。性別もキャラクターも全く違う役を、1日通して連続で演じるのは相当の体力と精神力が必要な筈だが、ギロチン・マダムを軽やかにコケットにひとつまみの毒と可笑しみを加えたマダムとしてBlancの中で生きていた。
濱野和貴さんのシトワイヤンは、去年此処で観た『リチャードⅢ世』とは、がらりと違い、たっぷりの皮肉と毒に、可笑しさとひとつまみの狂気を感じるシトワイヤン。
調布大さんのキュロットは、冷静にサンソンと革命を観つつも、何処かほのぼのとして、Twitter等でもかわいいという声が上がっていたが、何だかかわいさがあるキュロット。
武田航さんのデムーランは、人々から厭わしく忌まわしい仕事と、謗られ蔑まされ苦悩するサンソンの唯一の理解者で友人であり、革命によって、差別のない平等で自由な国を創ろうと革命に参加し、ロベスピエールと同じように次第に、独裁的になって行き、その事に気づいた時には引き返せない所まで来てしまった者の苦悩と痛みを感じた。
デムーランの妻小松崎めぐみさんのリュシルは、ただ一途に夫を愛し支える純真な姿が可憐で素敵だった。
死刑執行人の家に生まれ、兄と同じ苦しみを抱えて生きてきた加賀喜信さんのマルタンの家業を厭い家を出て、外の世界に行っても、結局は死刑執行人の家に生まれたことがついて回り、普通に暮らすことさえ儘ならない事に憤りと悲しみ、絶望を感じた姿が胸を刺した。
革命の理念に共感し、次々とロベスピエールたちの命により、痛みも疑問も持たずに死刑執行をサンソンに指示し、酷薄に見えた加藤大騎さんのダンヴィルが、自らもギロチンにかかる時に、サムソンに「お前が心配だ」と一瞬見せた人間らしさに、彼もまた、ただ、自由と平等と平和を願った革命に翻弄された一人の悲しい末路を感じた。
石上卓也さんのサンソンは、サンソンの佇まいが痛ましくも美しく、それだけに、厭わしく忌まわしい仕事と、謗られ蔑まされても、その家に生まれれば否応なしに継がなければならない者の悲しみと苦しみと葛藤とジレンマが犇々と伝わり、胸が締め付けられた。
人の手で、人の命を奪うことの葛藤、苦しみと痛み。それを一番感じ、心を苛まれていたのは死刑執行人のサンソンでなはかったのか。
木村美佐さんのサンソンの妻、マリー・
アンヌは、傷つき、悲しみと苦しみに苛まれ、葛藤とジレンマに懊悩するサンソンを静かで深く純粋な愛で包み、そっと見守り、毅然として支える姿に胸が震えて涙が溢れた。
一日通して観た3作品は、何れも素晴らしく、考えさせられることも、感じることも多かった。
『革命』とは、力や武力、弾圧で捩じ伏せるものではなく、今も蔓延る差別や区別を心から無くすこと。心をより愛あるものに変えること。心を変える事なのではないだろうか。
『フランス三部作』は、全て観ることによって、よりその事が強く伝わってくる素晴らしい舞台であり、3作品を通して観られたことを心から良かったと思う。
この舞台を観たことは、私の誇りであり宝物であると言える舞台だった。
文:麻美 雪

SEX
劇団時間制作
サンモールスタジオ(東京都)
2015/12/16 (水) ~ 2015/12/23 (水)公演終了
満足度★★★★★
劇団時間制作第九回公演:「SEX 」Bチーム
体は女性、心が男性の性同一性障害の女性が、男性として愛する男性と、結婚すれば、「女性」、「妻」になれるのではないかと葛藤の末、結婚をしたものの、心は男性、体は女性であることのアンバランスに悩み苦しむ。
嫁ぎ先の銭湯を舞台に繰り広げられる人間関係。深夜の銭湯に通って来る、女性同士の同性愛カップルの苦悩と自らの苦悩を重ね合わせる主人公。
全てを相手に告げることが、相手を信頼していることになるのか?自分の中の秘密は、誰のため?人を愛することは、本当に平等なのか?
多くのものに縛られながらも必死に生きる人々を描いた舞台。
とても難しくデリケートなテーマを、当事者が抱えるであろう苦しみや思い、他人事だと公平になれるのに、身内になると偏見と戸惑いを持つ人、自分が受け入れられないから排除しようとするもの、理解出来ない、気持ち悪いと言葉の刃を向ける人。
その全ての立場、全ての意見と思いを、何の衒いも偏見もなく、きっちり描いていた舞台だから、観ていて嫌な生臭さがなく、すっと胸にテーマが落ちて来る。それは、脚本だけだなく、役者それぞれが、自分の中の感情と向き合って、それぞれの今の思いを真摯にぶつけていたからだろう。
性同一性障害、同性愛と十把一絡げにされるが、心が男性で体が女性、心が女性で体が男性、女性として女性が好き、男性として男性が好き、体は男性だが心は女性として男性が好き、体は女性だが心は男性として男性が好き、その逆もまたしかりと、個人個人によって、様々でとても十把一絡げに出来るものではない。
それだけ、難しくもデリケートなテーマを、恐らく、この世にある思いつく限りの立場の見方でしっかりと描かれているから、違和感も嫌悪感もなく、素直にひとつの愛の物語として、人間の物語として観られた。
それは、役者それぞれが、その人として苦しみ、葛藤し、生きているからに他ならない。
森田このみさんは、性同一性障害の抱えているであろう全ての葛藤と苦しみと悩みを麗美として、目の前で必死で向き合っている姿に胸が詰まった。
他人事だと冷静に、偏見を持たずに接しられるのに、身内になると排除しようとする本能が働いてしまう、奈苗さんの麗美の夫明人の姉の反応は、きっと一番世間で多い反応のひとつだろう。
頭では理解していても、身近な人が性同一性障害や同性愛と知った時、哀しいけれど、冷静に受け入れられるかと問われたら、きっと誰しも「うん」とは、即答出来ないのだろうかと考えさせる存在でもある。
事実を知ってもなお、麗美を受け入れる小川北人さんの夫の明人は、完全に理解し受け入れたとは言えないものを心にまだ残しているものの、麗美がかつて明人に自分の性同一性障害を秘密にしてたように、麗美には、性同一性障害など関係なく男性の麗美を愛していると嘘をつく。
だが、それは綺麗事の嘘ではなく、心底麗美を愛しているが故の嘘。きっと、理解して乗り越えてみせるという自身に対しての近いとしての真実に転化させるための嘘。
永井李奈さんの直美は、同性愛者であることを、理解してもらえないだろうと母に隠し続けている女性。
ずっと隠して生きて行くのは嫌だという肥沼歩美さんの志保と、その考え方の違いですれ違いそうになる葛藤と向き合って行こうとする姿に切なくなった。
肥沼歩美さんの志保の結婚や家族にカミングアウトして、二人の関係を認めて欲しいと主張する志保の、心に抱えた不安と苦しみに心がヒリヒリと痛かった。
倉富尚人さんの明人の従兄弟聖也は、性同一性障害や同性愛に嫌悪感を顕にし、麗美を排除しようとする掻き回す存在。
最初から最後まで嫌な奴なのだが、口には出さないけれど、心の中でそう思っていることであろう世間を表す存在なのだろうなと思う。
その偏見にいつか、自らの足元を掬われるかもしれない、それでもこの人は変わらないんだろうなとも思わせる。それは、世間の認識そのものとも言える。「吐き気がするほどに」とは、真逆の人物。聖也以外の何者でもなかった。
あなただったら?私だったらどうなのか?そんな問いを観ている間ずっと突きつけられていた。
これは、人と人との関わり方、愛というものの本質をも考えずにはいられない、いい舞台だった。
文:麻美 雪

歌舞伎ミュージカル 雲にのった阿国
劇団鳥獣戯画
本多劇場(東京都)
2015/05/06 (水) ~ 2015/05/10 (日)公演終了
満足度★★★★★
「雲にのった阿国」
出雲阿国と言えば、ややこ踊りを基にしてかぶき踊りを創始し、このかぶき踊りが変遷し、今の歌舞伎が出来上がったと言われている、安土桃山時代の女芸能者として知られている。
評判になった阿国歌舞伎をまねて作られた、 おもに京都六条三筋町の遊女が,張見世として四条河原に小屋を掛け興行したので遊女歌舞伎とも呼ばれた女歌舞伎は色っぽいものであり、風紀を乱すと言われ、後に女歌舞伎は禁止され、ならばと前髪姿の美少年だけで作ったのが若衆歌舞伎で、当時若衆と言うとどうしても、男色(陰間、男性同性愛者)を誘発するという事で、これも禁止、 そこから男色を想起させない野郎で行われる野郎歌舞伎が派生し、以来現在まで歌舞伎は、男だけで行われるようにはなった。
因みに、阿国と表記されるようになったのは、阿国が伝説化した17世紀後半以降で、歌舞伎の創始期として語る場合には、お国と表記しなければいけないらしい。しかし、ここでは、広く知られた阿国として敢えて表記する。
その大元の歌舞伎の創始者、出雲阿国が活躍した安土桃山時代は、江戸時代に含まれるので、舞台は江戸。幕末も江戸、江戸にはピストルもブーツも入って来ているし、文化も時代も今よりもグローバルでいろんなものが混沌と入り交じり、ある種何でもありの自由な空気が漂っていた時代というイメージもある。
その何でもありの自由な空気が、鳥獣戯画の舞台、「雲にのった阿国」には溢れていた。
それは、まるで江戸の芝居小屋に紛れ込んで観ているような、これぞエンターテイメントという、江戸のワンダーランド。
石山有里子さんの阿国は、去って行き、また戻って来る者をも受け入れ、天才と言われた阿国の踊りにかける命懸けの情熱と想い、その裏で抱える孤独、それでもなお消えることない踊りへの執着と熱情が胸に迫る。
松本稽古さんの、阿国ライバルお甲は、芯の真の所では、阿国に憧れ尊敬もしているが、阿国だけが持て囃され自分の踊りに自信があるだけに、自分の踊りが評価されず光が当たらない事への不満と怒り故に反発し、阿国を潰そうとするが、それは良く出来た姉に嫉妬し拗ねる妹のそれと似ていることを感じさせると同時に、表情や踊りに色気を感じた。
渡辺健太郎さんの捨丸冒頭の、おかめとひょっとこのお面を付け替えながら踊る時の躍りの所作と動きが美しく、色気があって見惚れた。
渋川チワワさんは、台詞も歌も本当にいい声で、演じた伊達錦之助が殊にかっこよかった。
あぜち守さんの秀次郎は、艶っぽく、袂を別った後も、阿国に惚れているが故に、阿国を潰そうとする捨丸に阿国を守るために、命を賭して対峙した時の姿が男前で素敵だった。
竹内くみこさんのお福は、出て来る度に、明るく楽しく場の空気を変え、和み、好きだなと思う。
Witty Lookのお二人のパフォーマンスは、本当にダイナミックで素晴らしく、会場からも感性とどよめきが起こっていた。
亀田雪人さんの大道芸人のパフォーマンスの身ごなしの軽やかさにため息を吐き、ハイジの声で知られる杉山佳寿子さんのパワフルで一見強欲にもみえるが、気っぷの良さと何処か憎めない堺屋かねと、ちねんまさふみさんの何役もこなす、軽妙洒脱さに笑い、あっという間に終わってしまった出雲阿国。
笑って、驚いて、ドキドキ、わくわくし、ホロリと泣ける、正に江戸の芝居小屋で観ているような最高のエンターテイメントに満ち溢れ、客席からは、嗚咽と歓声と拍手が沸き起こり、おひねりが飛び交う素晴らしい舞台でした。
文:麻美 雪

霓裳羽衣
あやめ十八番
東京芸術劇場 シアターウエスト(東京都)
2016/12/17 (土) ~ 2016/12/21 (水)公演終了
満足度★★★★★
座席1階EX 列5番
老婆(熊野善啓さん)がアシュミタ(水澤賢人さん)が語るこの地に伝わる伝説、色欲の女神ダーキニーの物語から始まる物語はやがて、インドの神々と少女アシュミタに纏わる物語になる。
破壊神シヴァとの不義密通を、正妻パールヴァティーに見咎められ、一辺、四十里の大岩が、塵と化すまで( その時間を“劫”といい、古代インドにおける時間の単位のうち最長のものであり、一劫は、43億2000万年とも言われている。)、百年に一度舞い降りる、天女の羽衣の一撫でが、岩を塵へと変える“一劫”の間、無限に等しい時間の下敷きとなる罰を受けた、色欲の女神ダーキニー。
刑の長さに耐えかねたダーキニーは、人間の少女に大岩を鑿(ノミ)で削るように持ちかけ、それが末代まで続く呪いになろうとは思いもせず、不老不死の命と引き換えに、鑿を手に取った無垢な少女に課せられた呪いの連鎖、インドの神々と少女に纏わる物語が幕を開けた。
『呪いの連鎖と業の物語』観ている間中、そんな言葉が頭に浮かんでいた。
表面に見え業は女の業。けれど、その中に潜むものは、神も人間も関係なく、生と命、愛、富、出世を欲する欲と業と執着、その執着によって引き起こされる負の連鎖。
その連鎖の鎖は、いつしか心を蝕んで、気づいた時には身動きもならず、断ち切る事さえも出来ない程に自身を縛り、連綿と負の連鎖を繋げて行く。それを断ち切るのは、相当に巨大な力と痛みを伴わなければ止めることは出来ない。
良い人でも、理不尽に命を奪われてしまうことを、両親の死を目の当たりにして、知ってしまった無垢な少女ソーマが、不老不死を求めて、ダーキニーの甘言にのって、負の連鎖の緒を結んでしまったソーマ(二瓶拓也さん)の悲しみと痛み、やがて、第二のダーキニーになる予感に胸が軋んだ。
ソーマから娘へ、娘からシュクラ(塩口量平さん)へと受け継がれた連鎖は、聡明なシュクラによって、一瞬断ち切られると思われたが、色欲の女神ダーキニーの毒牙によって、シュクラの體の内にに押された色欲の烙印により、更に受け継がれて行く。
この場面を観た時、20年以上前に観た『ゲットー』という舞台の場面がフラッシュバックした。
ナチスドイツがユダヤ人を集めたゲットーと呼ばれた場所で、ユダヤ人の少女がナチスの男に無体にその清らか躰を奪われる場面で、直接的に見せるのではなく、真っ白な服にそこだけ真っ赤に染まった服を着た少女の姿とシュクラの服の裾から伸びた美しい布が荒々しくはためく、ダーキニーに色欲の烙印を押される場面が重なり、あの時『ゲットー』の少女の噴き上げるような憤りと血を吐くような痛みと、涙さえ渇れるような悲しみが胸に膚に突き刺さったあの感情と感覚が襲って来て、心に焼き付いて離れない。
控えめで野心を持たなかったサントーマ・シー(美斉津恵友さん)が、破壊神シヴァのお褥下がりになった側室たちの姿を見て、生き残る為に、人を貶め、蹴落とす邪な姿へと変わってゆくその心模様に、サントーマ・シーもまた、業に囚われ蝕まれた哀しい女神であり、それはまた、人間の女の業と重なった。
全ての元凶の発端となった、ダーキニー(笹木皓太さん)は、體の底から突き上げ、浸蝕してくる怖さを感じた。
それは、ダーキニーが人間の全ての欲望と業を体現した存在のように感じたからではなかったのか。
神も人間も関係なく、生と命、愛、富、出世を欲する欲と業と執着、その執着によって引き起こされる負の連鎖。
『呪いの連鎖と業の物語』と捉えたことは穿ちすぎだろうか。けれど、私があの日観たあやめ十八番の『霓裳羽衣』は、そのように思えてならなかった。
ダーキニーの『本当の事なんて見えはしない』という言葉と、その直後に放ったシュクラの『本当に大切なことは目に見えない』という言葉に、ふとサンデク・ジュペリの『大切なものは目に見えないんだよ』という言葉を思い出す。
もしも、その大切なこと、本当のことが目に見えていたら、もこんな悲しく痛ましいことは起こらなかったろうとも思う。
これだけ書いても、まだ、感情と感覚と思考が纏まらない。
ただひとつ言えるとしたら、この日味わった鮮烈な衝撃を放つあやめ十八番の『霓裳羽衣』は、ずっと、私の軆と心と記憶にずっと焼き付いて離れない素晴らしい舞台だったということだろう。
文:麻美 雪
