旗森の観てきた!クチコミ一覧

女は泣かない
名取事務所
小劇場B1(東京都)
2021/11/05 (金) ~ 2021/11/14 (日)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
韓国の告発劇だが、韓国の社会事情がよく理解できていないので、隔靴搔痒である。韓国がハイテンション社会とはよく聞かされ、映画で見ることはあるが実際に触れてないのだからよくわからない。問題は家庭内性暴力で、幼児に被害を受け今は被害者の保護のリーダーになっている女性(森尾舞)が、主人公だ。しかし彼女の生活も、家庭関係も一部見せられれるがよくわからない。それを探るひとや支持する人も出てくるがその立場もはっきりしない。国内ではこれで理解できるだろうが、この舞台では思わせぶりな上にテレビドラマの劇伴のような安い音楽がガンガン鳴るので、余計わからない。初日だったせいか、俳優座、文学座系、新国立養成所と手堅い俳優たちが揃っているのに、まだ探りあって、韓国で行くか、日本流にするか、戯曲の線で行くか、決めかねている。主演の森尾舞だけは、その中で毅然と決めていて圧倒的にうまい。彼女はもっと大きな400人規模の舞台が十分支えられる実力者である。かつて演じた俳優座のブレヒトの新鮮な演技などを思い出した。
こういう家庭内でしか描けない暴力や性の問題は既に英米にすぐれた作品が多数ある。そこへ割って入るのは、単に時事性だけでは容易ではない

フタマツヅキ
iaku
シアタートラム(東京都)
2021/10/28 (木) ~ 2021/11/07 (日)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
横山拓也の芝居には、いつも、どこか欠けている家族と、どちらかが相手に過剰な思いを抱
いている男女が登場する。舞台設定もいつも風変りだが、今回は落語家になりそこなった老境を迎えようとしている男(モロ師岡)と妻(清水直子)、その長男(杉田雷麟)の家庭である。Iakuの公演は、いつもは関西のあまり知らない俳優がしっかりと良い芝居を見せてくれるのも楽しみだったが、今回は西日本が多いが全国オールスターである。主演のモロ師岡は千葉八街出身。浅草からの芸人。
いつものように(とスッカリ、東京の客も手の内がお馴染になっている)親子の葛藤が芝居の軸になっているが、これまたいつものように、いかにも昔の新派芝居になりそうなところが新鮮で現代のドラマになっている。
今回は初顔の多いキャスティングが功を奏している。モロ師岡と俳優座の清水直子の夫婦などは絶対によそでは見られない組み合わせだろうし、平塚直隆もザンヨウコ(潰れた演芸場の座主)もよくは知らないが、こういう役には縁が遠かったのではないだろうか。俳優お互いの間にちょっと距離感が見えるのも現代的で、新派芝居になるのを掬っている。
落語家になりそこなってアパートの管理人になっている元・落語家にかつての弟弟子(平塚直隆・話の裏の進行役で地味だがいい)に介護ホームでの落語の仕事を持ってくる。はじめは断っていた男だが、つい、その気になって・・・、というストーリーをフタマツヅキのアパートの部屋を盆の上にのせて,回転させながら見せていく。あの、間仕切りのふすまを開けるところが山場だなぁと観客は期待していて、その通りになるが、そこへ行くまではいつもながらうまい。話の中に「落語の「お初天神」を仕組んだところも巧妙だ、たまたま、小三治が亡くなって、NHKの教育テレビでこの演目を見たのも奇縁だった。
どちらかが相手に過剰な思いを抱いている、という事では、今回は上の世代でも下の世代でも女性の方で、そこは、時代だなぁと思う。前の「the last night recipe」と同じようにそれが男の器量を超えていく。しかし、それは結果論で、はじめは、…と作者は若い時の二人も、現在の長男の相手との関係も描いていく。周到である。
出演者ではやはりベテランで、モロ師岡、清水直子。彼らの若い時を演じた二人(長橋遼也
橋爪未萌里)素直なところで初めて見た杉田雷麟。
盆回しに賭けた舞台美術もうまい。1時間55分。拍手鳴りやまず、無粋な公立劇場の終了のアナウンスにめげずカーテンコール。

ぽに
劇団た組
KAAT神奈川芸術劇場・大スタジオ(神奈川県)
2021/10/28 (木) ~ 2021/11/07 (日)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
現代の市井で使われている言葉が、劇的言語として舞台に登場した。
KAATの大スタジオに円形舞台に組んでいて、中央に砂場のような丸い囲みがあり、向かって上手から太い綱で編んだ粗目の網が天井に向かって伸びている。囲みの中が室内、出口は、網で、外へ出ようとすると網を上下するのに四苦八苦する。現代の独特の内向的なところがこういう風に舞台化されているのもうまい。幕開きで、小道具操作が囲みの中の二つの箱から児童向けのプラスティック玩具をぶちまけて芝居が始まる。
二十代後半、松本穂香と藤原季節の通い同棲中のカップルが、うじうじと日を過ごしている。穂香は育児シッターのアルバイトをしていて小生意気な五歳児を預かっている。二人の話題は海外留学で英語を覚えたいという他愛ない話なのだが、やがてそのとりとめなさがテーマだとわかってくる。今風の会話がちゃんと舞台のセリフになっている。
若者の現代風俗を素材にした舞台ではもうだいぶ前に岡田利規の「三月の五日間」という秀作があったが、こちらはセリフを軸に松本穂香と藤原季節の二人が生き生きと動く。言葉は舞台を制する。ことに松本穂香はテレビでも活躍していると聞くが、舞台でこその魅力がある。
だが、そんな二人は自分が生きることにも、他人へのかかわりにもまるでモラルがない。男女の関係はあるが、人間愛はない。あずけられる子供、預けて良しとする両親、託児サービスの所長、と周囲は広がっていくが、どこも張り付けたような笑顔の裏はモラル欠陥社会である。そこをこの若い作者は実に巧みに展開する。本作の見どころでもある。
そこへ、大地震が起きる。
混乱の中で、預けられた子が行方不明になる。その責任はどうなる。男女がお互いに無責任であったことも、周囲が全く頼れないこともあきらかになってくる。そこへ、行方不明の子どもが帰ってくる。43歳になって、手足は既に黒ずんでいる。これは「ぽに」だ。
突然舞台はファンタジーのような展開になる。育児時間の延長の事務処理というリアルなエピソードからファンタジーへと飛躍するが、テーマは外さない。
とにかく、見せ切ってしまう力量は大したもので、肝心の「ぽに」は結局よくわからないままに大団円になる。なんだか初期の野田秀樹の芝居のようだが全体の印象は全く今の空気だ。それが、コロナの終息が見えてきた今という瞬間と連動しているところがすごい、休憩なしの二時間。
新しい才能が確実な一歩を踏み出している。
苦言を言えば、円形舞台を使うのには今少し細心の注意が必要だ。私の席は左側だったが、俳優を丸く動かすのはうまいのだが背中を向けると折角のセリフに随分聞こえないところがあった。今は場内拡声の技術も進歩しているからマイクやスピーカーを仕込むことはそれほど難しいことではないだろう

いのち知らず
森崎事務所M&Oplays
本多劇場(東京都)
2021/10/22 (金) ~ 2021/11/14 (日)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
岩松了の芝居では、よく変なことが起きる。観客にとってわけの解らないこと、と言ってもいだろうか。それも突然。
それは作者が舞台の上に起きることに、ある視角をつけているからで、普通は満遍なく観客に説明していくところを隠してしまう。だから、ある俳優が(経歴が隠されているために)突然観客に理解できない言動をしたり、とんでもないところから(セットが隠されているために)あらわれたり、ストーリーが飛躍したりする。劇中人物にとっては当然のことだが、見る方はそのたびにおやっ?となる。
その一部隠しの作劇術は三十余年前の初期のご近所三部作や竹中直人の会から冴えていて作者お手のものだ。岩松流不条理劇の核心だが、今回はミステリである。もともと、隠すことで読者を翻弄するのが本領のミステリではどうなるのか。
設定は平易なもので、人里離れた飯場に、かつては同級生だった若い男二人(勝地涼 仲野太賀)がやとわれている。舞台はその飯場宿舎の一杯。先輩(光石研)やさきにここで働いていた兄を探しにやってきた男(新名基浩)に教えられながらの職場だ。しかしその職場で行われている事業がよくわからない、山中にある療養所なのだが、そこで何が行われているか先輩をはじめ、皆言うことが少しづつ違う。経営者の身内らしい本部の人(岩松了)に聞いても判然としない。
死亡した人を蘇生させる、事業だとも聞かされ、兄を求めてやってきた男は、兄がその実験材料になっているのではと疑っている。先輩もその噂は否定しない。次第に疑惑が濃くなっていく…、という展開を、登場人物のキャラクターや小さな日常的な身近なエピソードを混ぜながら膨らませていく。二時間、三度の暗転だけで、かなり速いスピードで休憩なしで畳み込んでいく。俳優は全員よく頑張ってセリフをこなしている。岩松了。この作品を台本だけ渡されて処理できる演出者は…ちょっと思い浮かばない。やはり、作・演出、それに出演もやって終始舞台を完結させたお点前お見事ではあった。だが、latticeさんの「見てきた」ではないがこのお流儀になれていないとつらいことも事実だろう。終演後の通路では「どーなってんの?}という声も聞かれたが、それでも九分の入り。かつて、東京乾電池は岩松作品を上演することで固定客が大幅に減ったがめげなかった。今はもっと楽に勝負できている。
ここから先はネタバレで書くが、これはミステリのパロディがテーマという芝居でもない。コロナ禍が生んだ、現代の情報社会への痛烈なパロディでもあるし、常に不条理が伴う現代の社会劇でもある。

紙屋悦子の青春【9月28日~29日公演中止】
(公財)可児市文化芸術振興財団
吉祥寺シアター(東京都)
2021/10/20 (水) ~ 2021/10/28 (木)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
「切ない」ドラマだ。
自分では動かせない大きな社会の流れ、その中で、何とか自分の立ち位置を見つけて生きていこうと健気に日々を送る人びと、その生活の哀歓に浮かぶ第二次大戦末期の九州の地方都市の小さな青春。
何度見ても、掴まれてしまう芝居だ。ことに今回は、新劇・小劇場から選ばれた実力のある俳優がキャスティングされていて、いままでの小劇場とは違う味わいのある舞台になった。いい舞台で、久しぶりの吉祥寺シアターの老若取り混ぜた満席の客席にもドラマはストレートに届いていた。
戯曲は、初期作品だけにストーリーに流されたような若書きのところも見えるが、終戦末期の絶望的な戦局の中で巡り合う青春のひと時が鮮烈に描かれていて、戦後何作か見た優れた戦争青春ものの映画に匹敵する出来である。その後(06年)映画化されたのもうなずける。
松田正隆がこの戯曲を書いたのはもう三十年も前、1992年、それから今までの歳月も感慨深い。考えて見れば、俳優はもちろん、作者も演出者もこの時代を肌で知っているわけではない。だが、三十年の前の初演の時は、まだこの「青春」を同じように生きた人は多く世間に残っていて、同時代風俗劇としての共感も大きかった。たが、今客席に当時を知るひとの姿はほとんどない。それはこのテキストが古典化したという事でもあろう。
古典となれば、時代を超える新たな責任も負うことになるだろう。
今回の舞台は、よくまとまっているし、主役の悦子を演じた平体まひろは十代後半の青春を見事に演じ切り、五人の出演者もそれぞれよく演じている(。しかし彼らの演技も体型もまぎれもなく現代の色を濃くまとっている。そこを超えろというのは過酷な要求であることは知っている)。演出も的確である。舞台装置(ラストの櫻)も音響(遠い潮騒の音)も絞り切って自然を見せ、聞かせているのも効果を上げている。選曲らしい音楽もいい。
しかし、と一言いいたくなるのは、つまらないことだが、客入れの音楽。あそこで流れるのは主にまだ戦局が逼迫しない前の東京の流行歌である。戦局逼迫が知れ渡っていた昭和二十年春に入ってからの雰囲気ではない。前半の二人の士官が訪ねてくるくだりでは若い客はよく笑っているが、あんなに笑わせては誤解されるのではないかと思った。
事実を追うばかりが能ではないが、古典を扱うときにはそれなりの覚悟がいるとも思った。

野外劇 ロミオとジュリエット イン プレイハウス
東京芸術祭
東京芸術劇場 プレイハウス(東京都)
2021/10/15 (金) ~ 2021/10/17 (日)公演終了
実演鑑賞
もともと劇場の前の広場で上演予定だった野外劇をそのまま大きな東芸のプレイハウスの舞台に組んで上演するというイベント上演である。上演時間2時間で原作を追っているので、舞台を劇場内に移しても、とはいうものの、違和感はぬぐえない。
多分、としか言いようがないが、野外劇でやって入れば、祝祭気分でこのイベントの至らなかった演劇部分、やたらに元気がいいだけが取り柄の出演者たち、意図不明の役と俳優のジェンダー越え、結構複雑な原作のストーリー説明不足、などはかなりカバーできただろう。
観客にも参加感もあっただろうが。プレイハウスのいい椅子に座ってしまえば、愚老などは、肝心のバルコニーの場のあたりで寝落ちしてしまう有様.とてもみてきたといえる状態ではない。

ジュリアス・シーザー
パルコ・プロデュース
PARCO劇場(東京都)
2021/10/10 (日) ~ 2021/10/31 (日)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★★
オール女性キャストと言う大胆で意欲的な「ジュリアス・シーザー」である。今までにない新鮮さで、本年屈指の舞台になっている。シェイクスピアの意図を現代に通じる舞台に形象化した森新太郎(演出)の会心作である。
見る前はこの芝居を女性でやるのは無謀だと思っていた。それが見事にに裏切られた。
主要な登場人物、ジュリアス・シーザー(シルビア・グラブ)もブルータス(吉田羊)も、アントニー(松井玲奈)もキャシアス(松本紀保)もみな、野望と信義の中で権力の座を目指すギラギラした「男」である。それをオール女性キャストでやる。タカラヅカの亜流になるのではないか、今、現実に男が支配している権力構造のドラマが浮いてしまうのではないか、男ならではの情感が表現できるだろうか、そういう低い次元の杞憂を吹き飛ばす快作であった。
なんといっても、この作品をフィメールキャストでやると判断して、それを見事に舞台化した演出が第一の功績だろう。女性がやることによって、ドラマの中身が抽象化されて人間が権力に侵されていくテーマが明確になった。その権力の闘争を裸舞台で俳優の動きでダイナミックに造形していく力量、それに答えた女優たちは必ずしも役にふさわしい人気のトップスターではないが、舞台俳優としての日ごろの評価を十分に発揮している。。
登場人物全員、濃淡のある臙脂色で統一したローマ風衣装は、個々の役柄の説明を拒絶しているが、それがかえって俳優の魅力を引き出し、それぞれの権力に取りつかれていく人間像を引き立てている。中ではやはり主演の吉田羊。預言者の三田和代。人気だけに頼らない的確なキャスティングもいい。シーザーとブルータスの死の場面で流れる観客が全く予想できない優美なピアノ曲。序幕シーザーの凱旋から崩壊まで2時間15分・休憩なしの一気呵成にまとめたテキスト・レジの力も大きい。などなど、様々な仕掛けが相まってこのユニークなジュリアス・シーザーが生まれた。
選挙で権力の交代期にこのドラマを、と言う時宜を見据えたパルコの企画力も大したものだ。しばらく劇場がなかったパルコにはぜひ、興行界がなびいている(新国立劇場までも!!!)タレント興行ではない実のある演劇興行を成功させてもらいたいものだ、とは言っても、この優れた舞台、残念ながら、いかにも芝居好きの大人たちの観客でも、客席は半分しか埋まっていない。当日前売りで安価な切符も出ている。

夏の夜の夢
演劇集団円
吉祥寺シアター(東京都)
2021/10/02 (土) ~ 2021/10/11 (月)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
舞台を二重に組んだグローブ座風の裸舞台の中央の高みに木材の森風のオブジエが立っている。それだけの愛想のない舞台に、二十人余の役者が次々に現れてはセリフを朗唱風に言う。稽古中はコロナ禍だったので、俳優間の距離をとったという。それがリアルではない独特の空間になっている。音楽は笛や小太鼓が入っているが現代音楽で、時に踊りもある。振付も、踊り手もパッとしない。テキストレジと演出は客演出の鈴木勝秀。近頃、現代化やコスチュームプレイ化でサービス過剰の「夏の夜の夢」を見慣れていると、森の中の恋人の取り違えと、町人たちの御前芝居に絞った構成で、祝祭劇らしい喜劇的なシーンの連続で休憩なしの二時間。演出が劇場パンフで正攻法のシェイクスピアと言っているように、この作品は、あまりごてごてと飾らなくても面白いのだと、納得できる舞台だった。
しかし、このように芯だけを上演するならば、俳優には今少し頑張ってもらいたい。かつてはこの劇団のシェイクスピアは安西徹雄訳だったが今回は松岡和子訳。言いやすくなったからか、若い俳優たちはほとんど、セリフを一気に口にするだけで,言葉のニュアンスの表現ができていない。味気ないことおびただしい。この劇団には声優としても高い評価のベテランがいるのだから、もっとキチンと教えたらどうだろう、この際、口移しでもいいと思う。そのうちにうまくなる。
この上演台本だと、音楽と、それに伴う踊りは芝居の雰囲気に大きな影響を及ぼす。音楽の曲は今風との折衷で悪くないと思うが、編曲が雑な感じがする。振付はやはりプロの振付師をスタッフに加えるべきだった。折角の妖精たちがそれらしく見えないではないか。
劇場は満席。コロナ明けの祝祭気分も溢れていて、観客も楽しんでいる。飾らないシェイクスピアの良さを久しぶりに見た。

或る、ノライヌ
KAKUTA
すみだパークシアター倉(東京都)
2021/09/25 (土) ~ 2021/10/05 (火)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
この舞台で、六十五年も前に大学の一般教養の「社会学」で初めて教えられた「社会は基礎集団(肉親の関係)と機能集団(他人の関係)から成る」と言う社会の構造の原則を思い出した。
いま現実社会が、それぞれの集団の規律を失い浮遊していることから、さまざまな問題が起きる。肉親の欠如を社会が埋めきれず、逆もまた機能しない。言わば、人間がどこにも主なき「ノライヌ」になっている。
第三国人が幅を利かせているような都会の街で三人の女が、恋人に裏切られ、捨てられ、肉親を怪しげなカルト集団にもっていかれる。そこからの回復への旅の道のりをロードムービー風に描いている。2時間45分(休憩10分)と長い。
家族はいま、社会はいま。と問うが、あまり教条的に進まない。「横転」や「ひとよ」、「荒れ野」の現代の社会劇(と言うのも古臭いカテゴライズだが)作者としてのこの作者のいいところだ。今の社会に取り残されたような人々や集まりをジャーナリスティックに取り上げているが、舞台には今の風が流れているし、提示されるテーマは根源的だ。
一筋縄ではくくれない発展途上の作者で、今までも自作を再演するたびに(あるいは舞台から映画へとメディアを変える時に)書き直してバージョンアップしている。この作品は自分の主宰する劇団で、自分も気持ちよく舞台に出て、と第一稿風で、まだ、まだるっこいところや説明不足のところも多い。
以下はその感想と言ったところだ。
この作者、いつも舞台を進めていく主人公がなかなか決まらない。一人一人、丁寧に説明していき、その時のエピソードや芝居も悪くはないのだが、それに気を取られていると、それぞれの人物の関係が分かりづらくなる。観客が芝居から外されてしまう。
「ひとよ」の映画版が分かりやすかったように映画ならワンカットの映像で済むところが、芝居はそうはいかない。この作者は映画脚本も書くのだから今後の課題だろう。
もう一つ、「或る、ノライヌ」と言うが、実際に彼女たちの周囲にいるイヌそのものを擬人化して舞台に上げてしまうのはどうだろう。犬の社会の説明もいるわけで、それで随分尺を食って分かりにくくなっている。みんなで、路地で吠えれば、たしかに象徴的だがどんなものか。
舞台からは最近珍しくなった80年代、90年代の小劇場の匂いがする。最近の新しい劇団はちゃっかり、ドラマターグなどを置いて客観的に整理してしまうところを、ここはぐずぐずと引きずっている。それは脚本だけでなく、俳優の演技や、美術や照明にも表れている。その功罪は決められないが、今回はすべてに少しとっ散らかっているように思う。
といろいろ言いたくなるところがこの劇団に良いところで、きっと作者も、第一稿のつもりで気が付いているだろう。観客は付き合うしかない。
さらに余計なことだが、この「倉」(ソウと読むらしい)という劇場、新装なってから始めて行った。もう彼岸過ぎで、このあたり夜はすっかり暗い。とても劇場とは思えないところに入り口がある。元劇場のあったところに表示でもあればわかりやすいのに。

九月大歌舞伎【第二部のみ9月6日(月)まで公演中止】
松竹
歌舞伎座(東京都)
2021/09/02 (木) ~ 2021/09/27 (月)公演終了
実演鑑賞
「四谷怪談」夜6時からの第三部。浪宅の場から隠亡堀まで、休憩20分を入れて2時間10分、超特急の四谷怪談だが(昔、夏芝居で見た四谷怪談はこんな見取りだったと思う)、名優二人の見せ場はちゃんと入っていて、一席置きの客席満席の見物衆はご満足。普段はジャニーズ客には困ったものだ、などと言っているくせに、こういう役者見物はやはり芝居の楽しみの一つだ。
芝居としては説明不足が幾つもあるが、ここのところ、コクーン歌舞伎や木ノ下歌舞伎で、普段はやらない場も見ているのでよくわかる。こんなところにもこの戯曲の現代上演の功徳もあると知った。

物理学者たち
ワタナベエンターテインメント
本多劇場(東京都)
2021/09/19 (日) ~ 2021/09/26 (日)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
舞台が明るくなると、看護婦が殺された病院のサロンの現場検証のストップモーション。
その病院は草刈民代の院長が仕切る精神病院で,そこには、アインシュタイン(中山祐一郎)やニュートン(温水洋一)を名乗る狂人、太古の王の宣言を信じる狂人(入江雅人)が収容されている。彼らは次々と善良な担当看護婦たちを殺していくが狂人とあって、罪には問われず、病院に収容されている。まるで、ミステリ劇のような出だしだが、舞台はそこから二転三転、ミステリ劇はやがて、陰謀劇になり、さらには国際スパイ劇になり、時には社会劇にも喜劇にも変貌する。登場人物は同じながら、ストーリーの進行に従ってさまざまな様式で劇が進む。登場人物たちも時に叡智溢れる物理学者だったり、時には狂人だったり、スパイだったり、忙しい。訳が分からないと、言うことはないのだが、観客がストーリーを追うのも容易ではない。
ヨーロッパのほかの国・ある意味、馴染みのあるロシア、イギリスやフランス、とは全く違った手つきのドイツの舞台劇だ。見ていれば、一つ一つのシーンはその飛び方が面白い、という事はあるのだが、その芯がつかめないもどかしさが残る。
ドイツの現代劇はわが国ではブレヒト以外は、ほとんど系統的に上演されないが、この作者デュレンマットは、ミステリの翻訳もある。戦後まもなく上演された「貴婦人の帰郷」が、数年前クリエでも再演された。ドイツでは大当たりの人気作家の代表作、と言われても、なぜ?、どこが?、当たるのか腑に落ちない。そこが国境を渡る「演劇」の難しさである。
まぁ、蜷川や野田の芝居をアチラへもっていっても、ホントに分かっているのかどうか、もどかしいところがあるから似たようなものか。習うより、慣れろ。とせいぜい見てみるしかない。そのうちに、フッとあ、なるほどと分かるのがこれまた演劇の面白いところなのである。
草刈民代はじめ俳優たちは、ノゾエの多分原作・戯曲に沿った演出でみなこのいそがしい喜劇を熱演しているが、客席の反応はいま一つ。ほぼ、1時間づつの二幕。休憩15分。
。

夏の砂の上
ハツビロコウ
「劇」小劇場(東京都)
2021/09/21 (火) ~ 2021/09/26 (日)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
松田正隆の初期の九州を舞台にした戯曲の中でも、「夏の砂の上」(1998は読売文学賞)は好きな作品だ。ドラマを人間の性がしっかり支えていて、表面は市井劇だが、風俗劇の域を超えている。90年代の代表的な戯曲である。小さな劇団が上演しやすい配役なのでよく、小劇団が上演するが、なかなか、初演を抜けない。
確か、初演は青山円形で平田オリザの演出.意外にオリザ風でなくしっかりと緊迫感のある演出をしていて、何よりも優子を演じたデビューしたばかりの占部房子がよかった。あれから四半世紀!
今回はハツビロコウの公演。客演も加わって、ガラ的言えば無理のない配役だが、初日のせいもあってか、ドラマが浮足立っている。それは仕方がないが、この小さな劇場でセリフが通らないのは困った。それは舞台美術のせいもあって、間口の広い舞台に長方形の大きな和机を中央に横に置き、両端で向き合うセリフが多い。せめて、机を小さく丸くするとか、置き方を考えるかしないとセリフのほとんどが客席に向かわず、壁に向かってしまう。セリフの経験の足りない声の逃がし方を知らない若い俳優は苦しい。優子を演じた金原爽佳は、現代的な体躯で役にはハマっているのだが、セリフが出来ていない。その相手役の小野涼平も柄はいいがセリフが弱い。この二人を取り巻く大人たちは職を失うとか、夫婦関係がこじれるとか、交通事故にあうとか、この一見平穏に見える社会で不安とともに生きざるを得ない人たちで、今のご時世では受け入れられやすいが、この芝居のキモは、それでも、人間は生きていく、と言うところだ。戯曲では情緒的には納得できるように書いてあるのだから、あとはそういう日常性の奥にある生命力の表現が出来るかどうかだ。そこは細かい日常的な表現から、抽象的な表現まで、人間の本音を舞台にあげる技術の修練がいる。そこが流れてしまっている。
さらに言えば、音響効果が雑。例えば、カゲの出入りの玄関の開閉のタイミングがずれる。蝉の声もアブラゼミから法師ゼミに移るという季節の説明だけになっている。折角長崎のはなしなのに、ローカリティが安手な船の汽笛の音だけと言うのはいかがなものか。

近松心中物語【愛知公演中止】
KAAT神奈川芸術劇場
KAAT神奈川芸術劇場・ホール(神奈川県)
2021/09/04 (土) ~ 2021/09/20 (月)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
帝劇で見、明治座で見、新国立劇場で見、今回この芝居を観るのは四度目か。
芝居は今生きている人間がやるものだから、時とともに変わる、その時代にしか生きられない観客の定めも感じる。秋元本は一九七九年初演以来、四十年。さらに原作の近松の「冥途の飛脚」や「跡追心中」にさかのぼれば、三百年。連綿と演じ続けられてきた日本の演劇の世界である。論じれば、切りがない芳醇な世界ではあるが、ここは、今日の「見てきた」観客の感想である。
蜷川演出による東宝の「近松心中物語」は戦後日本演劇史を飾る屈指の作品だった。今回も見ながらいくつものシーンを思い出した。観客の心をつかむ世界が、舞台の上で演じられる。
それが時代を超えて大きくて完成度が高かった。個人の恋愛から、社会のしがらみまで世俗的な世界を題材にしながら、日本人の心情に深く刺さっていく。原作が浄瑠璃という事もあって、歌が効果的に使われている。蜷川が亡くなった後のいのうえひでのり演出は、伝統日本のモダナイズの蜷川をなぞらずに、戯曲を立てた近代劇の愛のドラマにした。こちらも新鮮ないい舞台だった。ともに狙いがはっきりしていて、舞台の立体化が成功した。今の言葉にすれば、「ビジュアル」で成功した。
今回の演出は長塚圭史。今の時代の近松心中物語を、と目ざしたのはわかるが、ここぞ、と言うところがない。
それが影響して配役も落ち着かない。俳優が役の日本人の情感を運んでいない。戯曲は、登場人物の生活背景も書き込んでいて、いずれも商いに精を出さねば食えない二番手の小商売の家に田舎の家から追い出されるように店に入り込んだ男たち、遊郭の顔見世女郎、見栄は張りたいが張り切れない商家の家付き娘、と言うあたりがよく書き込まれているが、今回の上演ではそこがあまり見えない。だから、封印切りに至る経緯もことの流れで・・という風に見えてしまう。人物の性格や、それぞれの劇的対立はよく説明されるが、血が通っていかない。前例を言えば、太地喜和子も宮沢りえも柄として梅川が似合っていたとは言えないだろう。そこを役にしたのは俳優と演出の力だった。田中哲司も笹本玲奈も有力な新人ではあるだろうが、ここはもう一つ、演技に節目をつけて細かく役を膨らませる工夫が欲しかった。松田龍平と石橋静河は、演技も達者だし、役をよく呑み込んでいるが、舞台全体から見ると浮いている。シーンは演じられるのだが、演劇として詰まっていかない。
蜷川もいのうえも大劇場演出にたけていたから、群集シーンで見せ場を作っていたが、それがなかったのも寂しい。
今回の音楽は、日本の囃子をリズムに取ったようなスチャダラパーの曲を使っている。ここで大衆の声を代弁させる意図だったのかもしれないが。大劇場ではパンチが足りなかった。
最も問題なのは美術(石原敬)。奥が狭くなっていく八百屋に組んだ梯形の板の裸舞台に、次々に小道具が持ち込まれて場面を作っていくのだが、様式に統一感がなくちんまりして大きな舞台で映えない。
奥が狭くなっていくのも閉塞感を出す意図かもしれないが、奥の空間も生かされないし、見ているとうっとおしくなる。幕切れ、劇場いっぱいに歌舞伎の紙の雪を降らせた蜷川の大芝居の前例があるからやりにくいのはわかるが、西洋の童話劇のようなきらきら光る雪はないだろう。
日本演劇の粋の詰まった戯曲を、蜷川は歌舞伎で、いのうえは新劇で、長塚は小劇場でその時代に合わせてやってみたという事だろうが、前二者の大成功は重荷だったに違いない、しかしやってみる甲斐はあった。次は本多で,歌舞伎座で歌舞伎役者でと見物の勝手な夢は広がる。それまでこちらが生きているかどうかもわからない。しかし芝居は続く。
二時間二〇分で休憩なし。休憩は入れてもよかったのではないかと思う。客席は懐かしいもの見たさの老人客が多くほぼ満席であった。何かと乗りにくい公演ではあったが自分もまた、一つの歴史のなかに織り込まれた、という、芝居見物ではなかなか味わえない感覚が味わえた舞台でもあった。

ズベズダー荒野より宙へ‐
劇団青年座
シアタートラム(東京都)
2021/09/10 (金) ~ 2021/09/20 (月)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
野木萌葱の作。いつもながら、面白い素材を見つけてくるものだ。
今はなきソ連が、表看板の社会主義の優勢を立証するために対アメリカの宇宙競争にまい進する。1060年前後20年の覇権争いに巻き込まれたロシアの科学者の物語である。
第二次大戦の戦利品として、米ソはドイツから原子物理学者をやロケット技術者をそれぞれに拉致して、平和の宇宙開発と侵略のための長距離弾道弾の開発に拍車をかける。もちろん政府の本音は軍事優先なのだが、宇宙開発の宣伝力は大きいし人類の普遍的な夢もある。
ナチスドイツにも、ソ連にも夢に賭けようという人物は出てくるわけで、ソ連の夢の中軸を担った人物を主人公(横堀悦夫)にしたのは秀逸な着想である。ことにソ連は、(本当の理由は明らかではないが)その人物をの正体をを明らかにしなかったために様々な憶測を呼んだ。
青年座公演では「プラウダ」(今は注がないとわからない人も多いだろう。「真実」と言う意味のロシア語で、共産党の党機関紙の名前。いまの北朝鮮の「労働新聞」のソ連版である)という席置きのパンフレットを用意していて、米ソ冷戦のよくわかる年表がついている。その時代を大人として生きた者には懐かしい事件の数々である。
こうしてみると、国民こぞって。未来に熱狂した時代でもあったなぁ、と妙な感慨にとらわれる。作者の野木も知らない時代のはずなのに、その時代の雰囲気が感じられるところはうまいものだ。そのなかで、夢(宇宙開発)と現実(兵器開発)にゆれる研究者たち、と言うのはなかなかドラマチックな題材で、科学者のドラマにはよく置かれるテーマでもある。
米ソ冷戦の行方には世界の破滅か?と言う命題もかかっていた。
大仕掛けな話だけに時代背景と事実の説明シーンはかなり多く、数えれば百くらいはあるのではないかと思うが、状況説明を面白く見せる。フルシチョフ(平尾仁)の出し方などうまいものだ。劇中衛星が何度か発射されるシーンがあるが、音響効果もよく、違和感がない。
演出のテンポもいい。
この公演の成功の要因の一つは舞台美術(安部一郎)だ。円の回廊を三段、傾斜をつけてらせん状に組み、中央に机を二つ、その上の電話機が数台。その上に半円の楕円の作りモノが二つ、まるで衛星の軌道を示すようにかかっている。シュールだが使いやすい。
芝居は面白くできていて一幕70分、休憩15分、二幕95分、三時間を見せ切ってしまうが、見終わると、米ソの宇宙競争の話に呑まれて肝心の人間ドラマは少し薄手になっていたのではと思う。折角登場させているドイツから連行されてソ連での研究に殉じてしまうドイツ人科学者(須田祐介)とソ連科学者のドラマや、研究所の中の科学者たちの「社会主義」と「科学」の葛藤のドラマなど、今のドラマとして面白くなるおいしいところが、話の大きさで飛んでしまったように感じる。野木萌葱らしい面白さはそこにあるのに、と見る観客もいるだろう。
たまたま今、ソ連の研究所を舞台にした長編(十時間)の映画が公開されている。第一部しか見ていないが、当事国にとってもこれは取り上げるべき素材のようだ。

悪魔をやっつけろ~COVIDモノローグ~
燐光群
座・高円寺2(東京都)
2021/09/13 (月) ~ 2021/09/14 (火)公演終了
実演鑑賞
イギリスの代表的劇作家・デヴィッド・ヘアのコロナ罹病記。体験をモノローグとして書いているのを、同じ劇作家の坂手洋二がリーディングに近い形で読む。
体験記だが、劇作家だけあって、罹病の経緯など生々しく実感でき、さらにこの病(悪魔)に打ち勝つための周囲の人間の取り組みまで冷静に見ているところがいい。政治家(保守系首相ジョンソン)に辛らつだが、それも客観性を失っていない。
ロンドンでは、昨年の秋このモノローグドラマを九百人規模の劇場を三分の一の席にして上演。今もレパートリーにしているとウイキには出ているから、ロングランになっているらしい。ヘアは俳優もやるいわば演劇界有名人だが、本人がやっているわけではない。知名度のある俳優が演じ演出家もついている。
こちらは坂手洋二の演出,出演。坂手もたまには芝居にも出ている。小劇場での実績も承知しているからリアリティはある。しかし、日本の劇作家でも、もしくは俳優でも、一人くらいはこう舞台でこういう手の実感モノローグを聞かせてくれてもいいのではないか(。かって、谷賢一の同工異曲を見て相当がっかりしたことがある)。社会の、差別と偏見へのモノ言わぬ深さがやはりこの国は深いと実感させる公演だった。55分。

友達
シス・カンパニー
新国立劇場 小劇場 THE PIT(東京都)
2021/09/03 (金) ~ 2021/09/26 (日)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
久しぶりに観客がワクワクする演劇界の対決上演である。
この一月の間に安部公房の代表作、「砂の女」と「友達」の意欲的な再演を見ることができた。「砂の女」(1962)は今や、日本演劇界の顔となったケラリーノ・サンドロヴィッチの台本・演出。片や「友達」(1967)の台本・演出は弱冠まだ二十代の俊英・加藤拓也。この公演のネット動画広告では、出てもいない人気俳優が次々に登場して、稽古場で「友達!」と叫ぶ。フェイスブックをもじった駄洒落だ。出演者の自己紹介の最後には童顔の加藤拓也が登場して「加藤拓也でーす、演出やりまーす」という。30年前のケラならやりそうな秀逸なプロモーション(CMグランプリ!!)で舞台への期待も高まる。シスカンパニーの制作。劇場は新国立のピット。トラムに負けない満席である。
結果は、随分肌合いの違う安部公房が出来上がったが、演出者がそれぞれの視点から原作を現代に引き寄せた再演にしていて、ともに当年屈指の舞台になった。大家に挑んだ加藤拓也も負けていない。
甲乙つけるのは野暮と言うものだから、感想を列記する。
安部公房と言う作家について。現代社会の不条理を抽象的に把握していく戦後作家の世界が、今や、現実化してしまったことが、今回の新しい上演でよくわかった。これで、安部公房は現代に生命をもって再臨することになった.もちろん、砂の女の家も、闖入してくる家族も、抽象的な存在ではあるが、観客は現実社会と同じ水平でみて共感している。安部公房は、古典の位置を確かにしたとでもいおうか。
「友達」の上演台本は、スマホも登場するし、生活環境も現代にしているが全く違和感がない。その点では、慎重に昭和三十年代の時代設定にこだわったケラの「砂の女」よりも軽やかに現代のドラマになっている。「民主主義」の空洞化は書かれた時代よりも進んでいるのでリアリティもある。
「砂の女」の上演時間はほぼ3時間。映画よりも長い。「友達」はもともと二幕13場の舞台を数回の暗転で休憩なしの1時間半にまとめている。テンポも速い。時代に合わせたアダプテーションが成功している。(勝手な感想になるが)しかし、この台本だと、原作のラストを踏襲していいのだろうか。それはケラの時にも感じたが、その辺に安部公房の時代性があるのかもしれない。
演出。この演出家は若いのにステージングがやたらにうまい!平面の板の中央に上下に出入りを作って効果的に使うのは以前も見た記憶があるが、この舞台でも孤独でガランとした主人公(鈴木浩介)の部屋に闖入者が地面から湧き出すように板の中央に作られたドアからドカドカと現れる。ここで芝居の構造がはっきりわかる。ほとんどの時間舞台の上には十人の登場人物がいる。一人一人芝居がついていてその集団が息をするように膨らんだり、締まったりする。セリフのあるところはほぼ、舞台中央で処理される。舞台演出の基本と言えば基本なのだが、このリズム感がいい。
俳優。キャステキングがうまい。家族の山崎一(父)キムラ緑子(母)男女三人づつの兄弟姉妹たちもバランスがいい。客寄せも考えて(有村架純(次女)あるし、浅野和之(祖母)鷲尾真知子(管理人)大窪人衛(三男)の、普段は飛び道具の人たちもうまくはまっている。もっと面白くなりそうなのは、西尾まり(婚約者)内藤裕志(弁護士)。皆好演である。
スタッフでは美術(伊藤雅子)。後半、遠見に街のシルエットが出てくるが、これが観客を和ませる。この奇妙な寓話劇に巧みに情感を残している。音響効果は電子音のノイズを軸として、ここは、昔の阿部公房風だ。
この新国立の劇場へ来たから言うのではないが、こういう演劇界の刺激になる企画は新国立劇場が試みるべきではないか。普段、この劇場で見る日本の演劇は毒にも薬にもならないものがほとんどで、意味のある企画は、ここのところほとんどシスカンパニーの手で行われている。今の時代に「友達」を上演するという企画力、加藤拓也と言う若い演出者を起用して、地方も含めて長期の公演を成功させる(前売りは完売していた)興行力、演劇界を知り尽くした広範な分野からの的確な配役力、スタフィング。どれをとっても、この芝居をどう作るかと言う意図がはっきりわかる。流行の言葉で言えば「説明責任を果たしている」。そこが素晴らしい。
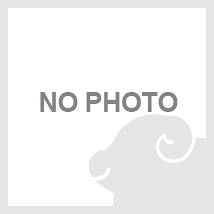
音楽朗読劇「シャーロック・ホームズ#1」
ノサカラボ
サントリーホール ブルーローズ(小ホール)(東京都)
2021/08/28 (土) ~ 2021/08/29 (日)公演終了
実演鑑賞
古典の活かし方もいろいろあって、古典ミステリの人気キャラクターは、最近流行の2・5ディメンション系の舞台では重用される。8月には最強キャラのホームズにタカラヅカ宙組と、この舞台が用意された。こちらは音楽朗読劇と銘打って、名作ミステリを次々と舞台に上げようという企画の第一弾。劇場もサントリーホールのブルーローズと小洒落ている。
俳優に人気の声優を配し、劇伴を生演奏で、朗読劇として上演する。内容は初期の「冒険」から三話。入り口ではイギリス公認の輸入グッズも販売している。客は日ごろ顔を出さない建前の声優の演技が見られるというのでファンが多い。これが、ミステリの中身で客が来るようになれば、新しい展開があるのかもしれないが、時代をくだるにつれて、ホームズ=ワトソンのような朗読劇には使いやすい人物関係が少なくなる。仕掛けも複雑になってこういうリサイタル形式ではできなくなるだろう。
宝塚宙組はコロナ拡大でかなり公演中止することになった。こちらは前途多難である。

『砂の女』
キューブ
シアタートラム(東京都)
2021/08/22 (日) ~ 2021/09/05 (日)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
かって親しんだ世界をいま、目前に見て、それに勝る興奮を感じられるか、そこが、古典を再演する肝だろう。「砂の女」(1962)は日本の戦後文学の里程標となった作品、作者自身の脚本による映画(1964・勅使河原宏監督)もまた、世界的な評価を得た。その後、芝居にもなったようだが、草月ホールで見たような、見なかったような。それから六十年。
今回はケラリーノサンドロヴィッチによる舞台化である。
『鳥のように、飛び立ちたいと願う自由もあれば、巣ごもって、誰からも邪魔されまいと願う自由もある。飛砂におそわれ、埋もれていく、ある貧しい海辺の村にとらえられた一人の男が、村の女と、砂掻きの仕事から、いかにして脱出をなしえたか――色も、匂いもない、砂との闘いを通じて、その二つの自由の関係を追求してみたのが、この作品である。砂を舐めてみなければ、おそらく希望の味も分るまい。』というのは安部公房自身の言葉だ。このシンプルな構造の中で、作者は戦後日本の課題を二人の男女に託して描いたわけだが、それを世紀を超えた今、舞台で見るとどうか。
コロナ禍で、全国に「非常事態」が拡がろうかという酷暑のなかのでトラムの公演は、観客の肌にも砂がこびりついてくるような迫力のある舞台だった。古典を今に生かしたケラの力量は大したものだ。それは、丁寧に追われる原作のストーリーの功績よりも、脚本・演出家の舞台あらではの工夫がこの成功につながっている。この欄で言えば、筋は原作で周知なのだから、いまさら「ネタばれ」でもあるまい。舞台に積み上げられたその細かい演劇ならではのネタが見事な舞台だった。
観客は老若男女取り混ぜた芝居好きで満席だった。舞台の上も下も芝居好きが集まった一夜の愉しみがここにあった。コロナの憂さも晴れようというものである。..少し長くて十五分の休憩をはさんで二時間五十分。..

4
ティーファクトリー
あうるすぽっと(東京都)
2021/08/18 (水) ~ 2021/08/24 (火)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
何もない舞台にホリゾントが立てられていてそこにマッピングで様々の模様が現れる。そこへ机やいすをもって次々に男たちが現れる。彼らは、そこで、客観も主観も交えて、死の前の人間をみようというのだ。
死の前の状況を人工的に作り出すには死刑執行と言う格好のが素材がある。その死にかかわる人たちと言えば、死刑を命じる法務大臣、判決に関わる裁判員、裁判官、具体的には死刑執行人の首に縄をかける役をつとめる刑務官。刑を受ける無差別殺人を行った罪人、その父親、などの役割を五人の俳優がそれぞれの人物となって、死刑を行う経緯とそれにかかわる人間の心境を語る。ドラマがかみ合う場面は少なく、証言ドラマのような形だが、どうやらこれは結論を求めてまとめようというわけでもない。話の流れが死から離れそうになると、男たちの一人司会者(今井朋彦)役の手でもとへ、戻されたりする。
こう書くと、なんだか、取り留めなさそうなのだが、これが結構緊張感をもって2時間10分の舞台になっている。
それは一つには、死は人間誰も避けられないが日常はあまり見ようとしないで過ごしている大きなテーマだという事もあるが、このコロナ禍で突然その死が身近になったという事があるかもしれない。舞台としてはあまりなじみのない形式なのだがバラバラの人物や場をつなげる作劇術もうまい。話題も、死刑反対派の議員が大臣の職につくと刑を実行せざるを得なくなるとか、死刑囚を前にした刑務官の精神的圧迫とか、シーンとしての若干の説明もあるが、独白の方が物語のテンポも速く舞台の引き寄せられる。極め付きは死刑執行時に誤って失敗する執行官のエピソードで、このことで刑務官は神経を病み離職する。
だが、俳優たちはそれぞれの役から発言するが、それがどこへ向かうかはわからない。死の実態は経験できないのだから、そこまで、と言う感じ。そのさまざまな距離感を、ロールプレイイングゲームのように描いて見せた死をめぐるアラベスクと言った感じのユニークな舞台で、作者は十年前のワークショップからリーディングや上演を重ねて今回作者自身の演出による上演となった由。そういう練り上げられた、と言う感じはよく出ている。いつもながら小劇場にしては洒落た舞台づくりに、小劇場のベテランの俳優たちに素敵な新人(池岡亮介)が加わったを俳優陣もよく演じ切って小劇場ならではのいい舞台になった。

ジェイミー
ホリプロ
東京建物 Brillia HALL(東京都)
2021/08/08 (日) ~ 2021/08/29 (日)公演終了
実演鑑賞
満足度★★★★
17年初演のロンドン ウエスと・エンド ミュージカル。イギリスモノだけあって、16歳のゲイの男の子ジェイミー(私が見たのは高橋楓の回)が根強く残っている家族、学校、社会のゲイ差別の中でドラッグ・クイーンを目指すというサクセスストーリだ。
もともとは、テレビのドキュメンタリーから発想された作品という事で「社会派」である。ミュージカルには古くは「マイフェアレディ」の階級、言語差別、「ウエストサイド」や最近の「インザハイツ」に至る移民差別、など差別をテーマにした名作があるが、これは性差別がテーマである。イギリスは同性愛を犯罪としていた時期もあって、それだけに社会の中にある種の緊張感がある。それがこの本来は無邪気な若者の成功物語にも影を落としていて、このミュージカルはよく考えられている本なのだが弾まない。
物語は、義務教育終了まじかの教室から始まる。これから社会へ出て行って何者になるか、と言うだれしも経験する期待と不安の門出である。
ゲイの主人公は、母(安蘭けい)には理解されているが父(今井清隆)はきもいと言って家を出てしまった。居場所はそんな母子家庭とかつてのドラッグクイーン(石川禅・この俳優はホントに日本のミュージカルには欠かせない名脇役だと思う)が営んでいる貸衣装やである。卒業前のイベントが迫っていて、そこで主人公は女装を見せようとするが、それをめぐって家を出た父親との葛藤、イスラムのヒジャブを被った恋人(山口乃々華)、ゲイを理解しない男友達、理解はするが解決しようとしない教師(樋口麻美)などの学校でのドラマが展開する。
日本でも様々な場でジェンダーの問題が表面化してきた昨今、時期を得た企画にもとれるが、やはり、イギリスとは社会環境が違う。切実さが伝わってこない。ストーリーは平凡な進行だが、曲に終演後も残るような名曲がない。ダンスにも際立ったナンバーがない。一つには時節柄、イギリス人の演出家を起用しているがリモート演出だという事も影響しているのかもしれない。言葉は悪いがずるずると締まりがない。
俳優で言えば、私も見た若いカップルは残念ながら力不足。特にまずいという事はないのだがドラッグクイーンと言い、イスラムの美女と言うならやはり、ハッとするよううな地の魅力が欲しい。今回は脇に支えられたと言う感じだ。
一幕・1時間20分、15分の休憩をはさんで二幕1時間15分。
