kikiの観てきた!クチコミ一覧

オペラ『イワンのばか』
オペラシアターこんにゃく座
あうるすぽっと(東京都)
2020/02/06 (木) ~ 2020/02/11 (火)公演終了
満足度★★★★
トルストイの『イワンのばか』を基にしつつ、こんにゃく座らしい仕掛けのある新作オペラ。
軍人のセミョーン、たいこ腹のタラス、イワン、口のきけない妹マラーニャの4人の兄妹、そして大悪魔と三匹の小悪魔の話だ。
このオペラでは、トルストイが農民学校で自作の『イワンのばか』を生徒らとともに読み進めていく形で物語が進む。生徒たちが入れ替わり立ち替わり物語の登場人物を演じたりもする、入子構造の物語がいかにもこんにゃく座らしい。
後半は、同じトルストイの『イワン・イリイチの死』の主人公が登場し、トルストイを取り締まろうとしたりもする。
大悪魔を演じる大石さんがイワン・イリイチを演じる。神の名を聞いて消える悪魔が残した穴と、病床で死を迎える人間の葛藤が重なる。
トルストイと、2人のイワン。ここにしかない物語。ここにしかないオペラ。
生演奏と人々の歌声の余韻に包まれて会場をあとにした。

末摘花
オペラシアターこんにゃく座
俳優座劇場(東京都)
2020/09/08 (火) ~ 2020/09/13 (日)公演終了
満足度★★★★
この作品の原作は榊原政常氏の『しんしゃく源氏物語』。もともとは高校演劇のための戯曲だったらしい。
作曲は作曲家でありピアニストでもある寺嶋陸也さん。演出はこんにゃく座の大石哲史さん。
脚色や作詞はクレジットなし。その理由は見始めてすぐ気がつく。たぶんこれ、元の戯曲の台詞をそのままメロディに乗せてるんだ。
作曲の寺嶋さんがご自身でピアノの生演奏をなさっていて、観客にとってゼイタクなことである。
舞い散る雪や枯れ葉や花びらが季節の移ろいを示す中、女たちは夢と諦めの間でその人の訪れを待つ。
信じても諦めても、結局は朽ちていく屋敷の中でただ待ち続けることができるだけだ。
由緒正しい血筋の姫はおっとりとした人柄で、個性的な長い鼻の先はちょっと赤い。世慣れていないため人付き合いも不器用で、ただひたすらにあの方のことを信じて待ち続ける。しかしその方は遠方に追いやられ、姫の屋敷は寂れるばかり。わずかな使用人もしだいに逃げだしていく。
女性ばかり7名のキャストはそれぞれ個性的で、きれいごとばかりではない女たちの本音をにじませていく。
歌い上げられるセリフは時に辛辣であったり、俗っぽかったりもして、思わずニヤッとしてしまう。
ハッピーエンドに見える結末も、結局は待つことしかできなかった姫のセリフにほろ苦さを含ませて、面白くてやがて哀しき……という物語。
休憩を挟んで約2時間20分。休憩後の屋敷の寂れた様子と藤の花が印象的だった。
キャストはそれぞれはまり役で、物語に生き生きと生命を吹き込んだ。ダブルキャストなのに都合で一方しか拝見できなかったのが残念に思えた。
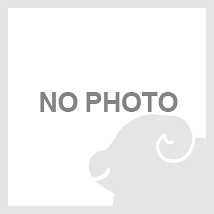
もうラブソングは歌えない
TBS
東京国際フォーラム ホールC(東京都)
2020/08/08 (土) ~ 2020/08/10 (月)公演終了
満足度★★★
『カラマツのように君を愛す』
不器用で誠実な2人のナイーヴな魂の遍歴を、天窓越しに月が見守る。
女の独白と男の日記。語られる声は柔らかく、物語は静かに進んでいく。
絵本に登場する少年。ツキノウラへ行って一緒に暮らす2人。小さなベーカリーカフェ。
雪深い土地で、小さな店を訪れる人々との出会い。
背後に映し出される窓と月のシルエット。丁寧に丁寧に紡がれていく言葉。
朗読劇といいながら振付もついて、重ねていく時間や2人の距離感なども感じさせる作品となっていた。
『大山夫妻のこと』
テンポの良い会話が続く、ちょっと辛辣でほろ苦い、でもどこか可愛いオトナのコメディ。
脚本家と売れない女優の夫婦。妻がある戯曲賞を受賞して、2人の関係が少し変わっていく。
気づいたきっかけは夫からのある誘い。素気無く断り続けるうちに、妻は自らの心に気がついていく。
一緒に暮らしていても、互いのことを大切にするって本当難しいよね。
キャストお2人の雰囲気がいい感じにゆるくて、情けなさも身勝手さも少しだけチャーミングに感じられた。

鶴かもしれない2020
EPOCH MAN〈エポックマン〉
駅前劇場(東京都)
2020/01/09 (木) ~ 2020/01/13 (月)公演終了
満足度★★★★
おとぎ話をベースにした恋物語を三台のラジカセと共に演じるひとり芝居で、再々演とのことだけれど、自分としては初めて拝見した。
二面舞台とアシンメトリーな髪型で男女を演じ分ける瞬発力。張り詰めた緊張感と楽しさ。恋することの煌めきと切なさ。喜びも哀しみも溢れ出すような生き生きとした表情。
作・演出・美術・出演とひとりで何役もこなすそのエネルギーの多才さとそれぞれのクォリティ、そして何よりそのチャーミングさに魅了された。

ミュージカル「空! 空!! 空!!!」【4月11日〜6月5日 公演中止】
わらび座
わらび劇場(秋田県)
2020/06/06 (土) ~ 2021/01/03 (日)公演終了
満足度★★★★★
鑑賞日2020/07/25 (土) 10:30
女性飛行士の草分けとなった及位ヤエの若き日の情熱と奮闘を描いた約110分のミュージカル。主人公を演じる川井田さんの熱量が、さまざまな困難に体当たりでぶつかっていくヤエの姿に重なる。架空の人物と思われる航平の個性的な人物像が物語にメリハリを加えた。脇を固めるベテランの説得力、多くの役を演じ分ける若手の存在感、希望を感じさせる美しい美術や工夫を凝らされた小道具、場面を成立させる照明や音響、困難な状況下で公演を支える劇場スタッフ。それぞれのご尽力で創り上げられた夢を追う人の物語が胸に沁みた。

松浦武四郎~カイ・大地との約束
わらび座
東ソーアリーナ&遅筆堂文庫(山形県)
2020/08/22 (土) ~ 2020/08/22 (土)公演終了
満足度★★★★★
蝦夷地を旅して多くの記録を残し「北海道」の名付け親となった幕末の探検家 松浦武四郎を描いたミュージカル。少人数のキャストで武四郎の見たアイヌと和人の関係や課題を多くのエピソードで綴っていく。自らの無力さを感じながらも書き続けた武四郎の情熱と誠意が胸を打った。

10knocks~その扉を叩き続けろ~
劇団扉座
紀伊國屋ホール(東京都)
2020/12/05 (土) ~ 2020/12/13 (日)公演終了
満足度★★★★★
10作品日替りリーディングのうち4作品を拝見。毎日が初日で千秋楽。公演が始まってから、ようやくこれがどんなに大変なことかわかったような気がした。単に台本を持ち替えれば済むという内容じゃない。朗読という枠組に留まらない多彩な演出で、劇団員やゆかりのゲストが入れ替り立ち替り濃密な芝居を繰り広げる。ことに脚本の良さが際立ち、物語の面白さを存分に味わえた。

リボンの騎士2020~県立鷲尾高校演劇部奮闘記~ ベテラン版 with コロナ トライアル
劇団扉座
すみだパークシアター倉(東京都)
2020/10/10 (土) ~ 2020/10/18 (日)公演終了
満足度★★★★★
鑑賞日2020/10/11 (日) 14:00
泣いた。もう何度も観て展開も台詞もほとんど覚えているのに。今回の上演は、青春への応援歌というより何かを創ろうとする人すべてへのエールのように感じられた。
ダブルキャストによる演出の変化なども面白かったが、何よりけだまや中島をはじめとするキャスト陣の演技が生き生きと魅力的で、物語の持つチカラを再確認させてくれた。楽しかった。

ジパング青春記 ー慶長遣欧使節団出帆ー
わらび座
男鹿市民文化会館(秋田県)
2020/09/27 (日) ~ 2020/09/27 (日)公演終了
満足度★★★★★
伊達政宗の黒船建造は慶長の大地震からの復興施策だったのではないか、という説をベースに、家族を失った若者の魂の再生を描くミュージカル。
何度も観ている作品なのに、人々の想いがこれまで以上にくっきりと立ち上がり、場面場面で涙腺を刺激した。ことに強い感情を歌で表現する部分で、音楽の持つエネルギーを感じた。
多くの情報と出来事をテンポよく配し、物語としての完成度とメッセージ性が同居する魅力的な戯曲、キャラクターの魅力と印象的な数々のセリフ、楽曲のクォリティ、劇団が得意とする民謡民舞の活用、そして、それらを活かすキャストとスタッフの力。遠征した甲斐のある舞台であった。

LOVELOVELOVE23
劇団扉座
すみだパークスタジオ倉(そう) | THEATER-SO(東京都)
2020/02/09 (日) ~ 2020/02/16 (日)公演終了
満足度★★★★★
鑑賞日2020/02/15 (土) 18:00
扉座研究所の卒業公演という位置づけで例年上演されている『LOVE LOVE LOVE』。研究生による実話を交えた短編をロミジュリの名場面でつなぐ構成は例年通り。演技だけでなく歌でも踊りでもアクションでも楽器でも持てる武器はすべて投入して生み出す渾身の作品を今年も目撃できた。
熱量だけでなく構成やテンポのよさも含めて2時間40分の長さを感じさせない舞台だった。ロミジュリは決闘の場面の迫力と、ひばりの声で朝を迎える場面での人を殺してしまったロミオの動揺からの2人のやりとりが切実で心惹かれた。

楽屋 —流れ去るものはやがてなつかしきー
ことのはbox
シアター風姿花伝(東京都)
2020/08/22 (土) ~ 2020/08/30 (日)公演終了
満足度★★★★★
鑑賞日2020/08/29 (土) 17:00
岡崎さん演出版を拝見した。
箕輪さんは、ニーナの台詞の若い娘らしい真摯な声色から、場数を踏んだある種の余裕とその一方で多忙や年齢による余裕のなさとが同居する生々しい女優Cであった。
女優Cのプロンプターだった女優Dは、自分がニーナ役に選ばれた、という妄想を抱いている。「この前電話で作者と話した」などと口にする精神状態のあやうさと、そこまで追い詰められほどの役への思い入れ。女優Cとのやり取りは観ているこちらまでハラハラした。
そして、女優Aと女優B。あらためて観ると最初から最後まで出ずっぱりで台詞も膨大な、見せ場の多い役だ。それぞれの時代感。報われなかった過去への鬱屈とそれでも楽屋から離れられない執着。2人の個性の違いとバランスの良さが作品をきれいにまとめていたように思える。
この芝居の面白さは、劇中で使われるたくさんの過去戯曲のセリフにもあるだろう。『かもめ』を中心に、さまざまな戯曲が各場面を彩る。彼女たちの生きた時代ごとの翻訳の違いなども面白い。
その膨大な台詞と劇中の場面の心情と。彼女たちの生涯の憧れの1本は何だったのか、観終わってから気になったりもした。
たくさんの方々が演じてきた戯曲を、今回の岡崎さんの演出は真正面から丁寧に立ち上げて、執着や報われない哀しみの中にもどこか甘やかな憧れを感じさせた。

江戸系 宵蛍
あやめ十八番
吉祥寺シアター(東京都)
2020/11/12 (木) ~ 2020/11/16 (月)公演終了
満足度★★★★★
鑑賞日2020/11/15 (日) 19:00
楽隊の演奏が振動となって身体に伝わる。人々の足取りが床越しに感じられる。観に来てよかった、と客席で思う。
幻の2020オリンピックと昭和39年のオリンピックをつなぐ怒涛の物語に引き込まれ、巧みなミザンスから目が離せない。現代劇でさえ古典のエレガンスが香る、あやめ十八番らしさ。
終演のアナウンスをかき消すように拍手が鳴り続け、上手から飛び出してきた主宰が楽隊とキャストを手招きする。立ち位置を確認するように登場した人々がもう一度客席に向き合うと、一際大きな喝采が響いて会場内の温度が微かに上がった。

All My Sons
serial number(風琴工房改め)
シアタートラム(東京都)
2020/10/01 (木) ~ 2020/10/11 (日)公演終了
満足度★★★★★
鑑賞日2020/10/03 (土) 13:00
家族・罪・欺瞞・信頼・愛情・隣人……さまざまな要素が重なり絡まりつつ立ち上がっていく物語に息を飲む約2時間半。ずっしりと見応えがあった。キャストも皆さん素敵で、特に神野三鈴さんをはじめとする女優陣の演技に釘付けになった。
![審判[加藤義宗 一人芝居]](https://stage-image.corich.jp/img_stage/m/873/stage_87395.jpg?746418)
審判[加藤義宗 一人芝居]
義庵
シアター風姿花伝(東京都)
2020/09/09 (水) ~ 2020/09/13 (日)公演終了
満足度★★★★★
鑑賞日2020/09/13 (日) 14:00
劇中で自ら何度も言ったとおり、ヴァホフは平静であった。何度も揺れ動きながら、平静に理性的に言葉を紡ぎ、その上で自分たちの罪について人々に問う。閉じ込められていた間のことを語る時より助けられてからのことを語る様子に胸が痛む。そしてこれは罪ではなく愛の物語なのだと、改めて感じられた。
ときおり、加藤健一氏の語り口に似ている、と思ったけど、それはたぶん親子だからではなく演出家だから、だった気がする。演出家が俳優の場合にはままあることだ。(残念ながら加藤健一氏の『審判』は拝見していない。他の作品で拝見した印象である。双方をご覧になった方の感想を伺ってみたい気がする)

風吹く街の短篇集 第二章
グッドディスタンス
「劇」小劇場(東京都)
2020/08/26 (水) ~ 2020/08/30 (日)公演終了
満足度★★★★★
鑑賞日2020/08/29 (土) 12:30
『二度ところな!』を拝見。
ある家族の重ねてきた年月を、18年ぶりに会う兄と弟のやり取りで綴っていくオトナの会話劇。クスッと笑ったりじんわりしたり、気がつけばあっという間の約50分。脚本も演出も確かな手腕で、2人のキャストの魅力を引き出していた。

BLACK OUT
東京夜光
三鷹市芸術文化センター 星のホール(東京都)
2020/08/21 (金) ~ 2020/08/30 (日)公演終了
満足度★★★★★
鑑賞日2020/08/28 (金) 19:30
ネット上の感想に惹かれて観に行った。
商業演劇の演出助手をしつつ個人ユニットの主宰もしている主人公の葛藤とコロナ禍に翻弄された公演に携わる人々のを描く私小説的(?)演劇。ステージの上に新しい物語を紡ぐ人々の奮闘と誠実が胸に残った。

天保十二年のシェイクスピア【東京公演中止2月28日(金)~29日(土)/大阪公演中止3/5(木)~3/10(火)】
東宝
日生劇場(東京都)
2020/02/08 (土) ~ 2020/02/29 (土)公演終了
満足度★★★★★
鑑賞日2020/02/15 (土) 13:30
戯曲の面白さは重々承知していたけれど、大劇場を満たす祝祭感に圧倒された。鮮やかな色彩と音楽、そして何よりたくさんの言葉が人間の業や愚かさとともに生きるエネルギーを描き出した。

ののじにさすってごらん
やしゃご
こまばアゴラ劇場(東京都)
2020/10/22 (木) ~ 2020/11/01 (日)公演終了
満足度★★★★
近年個人的に赤丸急上昇の見逃せないユニット。
作・演出の伊藤氏の1人ユニットだけど常連の俳優陣もめちゃ好みで、ここ数年楽しみにしている。
今回も、なんていうか痛いくらい切実な日常を描いて胸にしみる。
細やかな生活感が今のリアルを映し出していた。

音楽劇 獅子吼
オールスタッフ
上野ストアハウス(東京都)
2020/10/21 (水) ~ 2020/11/01 (日)公演終了
満足度★★★★★
戦時下の動物園。老いた獅子と元飼育係の若者。
戦争という理不尽の中で、動物も軍人もそれぞれの矜持と愛情を試される。
浅田次郎の短編小説を音楽劇にした脚本と演出の手腕、少数先鋭のキャスト陣も見事。
特に、生演奏のお二人とコロスのお三方の確かな技術と表現力が物語に深みを加えた。

糸井版 摂州合邦辻
木ノ下歌舞伎
あうるすぽっと(東京都)
2020/10/22 (木) ~ 2020/10/26 (月)公演終了
満足度★★★★★
昨年3月に拝見し、また観たいと思っていた作品の再演。
壮絶な物語に組み込まれたゆるやかなメロディと動きによる独特の世界観に引き込まれる。
玉手御前役の内田さんや合邦道心役の武谷さんをはじめ魅力的なキャストが揃って目が離せない。
シンプルながら場面によって姿を変える美術も印象的。
物語の随所に過去の幸せな時間が埋め込まれるように描かれいて、それを観るといっそう胸が痛んだ。
