 公演情報
「ピテカントロプス・エレクトス」の観てきた!クチコミ一覧
公演情報
「ピテカントロプス・エレクトス」の観てきた!クチコミ一覧
-
実演鑑賞
満足度★★★★
鑑賞日2024/05/30 (木) 14:00
時を超える「穴」を通して問答を交わす猿人・原人・旧人・人類・未来人(?)……。
星新一の「おーい でてこーい」も想起しつつお得意の(?)能楽っぽい表現を愉しんで観ていたが終盤の「問いかけのラッシュ」が痛烈。
しかし事前に公開している「あらすじA」は比喩で裏に「あらすじB」があるって、もう一度観させる巧妙な策略では?(笑) -
実演鑑賞
会場に入ると、アクティングエリアの中央に穴(奈落)が開いていて、その四方をカラーコーンで囲っている。客席はその穴から距離をとり四方に設置され、穴を取り囲むような状況に。ゴリラっぽい着ぐるみを着た人が場内にいるが、作品タイトルから演出の一部と想像。この穴がタイムホールのように時間を繋ぐ存在となっており、穴を通して前時代(と言っても何万年単位だけれど)の「祖先」と対話する。類人猿からヒトへの時間を辿りつつ、その進化の過程から「知的生命における、生物的、あるいは社会的進化とは?」を見つめ直す…ような作品に、僕には見えました。
-
実演鑑賞
満足度★★★
台詞の言い方を制御するタイプの劇団だが、序盤はただただ単調であり、客席の入眠率も高かった。コンセプトや形式が特徴的なのかもしれないが、ただの戦略ではなく、芝居の面白さに結びついていると感じさせてほしかった。
ところどころドキリとはさせられる。客のことを丁寧に想定していないのか、続きを見せたくする仕掛けが薄く、こと主張に関しては過剰な説明台詞に聞こえた。
一方で進化は感じた。同時に、ゆえにこれでいいのかという疑問も涌き出た。 -
実演鑑賞
満足度★★★★
いろいろ考えるなあ、と言うのが印象。内容はメッセージ性も強く、嫌いじゃないのですが、少し単調な感じも否めない。もう少し変化があると入り込めたかもです。
でも、挑戦的な内容で、新鮮ではありました。 -
実演鑑賞
満足度★★★★
最初の30分というか、原人のパートになるまでが少々しんどかったというのが正直なところ。それ以降はなかなか面白かったのだが、最後の方はセリフが聞こえにくくなってしまったのが残念。劇場の使い方に☆を追加。
-
実演鑑賞
う~ん星の付け何処が悩み・・・
自分の好きなSFではあり
舞台の使い方もユニークで
何とも言えない記憶に残る作品なんだが
二時間の長丁場で
睡魔も襲ってきたし・・・
考え込むなぁ と
こんだけ
いろんな作品数観てきて
ここまで星評価を考え込んだ話は
今までで無かったデス -
実演鑑賞
満足度★★★★
会場入りすると、猿人さんがお出迎え?なんか嬉しい。実にスタイリッシュな舞台ですね。説明が丁寧で分かりやすいのですが、ちょっとくどさも感じました。
-
実演鑑賞
満足度★★★★
開演前、猿人と思しき者がモギリをしている場に現れたり、開演直前に劇空間に設えられた立ち入り禁止区域のコーンや侵入防止用の棒等を撤去する為に作業に入ったスタッフを邪魔してする悪戯が極めて面白い。追記6月3日0時38分
-
実演鑑賞
観念的な作品といった印象の異色作 というか意欲作。
舞台美術(設営)を始め、照明・音響といった技術も独特の雰囲気で、その中で極めてシンプルな演技が…。演技だけではなく、衣裳も含め余計なものを削ぎ落とし、内容そのもので描き伝えるといった意気込みを感じる。しかし、観客がそれを どれほど理解し吸収出来るか否か、評価が分かれるところ。
説明にある四幕、その表層は何となく解るが、その裏に潜ませた思いを汲み取ることは難しかった。終演後、カウンターに置かれてあった<あらすじ>の裏面を読んで、その意図を知った。
(上演時間2時間 途中休憩なし) -
実演鑑賞
満足度★★★★
とても面白いというか,そそられた舞台。会場入りして,まず囲み舞台であること,その真ん中に穴があることで,どのような芝居になるのかに関心。芝居が始まり,役者さんが登場,その所作や発声に能の気配満載で,自分の好みであることを確信。それぞれの場面場面の表現も能に通じるところが感じられる。ただ,芝居最後の言葉の洪水は,一つ一つの発言はよく理解できるのだが,全体としてこの芝居における意図,メッセージを掴みきれたかというと自信はない。ということで,観劇の感想は冒頭の一言になってしまった。
-
実演鑑賞
シアターイーストに足を踏み入れると、なんと!真ん中に四角い穴があって客席はその4面を取り囲んでいます。穴は工事用のコーンとコーンバーで守られていますが、監視しているスタッフさんの目を盗んでお猿がコーンを倒したりバーを外したり。その度スタッフさんが直しますが、お猿はまた隙を狙って・・・と攻防が続きます。受付でチケットを受け取る時に「面白い前説とかありますか?」と聞いたら「前説はないですが早めに入ったほうがいいですよ」と言っていたのはこれだったのね!とお猿さんとその後の展開に期待したのでした。
-
実演鑑賞
東京芸術劇場シアターイーストってこんなにレイアウト自由な劇場だったのか!と入ってみてビックリ
壁際の四方向全てに座席が配置された囲み舞台
どこが正面?ヒントになるものは舞台上に無いのだけれど、心配ご無用
どの座席列も正面、どこに座っても平等に鑑賞できます
(お目当ての役者さんがいる場合、その役者さんがどのラインの席に座れば好みの角度で観られるのかスタッフさんに聞いてみても良いのかもしれません)

 ゴージャス(2300)
ゴージャス(2300)
 じべ。(7236)
じべ。(7236)
 園田喬し(128)
園田喬し(128)
 レタス水上(107)
レタス水上(107)
 ひろ(2400)
ひろ(2400)
 ベンジャミン2号(1375)
ベンジャミン2号(1375)
 長寿郎(6252)
長寿郎(6252)
 バート(7932)
バート(7932)
 ハンダラ(11026)
ハンダラ(11026)
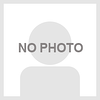 あかりのこ(1444)
あかりのこ(1444)
 uz(1416)
uz(1416)
 タッキー(4457)
タッキー(4457)
 ポチ様様(2123)
ポチ様様(2123)
 みなみ(3505)
みなみ(3505)
 コナン(1517)
コナン(1517)