 公演情報
「音楽劇 金鶏 二番花」の観てきた!クチコミ一覧
公演情報
「音楽劇 金鶏 二番花」の観てきた!クチコミ一覧
-
映像鑑賞
満足度★★★★★
正月に無料で観れるとのことだったので勧められて観ました!
最初の中野さんと金子さんの掛け合いのとこからぐっと演技に惹き込まれて見入ってしまいました。メインでお話している演者以外にも周りで動いている演者の動きもすごくて画面越しなのにほんとに昭和の世界に連れてかれたような気分でした。ぜひ劇場で観たかったなと思いました。お芝居を観るのは初めてでしたが観てよかったです。ありがとうございました! -
実演鑑賞
満足度★★★★★
テレビ黎明期、戦後復興、そのなかで力強く生きた人々。
時代背景をふんだんに盛り込みつつ、さまざまな立場の人生を丁寧かつ自然に交錯させ、観ている側を誰も置いていかない演出、あっという間の2時間45分。。ほんとうに素晴らしい作品です!
登場人物全てに愛着を感じずにはいられない、誰が観ても惹き込まれていく間口の広さ・柔軟さも兼ね備えたミュージカル、圧巻でした。
演者の皆さまの演技・歌唱・ダンス、どれをとっても魅力的で、観劇後もメロディーが脳内再生されていました。もちろんDVDも購入しました、
あやめ十八番で役者としての一面を開花してきた主演の浜端ヨウヘイさん。ミュージシャンとしての本領も存分に発揮しつつ、今作品でも素晴らしき存在感を放っておりました!
できることなら、再演を望まずにはいられない…心に残るたいせつな作品になりました! -
実演鑑賞
満足度★★★★★
あやめ十八番さんの舞台が大好きで、今回もガッチリと心を掴まれてしまいました。音楽がとても素晴らしかった。
そして多幸感に包まれて帰宅する日々が嬉しくて終わらないでほしい!!と心から思った舞台です。 -
映像鑑賞
満足度★★★★★
映像での鑑賞でしたが、実際に会場で観なかったことを後悔するレベルの素晴らしい舞台でした。もともとミュージカルというものに何故か苦手意識があったのですが完全に払拭されました。浜端ヨウヘイが熱く思いを伝えるシーンと中野亜美さんの歌のシーンが特に印象的で、本当に素晴らしいシーンでした。愛おしいもの というタイトルの曲のメロディがしばらく頭から離れませんでした。
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
この時代設定の脚本で、女性を力強く書いていて、朝ドラみたいな治安の良さに安心しました。
ミュージカルの質もものすごく高く、オリジナル楽曲楽曲の豊富さに驚きました。 -
映像鑑賞
満足度★★★★★
人生初めての演劇で様々な事に
驚かされっぱなしであっという間の時間でした
人形役の人と上で操っている人の動きが連動してて
細かい仕草や一つひとつの動作が
その場面をみんなで作り上げているんだと思いました
ハンガーラックをドアに見立てたり
脚立をベッドに見立てたりなど
小道具も工夫して使われており
それを役者さん達の演技で本物のように見せる力は
圧巻で違和感なく楽しむ事が出来ました
テレビを放送する為にどれだけの人が動き
苦労しているのだと改めて実感しました
綺麗に映したいという想いとそれ故に
傷つけてしまうという現実がとてももどかしく
(浜端ヨウヘイ)さん演じる宮さんが好きで
声も良く歌声も素敵で式では
自分も参列してるかのように泣きました(笑
(金子侑加)さん演じる喜代子と
(中野亜美)さん演じる黒柏繭の歌声は
とても綺麗で一瞬で引き込まれました
最後は互いを想い合ってる同士が出てきて
ほっこりする気持ちになりました
初めての演劇でしたが
初めてが『金鶏 二番花』で本当に良かったです
素敵な時間をありがとうございました -
実演鑑賞
満足度★★★★★
舞台、演劇ってストーリーがよくわからなかったり、世界観がブッ飛んでいたりして分かりづらかったりするのですが、とても分かりやすいストーリーで、よかったです。
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
鑑賞日2025/07/09 (水) 18:30
テレビ放送黎明期の試験放送等に関わった人々の奮闘を戦後日本の復興と重ねて音楽劇として描く。笑いや華やかさだけでなく切実な出来事もあるが、主人公2人の歌声と洒脱な魅力が作品の印象を明るくした。金子さんの歌声に物語を支える説得力があって見事だった。
-
実演鑑賞
満足度★★★
とても華やかな公演でした。
個人的にはダークなあやめ十八番さんが好きなので、前日譚である一番花の方が好みでしたが、こちらは万人受けするし見やすい作品だったのではと思います。楽隊のみなさんは相変わらず芸達者の域を超えていて流石でした。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
あやめ十八番の舞台の鑑賞はこの作品で3度目、この作品は3回観に行かせて頂きました 舞台演出、生演奏の音響も圧巻、役者さんの演技力、歌唱力全てにおいて素晴らしい作品でした
お話に入りこみ涙なしでは観れませんでした
家でも楽しみたかったのでDVDも購入しました -
実演鑑賞
満足度★★★★★
今まで舞台を観劇する機会があまりなくて、ドキドキしながら観に行ったのですが、シンプルな舞台ながら場面転換や演出が凄くて、めっちゃ惹き込まれました!!
特に主演のお二人の場面や、浜端ヨウヘイさんの熱の込もった演技と歌唱が心に残っています! -
実演鑑賞
満足度★★★★★
初めての舞台鑑賞。
簡素な舞台セットの上で、役者さん一人一人のお芝居で情景が浮かび上がってくることに感動。
演者の方も裏方の方も、みんなが何役もしながら作り上げられていることにも感動。
その中にあって、シンガーソングライターである浜端ヨウヘイの歌声には説得力がありました。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
浜端ヨウヘイさんが出演されると聞き、観に行きました。
笑ったり泣いたり感情が激しく揺れ動きました。
そう遠くない過去…
今では考えられないことがたくさんあったんだろうなと思いました。
自分の思いで、何でも自由にできる今。
それは当たり前なことではないんだ…と感じ、今できることを全力で、悔いなく生きていこうと思いました。
一度しか見ることができず、残念でした。
素晴らしい作品をありがとうございました。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
主演の浜端ヨウヘイさんを目当てに観賞。
どの役者さんも素晴らしく最初から最後まで目が離せなかった。
舞台装置や小物の使い方も面白かったです。
本職はシンガーソングライターのヨウヘイさん、次の舞台出演も楽しみになる役者っぷりでした!
DVDになるのも楽しみにしています。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
鑑賞日2025/07/11 (金) 13:30
レビュー系でのオーケストラピットと客席の間に横向きの花道があるものを想起させる(しかも一部は可動式の)舞台と上手上方のレフ板のような白い大きな円型の装置、舞台後方中央から下手に下げられたカーテン状の布等が特徴的な空間で語られるのはテレビ放送黎明期の逸話。
その内容はもちろんだが個人的には冒頭場面をはじめとして先述の円型装置・布などを活用した影を使った照明効果に心惹かれる。
また、実在のものをベースにしたのではなく完全オリジナルな(推定)劇中歌にも感嘆。
さらに戦争が人々に残したものをさりげなく盛り込み声高ではなく反戦を訴えたのもイイ。
あと、狂言回し的な役どころを演ずる金子侑加・中野亜美お二方のメインパート(過去)と現在パートの老若の演じ分けも見事。
これだけのものがB席3000円ってウソだろ!?

 うみ(1)
うみ(1)
 うにしょうゆプリン(1)
うにしょうゆプリン(1)
 マジメ(1)
マジメ(1)
 yoshy(90)
yoshy(90)
 Miiiiisaki(2)
Miiiiisaki(2)
 ぽっちゃま(1)
ぽっちゃま(1)
 ささき(28)
ささき(28)
 ぐみ(1)
ぐみ(1)
 3匹の子ぶたのパパ(3)
3匹の子ぶたのパパ(3)
 てつお(1)
てつお(1)
 kiki(609)
kiki(609)
 REI(15)
REI(15)
 のりぷー(1)
のりぷー(1)
 みほ(1)
みほ(1)
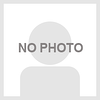 ミノリ(2)
ミノリ(2)
 TAIJI(1)
TAIJI(1)
 うーじこーじ(1)
うーじこーじ(1)
 ちか(1)
ちか(1)
 かためかよ(1)
かためかよ(1)
 じべ。(7236)
じべ。(7236)