 公演情報
「ストレイト・ライン・クレイジー」の観てきた!クチコミ一覧
公演情報
「ストレイト・ライン・クレイジー」の観てきた!クチコミ一覧
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
一公演で同演目を3度観るというのは多分初。実は二回目を誤って最初観たのと同じ星組を観たがためにこれで花組を観なきゃバランス取れないし、と(こじつけて)「変化」を観たさに観劇した。
見比べは興味深い。プレビューは生硬さが却って無駄を削いだ芝居の輪郭を見せ、「おっ」と思わせたのだが、二度目は色々探り始めてか、芝居が少し「軟」に寄り、初日よりも台詞が回っていなかった(人がいた)のが残念だった。
日を置いて観た今回の花組は、熟した芝居。老舗劇場スズナリという演劇の精?が、芝居に微笑む瞬間があった。客席の拍手が程よく力強く響いていた。こういうのが正しい拍手のあり方。ダブルは必要ない。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
鑑賞日2023/07/24 (月) 19:00
久しぶりの燐光群、劇団の力をみせる公演だった。正しい、とはどういうことか。個人にとって、市民にとって、国にとっての正しさはそれぞれ違う。自分の正しさを主張し衝突し、ずれていく人々。動いていく時代。膨大な台詞の波に運ばれながら、人生の深みと混沌を感じさせる刺激的な演劇。見応えたっぷり。
-
実演鑑賞
満足度★★★★
行政・政治家の善意と先見性が大事なのか、住民・ジャーナリストの声が大事なのか。いまだに解決のつかない永遠の問いを、あらためて考えさせる舞台だった。
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
日時によって星組、花組Wキャスト上演である、どの役を誰が演ずるかテイストの違いを楽しむこともできる。(花組を拝見)
2部構成、休憩なしの2時間25分程。一瞬たりとも目が離せない。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
鑑賞日2023/07/20 (木) 14:00
座席1階
ニューヨークのマスタービルダーと呼ばれた都市計画・建設者であるロバート・モーゼスの物語。ストレート・ライン・クレイジーとは、先住の都市住民を追い出してもまっすぐな高速道を通そうとした彼の人生につけられたニックネームだろう。
産業が興り、従事する人たちが集住して都市ができていくが、そのまま放置していては無秩序な街になる。都市の基幹は道路だ。都市計画は、道路をいかように通していくかということに集約されると言ってよい。
ただ、道路建設と言っても単純ではない。特に、既に建物が集まりコミュニティーができているような地域では、コミュニティーを守りたいという住民と、都市全体の交通網を考えた都市計画当局とは衝突することが多い。東京の都市計画道路は関東大震災後というほぼゼロからのスタートで後藤新平というリーダーが辣腕をふるって骨格ができた。だが、戦後の復興計画で道路建設がうまくいかなかったのは、後藤のようなリーダーが東京都にいなかったからだと自分は思う。朝鮮戦争特需で街が急速に発展する中で、東京都が環状道路を建設していくのは至難の業だった。全部で8本ある都心の環状道路の中で、環状三号線など計画倒れになっている道路が依然として残り、都心の渋滞をひどくしている。
この演劇の上演地である下北沢も、東京都が通そうとしている都市計画道路がある。裁判にまでなった小田急線高架化は断念され地下化となり、元線路だった場所は歩いて楽しむ、今やテレビドラマに何度も登場するトレンディースポットに変貌した。立ち退きを伴う道路建設は、北朝鮮の将軍様のような独裁者でもいない限り、今や不可能に近い。下北沢でこの演目が上演されたのは、何だか因縁みたいなものを感じる。
物語はモーゼスがニューヨーク近郊のロングアイランドを庶民の避暑地にするために二本の高速道を建設する場面から始まる。土地所有者である富豪たちとの強硬な交渉や、法の手続きを無視してまで進める仕事ぶりにまず、驚かされる。まさに人間ブルドーザーだ。日本で言えば、田中角栄のようなものだ。懸命に付いていく部下たちが痛々しいが、そこには庶民の生活向上という納得できる理屈があった。
戦争を経て、経済成長の中でニューヨークマンハッタンの高速道整備は難渋する。モーゼスはやり方を変えない。都市生活者として成長している市民たちが組織する反対運動の力を見誤って、時代の流れと共に計画は頓挫していく。「人間ブルドーザー」が都市の発展に力を発揮した時代は既に終わり、都市の成熟にはブルドーザーは害悪となっていた。しかも、彼が信奉した車社会に疑問が投げかけられようとしていた。
高速道計画を阻んだワシントンスクエアは車両通行禁止に。市民がそぞろ歩きをしながら都心の生活を満喫するという今のスタイルの萌芽となった。ニューヨークにはかつての高架鉄道の跡地を遊歩道にするなど、都市遺産というべきモニュメントがトレンディースポットになっている。上演劇場のスズナリがある下北沢のように。
さて、今作は力のある燐光群の看板俳優たちが遺憾なく実力を発揮し、見応えのある舞台に仕上がっている。2時間の上演時間の間、迫力のある会話のやり取りが続き、舞台から目が離せない。モーゼスの人生とは別に、民主主義と都市計画、貧困と富裕など考えさせられるテーマが散りばめられ、観劇後の一杯の席のネタには事欠かない。観てよかったと思える舞台だった。 -
実演鑑賞
満足度★★★★
内容的には燐光群の今までの演目のような社会問題を扱っているイギリスの作家の翻訳劇である。燐光群40周年の記念公演という。もうそんなに年月がたったのかと感慨もある。
いつもの正邪明白、立場明白の戯曲ではなくて、一頃よく上演されていたインフォメーションドラマ、のタッチである。そういえば、坂手の初期の作品は、よく考え抜いたこの手の作品があったな、ト思い出す。「天皇と接吻」「海の沸点」、多作の作者だからすぐには思い出せないが、フレッシュな視点から現実に発言するドラマだった。しかも見ていて面白い。
今回の作品も、演劇激戦区の英米市場の作品だけに、都市開発問題を扱っていてもなかなか手が込んでいる。ニューヨークの都市計画を強引に推し進めた官僚の功罪を問うドラマである。1920年代後半、大恐慌の前、この官僚(大西孝洋)が、利用できる政治家(川中健次郎)や腹心の部下(秘書、技師・((竹山尚史)大健闘)を、自己の構想のママ使い倒して、平民の幸福のために自動車社会をスムースに実現できるよう近代的な都市計画を実現していく。ここまでが前半で、後半はそれから30年(1950年代後半)。官僚は、下町改革に取り組むが、ヴィレッジの多様な住民の反対に遭って挫折し、腹心たちも離れていく。
関東大震災後の後藤新平の改革はどうだったかと問うようなもので、大都市の住民にはどこでも共通する問題をうまくすくい上げている。最後に、ヴィレッジは現在NYで住むには最高級住宅地になっている、というオチがついている。
大都市住民とその環境整備の公と私を巡って、現在も大きな問題を抱えた都市問題を多角的に扱っており、一つ一つの論点を巡っても、限りない議論が生まれる。そこをあまり一方的な視点に落ちず、また、日本ではよくある人情話に落とし込まず、2時間20分、休憩なしで押し切った。多面的な情報を仕組んだ戯曲のうまさが第一の見所である。
燐光群の俳優たちも初期からの人たちも多くこう言うドラマには慣れていて、ソツはない。しかし、いつも感じることだが、役が見物が楽しめるように膨らまない。必要ないと思っているのかも知れないが、秘書の役なんかもっと面白くやれるのに、と思ってしまう。せっかく森尾舞という技術、ガラ抜群の女優を呼んできているのに、これでは勿体ない。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
久々に燐光群らしい切れ味の舞台を観た。
演劇との遭遇の「幸運さ」を実感していた演劇観始めの頃(感動そして衝撃を与える舞台に当たる確率がえらく高く感じたものだった)、燐光群の作品の幾つかもそれに含まれた。スズナリでは「最後の一人までが全体である」「だるまさんがころんだ」にやられたが、今回は当時を彷彿する舞台の空気感がある。ただし戯曲は坂手洋二作ではなく2005年以来燐光群が日本初演を重ねてきたデヴィッド・ヘアーの近作。「ニューヨークを作った」と言われる実在した男の人生を、彼の最も輝いた時代と、栄光に陰りが差す時代の二部構成で描く。スリリングな台詞の応酬は往時のアメリカ(1930年代)の世相が進歩を牽引する主人公(守旧派に当たる地主たちとの格闘もある)の信念に寄り添うという結果に着地したればこその躍動。辛辣さも程よい酸味である所、後半では意を尽くしての部下の批判も長年の同僚の助言も当人には届かない徒労感が宙に漂う。一人の人生はアメリカ現代史を雄弁に語らせ、時代と人とに思いを馳せる。
この公演に関するtwitter
初日1週間前から「団体名」と「公演タイトル」を含むツイートを自動表示します。
(ツイート取得対象にするテキストは公演情報編集ページで設定できます。)
-
書きました。都市を創るのは誰か? 都市は誰のものなのか? 燐光群『 ストレイト・ライン・クレイジー』上演|堤 広志 - 不要不急ではなく常に“要急”な舞台芸術学|NewsPicks https://t.co/gqRPIkQDNK #NewsPicksトピックス
2年以上前
-
◆チラシ折り込み代行◆ 本日7月4日(火)締切の公演をご紹介します(7/10)。 ・燐光群 『ストレイト・ライン・クレイジー』 https://t.co/wDsJfg5SBc こちらの公演で、チラシによる宣伝をしていただけます… https://t.co/rsf9cafsyK
2年以上前

 tottory(3001)
tottory(3001)
 よしこ(13)
よしこ(13)
 Takashi Kitamura(773)
Takashi Kitamura(773)
 ハンダラ(11003)
ハンダラ(11003)
 かず(685)
かず(685)
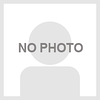 旗森(778)
旗森(778)
 tottory(3001)
tottory(3001)
 タッキー(4433)
タッキー(4433)



