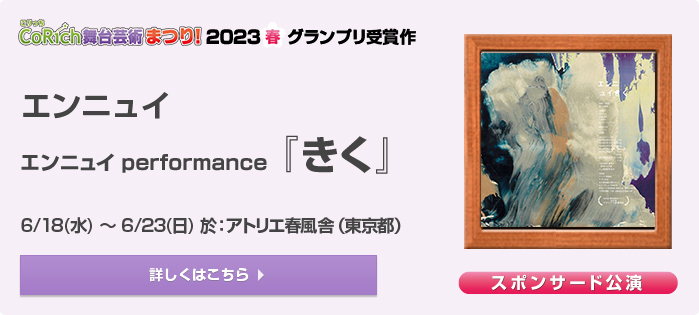CoRich舞台芸術まつり!2023春・グランプリ受賞作のエンニュイ『きく』が、こりっちスポンサード公演として2024年6/18(火)~23(日)にアトリエ春風舎(東京都)にて再演されます。
⇒ 特設ページ
⇒ グランプリ受賞ページ
⇒ 審査員クチコミ評
公演関係者の皆様(青木省二さん(ドラマトゥルク)、高畑陸さん(出演・撮影)、長谷川優貴さん(主宰・作・演出) ※五十音順)にZoomでお話を伺いました。
| インタビュアー |
グランプリ受賞おめでとうございます!まずは、応募をしようと思ったきっかけや理由からお聞かせください。 |
|
|
本作をお手伝いして下さったダンサーの木皮成さんに勧めていただいたことが最初のきっかけでした。CoRichのことは知っていたんですけど、この催しは知らなかったんですよ。それで要項を見たら、締切が数日後に迫っていたのでそのまますぐ応募しました。 |
長谷川優貴さん | |
|
僕は、CoRich舞台芸術まつり!に照準を合わせて作品を作るのではなく、作品そのものが登録できる形式がすごくいいなと思いました。「いつも通りのエンニュイをやればいいのだ」と。そう思えたんですよね。 |
青木省二さん | |
|
グランプリ賞金が100万円と聞いた時は、やっぱりわくわくしましたね(笑)。長谷川さんもお笑い芸人で自分もコントをやっていたので、お笑いコンテストを思い出したりしつつ「是非やりましょう!」と盛り上がっていました。 |
高畑陸さん | |
|
ちょうどその前の年に、神奈川で行われる演劇大会に出る予定だったのですが、コロナ感染者が出て見送ったんですよ。それの賞金も100万円だったので、最初は取り戻すような気持ちでした(笑)。 |
長谷川優貴さん | |
グランプリ受賞後の変化 |
||
| インタビュアー |
グランプリ受賞発表時の皆さんの心境や周りの反応は? |
|
|
僕は最終の10組に残った時点で「グランプリ受賞するかも」と思ったんですよ。特に根拠があったわけではなく、本当に漠然となんですけど…。だから発表時も僕が一番驚いてなかった気がします。長谷川さんはめちゃくちゃ驚いていましたよね(笑)。 |
青木省二さん | |
|
僕はアガリスクエンターテイメントさんが受賞すると思い込んでいたからすごくぼーっとしていて、名前を呼ばれた時に思わず聞き返してしまいました。そのくらい驚きが勝っていました。でも、受賞後には初対面の方からも「グランプリ取りましたよね」って声をかけてもらうことが増えて、すごく嬉しかったです。プロフィールにも受賞歴が書けるようになって、何かしらの申請の度に喜びを実感しています。 |
長谷川優貴さん | |
|
僕が受賞の喜びを最も実感したのは審査員の方々の選評を読んだ時でした。皆さんが選定における考えをそれぞれの言葉で書いて下さっていることがすごく嬉しかったんですよね。みなさんの考え方が違うところも含めてすごく豊かな選評だと感じました。 |
高畑陸さん | |
|
こういう受賞って、みんなで結果を待って瞬間的な喜びを分かち合って…みたいなイメージがあったんですけど、実際は長谷川からの伝達で各々が知り、個々でじわじわと喜ぶ感じでしたよね。一時的に高揚するというよりも、平均的にずっと嬉しいみたいな感触。思っていたよりも冷静に受け止めながら、「よし、次行くぞ!」と先を見つめられていた気がします。 |
青木省二さん |

『きく』舞台写真
| インタビュアー |
初応募にして初受賞でした!これまでの歩みを振り返って今思うことは? |
|
|
僕は学生時代から演劇をやっていたわけでもないし、エンニュイという団体は劇団という感じでもありません。一人のお笑い芸人が仲間もいない中急に演劇を始め、右も左もわからずやってきた中で一緒に作ってくれる人と出会い、こういった受賞をいただくことができました。だから、今まさに「ツテがなければ演劇ってできないのかな」とか「どうやって劇場借りたらいいのかわからない」って思っている人たちでも面白い作品を作っていたら、こうした賞を取ることができるかもしれない。僕たちの受賞をきっかけに、今後もどこからどのようにして現れたかわからない団体が演劇を始めたり、続けたりしてくれたら嬉しいです。 |
長谷川優貴さん | |
| インタビュアー |
受賞作は「きく」という行為にフォーカスした作品ですが、創作にあたってはどういうところを工夫されたのでしょうか? |
|
|
実は本作は数年前に初演を行っているんです。そこから一度僕が一人になって、新たなメンバーでもう一度やろうと動き出したのが昨年でした。元々は僕の母親がガンで亡くなったこと、その時の周囲との会話から着想を得て生まれた作品。話す人と聞く人との間に生じるズレ、例えば、相手は聞いてくれているのに「どうしてもっと親身になってくれないんだ」と思ってしまった自分の感覚とかを具現化できないかっていうところが発端でした。作品の中心に物語があるわけではなく、ただ話聞くだけの話なので、「どういうふうに創作をしていけばいいんだろう」というところから話し合いました。そこからさらにリクリエーションとして観客の方にどう伝えるか、っていうことを練っていくような感じだったので難しい創作ではありましたね。 |
長谷川優貴さん | |
|
最近は本屋に行っても「きく力」「きく技術」なんてタイトルが並んでいたりするし、「きくこと」自体がブームを通り越して道徳みたいなものになっているんですよね。実体験としても、近頃はなんだかいやに人が自分の話を聞いてくれているな、という感覚がありました。そういった傾聴感を感じる一方で、「人の話を1から10まで聞いていられない」っていう人間の野性もやっぱりあるんですよね。こうやってインタビューを受けていても、残りの二人が話している時に僕は次に何を話すか考えていたりするわけじゃないですか。「8割聞いて2割話すといい」とかよく言われていますけど、二人の会話で互いがこれを実践したら、ほとんど沈黙の状況になるんです(笑)。それくらい「きく」という行為を巡る解像度って実は低い。本作はそういった風潮への批判的な意味合いも含んでいます。長谷川の持つ実感と傾聴ブームの解像度の低さみたいなものが重なった結果生まれた作品だと思っています。 |
青木省二さん |

『きく』舞台写真
| インタビュアー |
創作・稽古の中で何か印象的だったことは? |
|
|
まさに「きく」というテーマ通り、各々がナチュラルな「きく状態」になれるか、というのが創作の起点だったような気がします。キャストの皆さんはそのあたりが非常に達者な方ばかりでした。僕は映像撮影もあったので、半分観客というか視聴者的な立場だったんです。その視点から稽古を見て思ったのは、プレイングとしての「きくことへの傲慢さ」と「きくことにおける協調性」の調整の繊細さ。双方のつまみを瞬間毎に回すように、楽しんだり試行錯誤したりしながらみなさんが絶妙な塩梅を探っているように見えました。俳優の調整の細やかさを痛感する現場でもありました。 |
高畑陸さん | |
|
高畑君にはある大会の実況者として出演してもらったのですが、その箇所のセリフは全部アドリブなんですよ。上演後に岸田國士戯曲賞の推薦をいただいて台本に起こさなくてはいけなくなったのですが、その時に初めて高畑君が喋っている音声を聞きながら文字を打ち込んでいくっていうことをやって「僕は一体何をやってるんだ」って思いましたね。まさに「きく」ではあるんですけど(笑)。 |
長谷川優貴さん | |
|
長谷川はコミュニケーションが好きな人間であり作家だから、「誰かの言ったことや感じたことに対して何を考えるか」っていうことを大事にしているのだと思います。それは「世界の考え方が今どうなっているのか」を考えることでもあるんですよね。リアルなコミュニケーションと世界の重なりがそのまま作品へと流れていく。そこはエンニュイの演劇や本作の大きな特徴であり魅力なんじゃないかなと思います。 |
青木省二さん | |
| インタビュアー |
昨年の上演時に寄せられた観客からの感想や反応で印象的だったものはありますか? |
|
|
エンニュイの演劇は毎回意見がすごく割れるのですが、そんな中で本作は「刺さった」と言って下さる方が想像以上に多かったんですよ。構造的にはシンプルなのですが、複雑に見ようとしたら見える造りでもあったので、シンプルな方向で届けられたという実感がすごく嬉しかったです。 |
長谷川優貴さん | |
|
僕は観客として2019年の初演を観ていて、その時は強い個が点々と集まっているような面白みや魅力を感じていたのですが、今回は「個人であること」と「チームとして1つになっていること」のバランス感みたいなものも伝わった気がしてすごく嬉しかったです。作品全体に触れていただいている感想も多くて、チーム感というか、一体的なニュアンスも多少は伝わったのだ、という実感がありました。 |
高畑陸さん | |
|
批判的な意見からも発見がありました。観客の方は僕たちが思っている以上に作者の意図を読み取ろうとされるんですよね。必ずしも全ての演劇に言いたいことが存在するわけではないですが、観客の方は座って集中しなければならない環境も相まって「この人は何が言いたいのだろう」っていう視点を持たざるを得ません。でも例えば、もっと自由でいつでも出入りOK、となったら、それぞれが好きなところを見たり、印象に残ったところだけを持ち帰るみたいなこともできるのかもしれない。そういった、客席の設定から考え直す重要さについても付随的に考えました。 |
青木省二さん | |
再演について |
||
| インタビュアー |
昨年の公演と比べて、この再演ではどんな変化が生まれそうですか? |
|
|
今はまだ100万円のパネルとともに集合写真を撮ることしかできていないんですよ(笑)。でも、一通りのことをつかんではいるので、今までにない安心した状態で作品と向き合ったり、これからの稽古でどんどん新しいことをやっていけることがすごく嬉しいです。前回の会場である三鷹SCOOLが真っ白だったのに対して、今回のアトリエ春風舎は真っ黒。そこだけでも印象は随分変わると思いますし、声の響きや立つ場所にも面白い変化が生まれそうです。あと、春風舎の螺旋階段やその高低差をうまく使いたいと思っています。出演者の方々は一緒ですけど、1年前とは身体や考えも変わっているはずなので、今しか生まれない作品として面白くできたらと思っています。 |
長谷川優貴さん | |
|
前回はマイクと小さなミキサーを使っていたのですが、今回は音にもさらなる工夫を凝らしたいです。この1年を通じて身についた知識や興味もあるので、そのあたりを活かして新しいことができたらいいなと思っています。僕は、半分は技術マン、もう半分はキャストとしての参加なので、ただのスタッフとしてのオペレーションではなく、作品の根源と絡む様なアプローチで提案ができたらと思っています。人間としてそこにいながら、いかにテクニカルなムーブができるか。本作はまさにその実践なので、今回もさらなる追及ができたらと思います。 |
高畑陸さん | |
|
僕が今この瞬間まさに感じているのは、インタビューを受けている今の状態やその面白さをどうにか作品に活かせないか、ということでした。この1時間、脳の中で“聞く野”と“話す野”が熱くなりながら喋っている感じで、こんなにも考えながら話す場はそうないだろうな、と痛感したんですよね。 |
青木省二さん | |
|
たしかに!インタビューはまさに聞く場であり、話す場でもありますよね。 |
長谷川優貴さん | |
|
稽古の一環みたいでしたよね。僕も『きく』の創作中みたいだ!ってすごく思いました。 |
高畑陸さん | |
|
この状況や体感を携えながら稽古場に行くと、何か別の補助線が引けたり、新たなシーンが生まれる可能性に繋がったりするかもしれない。 貴重なケーススタディをありがとうございました!(笑)。 |
青木省二さん |

『きく』舞台写真
| インタビュアー |
このインタビューすらも創作の一環になりうる『きく』、ますます楽しみです!最後に意気込みをお願いします。 |
|
|
エンニュイの作品はコミュニケーションのお話が多いのですが、中でも本作はその持ち味が色濃く出ている作品だと思います。多くの人がわかりきっているって思うことがわかりきってないことで苦しんでいる人もいっぱいいる。そういう人たちも含めて見捨てられる人がいないように、様々な状況の人たちにとって何か一つでも気づきや救いになるような多角的な作品にしたいと思っています。もしかしたら、自分に似ているキャラクターが批判されるシーンもあるかもしれないけど、肯定されるときも必ずある作品なので、そういった体感を楽しんでもらえたら。 主人公がいるわけでもその物語を追うわけでもないので、誰もが自分の感覚で自由に気軽に観てもらえたら嬉しいです。 |
長谷川優貴さん | |
|
コミュニケーションってやっぱり緊張するものだし、それはその正体がよくわからないからだと思うんですよね。例えば、「きくこと」に限らず、めちゃめちゃ適当に話したことが相手の深い呪いになったりすることもあるし、それは複雑さというよりは単純さゆえの拗れであったりする。『きく』という作品はそういったコミュニケーションを巡る重層的な問題を掬い上げた作品でもあるので、コミュニケーションについてなにか知りたいと思っている方にとって面白がれる作品になっているかもしれません。 |
青木省二さん | |
|
これまでのエンニュイの演劇はどちらかというとオルタナティブ的なムーブの中で育った方々が観に来て下さっていた印象なのですが、グランプリ受賞という一つのスマッシュヒットが出たことで新たな拡がりが生まれたような気がしています。スポンサード公演として大人の力もお借りしつつ、バージョンアップした作品の姿をお届けできたらと思っています。誰のことも区別せず、誰のことも“きく”スタンスで。そういった作品の根幹、エンニュイの特徴をより多くの人に観てもらえたら嬉しいです。 |
高畑陸さん |

集合写真
インタビュー実施日:2024年5月1日 ZOOMにて 取材・文:丘田ミイ子 ※文中敬称略