 公演情報
「ズベズダ」の観てきた!クチコミ一覧
公演情報
「ズベズダ」の観てきた!クチコミ一覧
-
実演鑑賞
満足度★★★★★
鑑賞日2025/02/24 (月) 13:00
縦断上演、つまり三部作の通し上演で1日じっくり宇宙と向き合った。
彼らの情熱、ロケット発射時の振動、祖国への思い、繰り返される挑戦と失敗、その先の成功、命の重さ、それぞれの思惑。仕事帰りに夜空を見上げた。濃密な1日。いい舞台を観た、と思う。 -
実演鑑賞
2021年の青年座上演作(180分)を、作家自身の劇団で大幅にパワーアップして120分✕三部作として上演。3月2日までザ・ポケット。
https://kawahira.cocolog-nifty.com/fringe/2025/03/post-4955c3.html -
実演鑑賞
満足度★★★
この{ズべズダ」は青年座公演で21年に見ている、素材は二次大戦のナチの技術者争奪戦の米ソ秘話がその後の両国の宇宙開発に現在にまでも影を落としていくハナシだ。思わず耳をそばだてるような秘話に巧み盛るのは上手い野木萌葱が青年座に書いた本で、よく知らない世界と言うこともあって面白かった。今回は全体をさらに詳しく全編三部にして一挙上演と言う。全6時間半と聞いて、長くなったのなら後半だろうと当てをつけて第三部を見た。今回は作者自身の劇団パラドックス定数に小劇場ではよく見る俳優を集めての公演である。
これがかなり当てが外れた。
青年座版の内容は今回では一部、二部になっているらしく、第三部のパラドックス版はアメリカが月面到着に成功した後の取り残されたソ連科学者の内部抗争が軸になっている。従って、第一部で特に面白かった、米ソという異国にいわば拉致されたドイツ科学者たちとソ連の科学者との、科学の発展と成果をかけた米ソ対立、と言うこのストーリーの面白く、おいしいクライマックスは、はじまってすぐ、慌ただしく決着が付いて、第三部の中身はほとんどがその後の後始末になっていて、すっぱり落ちていて意気あがらない。ソ連が負けたのは社会体制にも原因はあるわけで、先の青年座版では当時我々にもおなじみだった米ソのリーダーたちも少しは登場してハナシが面白くなったのにそこもない(ワンシーンだけフルシチョフが出てくる)。次第に追い詰められていくソビエトと、その先端を任された科学者たちの苦悩は、ソビエト型国家予算の取り合いでしか描けないから、小国になった我が国の予算審議のようなチマチマしたよくあるハナシになってしまう。青年座版にあった米ソの情報合戦も科学的成果も勝負が一方的に付いてしまった後では発展させようもない。また、いいネタでもあるドイツ拉致科学者が三部では全く描かれなかった。
出演者たちの背景も役柄もはっきり設定されていなくて、ドラマのシーンとしては物足りない。つまり、アメリカにスパイに出かけるというのと、喰うためにNASAに転職するというのでは分けが違う。
青年座版では宇宙を思わせる抽象舞台で何もかも会話で処理していて、それが上手くいった。テキパキした出し入れもロケット発射も、照明も音響も頑張って効果を上げていた。3時間ほどある長尺だったが飽きずに見られた。三部では、アメリカの月到着のシーンがあるのに、そこへ至るまでの経過もふくめかなり速いスピードで事実報告のような進行になっていて、そこも疑問だ。そこのソ連側への衝撃が上手く描かれていないと、後が持たない。
三部のパラドックス版は(1,2部は見ていないから分からないが)そこもかなり不利だったとおもう。作者はこの話はどうしてもかきたかったと劇場パンフでは熱弁を振るっているので、是非改訂版を頑張って、もう少し大きい劇場でせめて、トラムや、あうるすぽっと(天井の高い小屋)でやって欲しいものだ。また、科学をドラマに中で大きな比重を置くのはこの作者の魅力だが、そこも今回は薄味で残念だった。総体でいうと、この第三部は折角の異色の企画のしめどころなのに、青年座が俳優も演出もでがたくまとめる方向で成功したのに比べると、作者、演出両立で時間もまとめる時間も足りなかったのではないかと思う。 -
実演鑑賞
満足度★★★★
鑑賞日2025/02/27 (木) 14:00
三部作全て観劇しました。ソビエト連邦からみたロケット・宇宙開発。第一部は黎明期から成長期、第二部は絶頂期、第三部は衰退期。国家の思惑に翻弄されながらアメリカNASAに立ち向かうソ連の科学者達の純粋な魂。月の石持ち帰り計画の失敗直後アメリカの月面着陸成功を祈る心に科学者の矜持を感じる。科学者・政治家達の活気がある第二部がもっとも迫力があり面白かった。
-
実演鑑賞
満足度★★★
第三部 1964〜2025
今三部作のテーマは唯一つ。SF小説の始祖、ジュール・ヴェルヌの言葉。「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」。想像できるということは実現可能ということ。その糸口を探せ。
コロリョフは人類史上初となる月探査衛星に「メチタ(夢)」と名付けた。最後まで夢見る男。
松本寛子さんがいい味。
是非観に行って頂きたい。 -
実演鑑賞
満足度★★★★
第二部 1957〜1964
1958年7月29日、ソ連への技術の遅れを挽回する為にアイゼンハワー大統領はNASA(アメリカ航空宇宙局)を発足させ、猛然と追い上げを図る。
今作こそこの三部作の魅力の要。セルゲイ・コロリョフと姿を見せぬヴェルナー・フォン・ブラウンのソ米対決こそが肝。メチャクチャ面白い。「お前ならどうする?」
必見。 -
実演鑑賞
満足度★★★
第一部 1947〜1957
第二次世界大戦の終結が見え始めた頃、連合国のアメリカとソビエト連邦はその後の世界情勢を見据える。この二つの大国の覇権争いになると。敗戦間近のナチス・ドイツは科学技術力が圧倒的に優れていた。この技術を自国のものとすべき、決して奴等に渡してはならない。
1944年に世界初の弾道ミサイルを開発した天才、ヴェルナー・フォン・ブラウンはアメリカにスタッフ数百人と亡命する。
一方、ソ連は研究者を家族込みで2万人拉致。ゼーリガー湖のゴロドムリャ島に監禁、その技術を徹底的に吐き出させた。
主演のセルゲイ・コロリョフ役植村宏司氏が第一声から声が枯れていた。三部縦断上演、大丈夫なのか?と不安が走る。だが何とか持ち直し最後には気にならなくなる。物凄い台詞の量、化け物に見えた。短髪の亜麻色の髪、遠目だと魔裟斗っぽい。少年時代からの空への夢、グライダー、航空機、更に宙へと。宇宙にまで人間は飛んで行ける。あらゆる困難を乗り越え、コロリョフは敵国に向けたロケット(ミサイル)の目的地を月面へと変えていった。国威発揚の名のもとに。
第一部のもう一人の主人公、アルベルト・レーザ(大柿友哉〈ゆうや〉氏)。後にソ連に帰化したナチス・ドイツの工学者。戦争協力なんかの為ではなく、セルゲイ・コロリョフの夢に賭けた。月に人は立つのだ。それは決して不可能なことではない。人間の叡智は更に進化していく。必ず成し遂げる。限りなく頭脳をフル回転させてそこにまで辿り着く。人間は生きながら進化できる稀有な生物だ。必ず行くのだ。
コロリョフと複雑な関係にあるエンジン設計士ヴァレンティン・グルシュコ(神農〈かみの〉直隆氏)、ロケットエンジン開発の要。1933年ジェット研究所で出会ったコロリョフとグルシュコは互いの才能を認め合った。だがスターリンの大粛清が始まり、密告が奨励される世の中に。1938年、グルシュコは反体制派の嫌疑で投獄、禁錮8年の刑。苦境に立たされた彼は司法取引に騙され、無実の同僚コロリョフを反体制派として告発してしまう。冤罪のコロリョフはシベリアの強制収容所コリマ金鉱山に送られ10年の刑。栄養失調からの壊血病で全ての歯が抜け落ち心臓病を患う。この地に送られて死んだ者は100万人を超えた。コロリョフの罪が免除されたのは1944年。後に自分を陥れた者がグルシュコであることを知る。当時の政治情勢として仕方ない事とはいえ、ずっと心の底に残るわだかまり。互いの能力を認めつつ、複雑な感情の人間関係は一生続いた。
岡本篤氏、前園あかりさん、松本寛子さん、3人組のキャラ立てが巧い。少ない人数で大河ドラマを綴るにはキャラとエピソードの凝縮と選別が要。
MVPはフルシチョフ第一書記役の今里真氏と国防工業大臣ドミトリー・ウスチノフ役の谷仲恵輔氏。JACROWを観ているような手慣れた手腕の政治劇。この二人のハイテンションで客席がパッと明るくなる。成田三樹夫や小池朝雄、遠藤辰雄の風格。出て来るだけで盛り上がる。
驚くのはこんなガチガチの理系話に詰め掛けた女性客の多さ。野木萌葱さんの信望か?
是非観に行って頂きたい。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
鑑賞日2025/02/24 (月) 13:00
縦断観劇。
芝居の展開が早い演出が宇宙開発のペースに合っていて小気味良かった。
時代のイベントとして認識している出来事を当時にリアルタイムに生きた擬似体験として感じる事が出来た。 -
実演鑑賞
満足度★★★★★
縦断上演を鑑賞。青年座版の2倍の長尺ということもあり、ストーリー展開のディティールがより詳しく描かれているし、主人公コロリョフの死後の話も、ほぼ現在に至るまでずいぶん入れられている。専門的な事柄や歴史についてよく調べられそこから緻密に創作が組み立てられた驚異的な台本だ。また、青年座版では演出ゆえかカラッとした明るさがあったように記憶しているが、本上演はパラドックス定数らしい基本的にシリアスな雰囲気(いくつか笑いをとる場面があるとしても)で照明を落とした暗めの場面も多用されていた。段差が付けられた簡素な舞台を巧く利用した演出はなかなか優れている。それにしても、難しい専門用語や発音しにくいロシア人の名前が散りばめられた大量のセリフを6時間も駆使し続けた俳優たちは絶賛に値する。

 kiki(609)
kiki(609)
 かわひ_(713)
かわひ_(713)
 旗森(778)
旗森(778)
 TAKEZO(80)
TAKEZO(80)
 ヴォンフルー(3012)
ヴォンフルー(3012)
 ヴォンフルー(3012)
ヴォンフルー(3012)
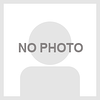 ヴォンフルー(3012)
ヴォンフルー(3012)
 JOBMAN(755)
JOBMAN(755)
 FIG(414)
FIG(414)