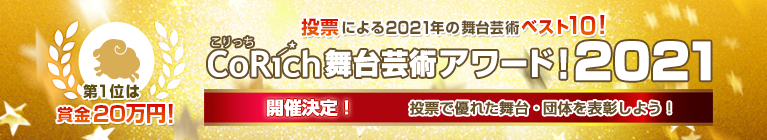「『砂の女』」への投票一覧
※投票内容を「非公表」に設定しているメンバーは表示されません。
| 投票者 | もらったコメント |
|---|---|
 はみ~にょ(1155) はみ~にょ(1155) |
4位に投票 実演鑑賞わぁ怖い。恐ろしい。いつの時代にもあるであろう閉塞感。舞台全体がいや、客席までも砂まみれな体感を感じてしまった。あぁ、ねっとりだわ。 |
 ガチャピン(525) ガチャピン(525) |
3位に投票 実演鑑賞観てきました。 現実的じゃない設定で、気軽に楽しめるタイプの芝居ではない。プロジェクションマッピングなどの演出は、さすがケラさん。とにかく仲村トオルさんが良い☆ |
 旗森(778) 旗森(778) |
8位に投票 実演鑑賞かって親しんだ世界をいま、目前に見て、それに勝る興奮を感じられるか、そこが、古典を再演する肝だろう。「砂の女」(1962)は日本の戦後文学の里程標となった作品、作者自身の脚本による映画(1964・勅使河原宏監督)もまた、世界的な評価を得た。その後、芝居にもなったようだが、草月ホールで見たような、見なかったような。それから六十年。 |