 公演情報
SPIRAL MOON「小刻みに戸惑う神様」の観てきた!クチコミとコメント
公演情報
SPIRAL MOON「小刻みに戸惑う神様」の観てきた!クチコミとコメント
-
実演鑑賞
満足度★★★★
面白い…お薦め。
公演のご案内に「芝居って、どれだけ上手に嘘をつけるか、そしてその嘘を受け入れられるか」とあったが、舞台という虚構の中に、人生で経験するであろう「葬儀」を嘘と現実の世界を上手く切り分けながら、それでいて融合している 一見矛盾したような観せ方が巧い。視覚的な場景描写、想像的にそこに居る人々の心情を浮かび上がらせることで、虚構の世界(芝居)の中で「葬儀」を経験することになる。同時に次元の違う存在によって 嘘としての「物語」を想像し、その面白さと醍醐味を知ることになる。
一般的に思われている「葬儀」という湿っぽさはなく、どちらかといえばカラッとしている。しかし、そこには地位や名誉ではなく、自分の思いで確かに歩んできた人の人生が観える。
上演前は懐かしい昭和歌謡「喝采」などが流れるが、歌詞「♪いつものように幕が開き♪」とは違い、アナウンスでこのような(コロナ禍)状況の中おいでいただき、といった謝辞。先のご案内に「SPIRAL MOONは歯を食いしばり舞台芸術が消えないよう頑張っている」…上演迄の苦労は想像に難くない、そんなことを思いつつ観劇。
(上演時間1時間45分 途中休憩なし)

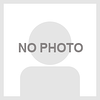 タッキー(3785)
タッキー(3785)